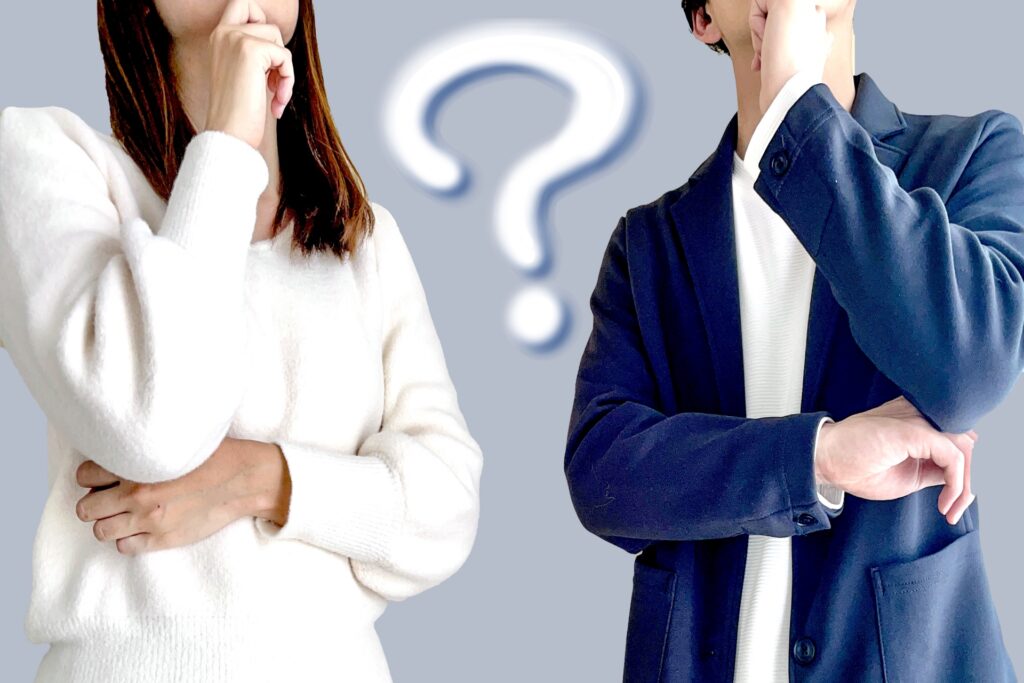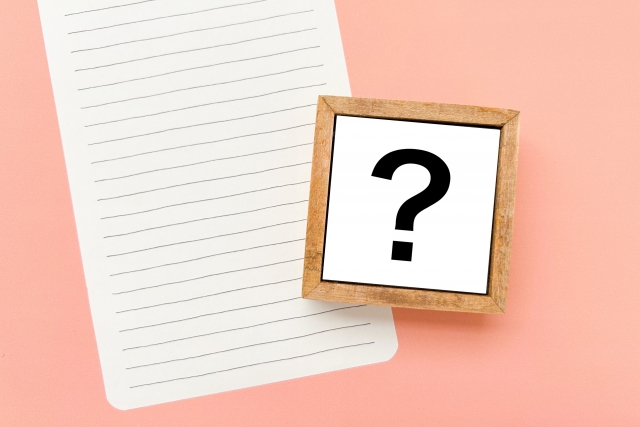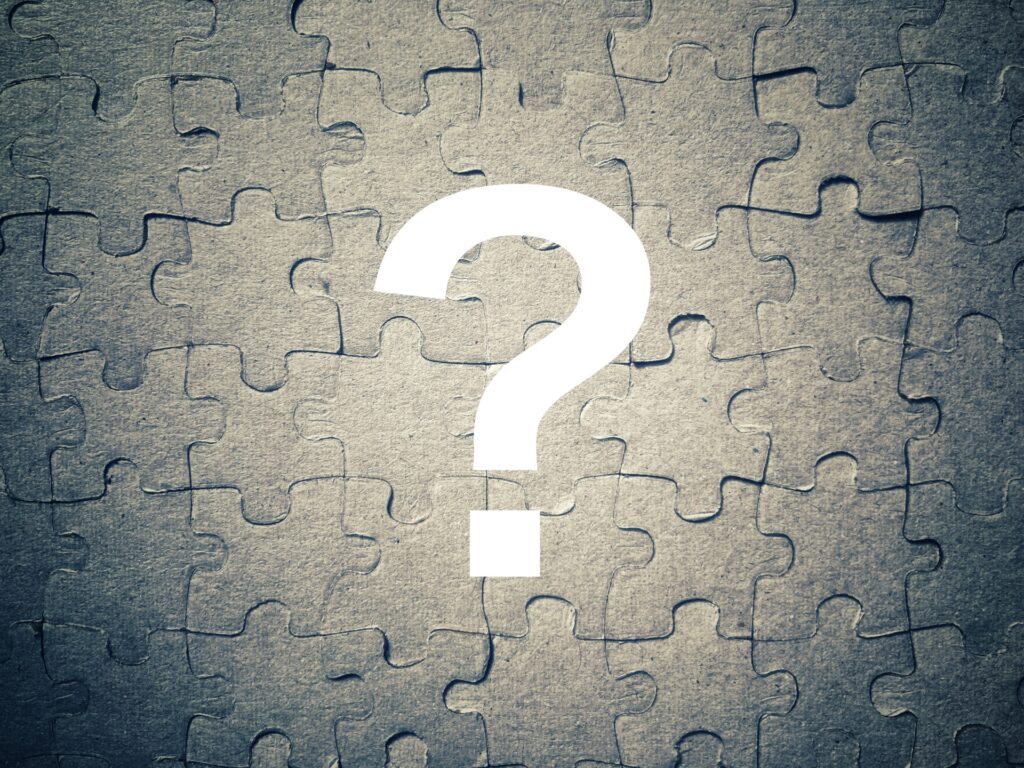こんにちは!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日は皆さんの会社生活で「もしも」のときに役立つ知識をお届けします。「始末書」と「顛末書」、似ているようで実は全然違うんです。ボクも以前は混同していたのですが、子どもの学校行事で遅刻しそうになって慌てて書類を提出したとき、「これは始末書じゃなくて顛末書ですよ」と言われて赤っ恥をかいた経験があります。そんな失敗を皆さんにはしてほしくないので、今回はしっかり違いを解説していきますね!
始末書と顛末書の基本的な違い
まず押さえておきたいのが、この二つの書類の基本的な違いです。一言でいうと、始末書は「反省文」、顛末書は「報告書」という性質の違いがあります。
始末書は、ミスやトラブルの経緯を報告しつつ、当事者の反省や謝罪の気持ちを表明するための文書です。一方、顛末書は事の顛末(てんまつ)、つまり一部始終を客観的に報告するための文書なんですね。
目的の違い
始末書と顛末書では、作成する目的がまったく異なります。
始末書は、不祥事やミスを起こした本人が反省し、謝罪の意を示すことが主な目的です。「すみませんでした、二度としません」という気持ちを伝える文書なんですね。
対して顛末書は、起きた問題の経緯や原因を客観的に報告し、再発防止策を示すことが目的です。「こういう経緯でこんなことが起きました、今後はこうします」という報告書的な性質を持っています。
作成者の違い
誰が書くのかという点でも大きな違いがあります。
始末書は基本的に不祥事やミスを起こした当事者本人が作成します。自分の行動を振り返り、反省するプロセスとしての意味合いも持っているんですね。
一方、顛末書は必ずしも当事者が書く必要はなく、現場担当者や直属の上司など、報告するのに最も適切な立場の人が作成することもあります。客観的な報告が重要なので、時には第三者の視点が必要になるわけです。
提出のタイミングと対象となるケース
始末書と顛末書は、提出するタイミングや対象となるケースも異なります。
始末書を提出するケース
始末書は比較的重大な問題が発生した際に提出を求められることが多いです。例えば:
- 会社の規定に違反した行為
- 金銭に関わる不正行為や虚偽報告
- 取引先への無礼な言動
- オフィス機器・建物などの破損やデータの紛失
- 連続無断欠勤のような重たい就業規則違反
- パワハラなどの深刻なハラスメント行為
- 取引先の信用を失墜させるような行為
これらは懲戒処分の対象となる可能性が高いケースが多いんです。ギュウギュウに詰まった電車の中で会社の機密情報を大声で話してしまったとか、そういう「やっちゃった…」というレベルの問題ですね。
顛末書を提出するケース
顛末書は、比較的軽微なミスや、客観的な事実確認が必要なケースで提出されます。例えば:
- 商品に不備があった場合
- サービスに不具合が生じた場合
- 手続きにミスがあった場合
- システムの不具合
- 社用車運転中の事故
- 発注や納品ミス
これらは事実関係の把握と再発防止が主な目的で、必ずしも懲戒処分につながるわけではありません。「あれ?なんかおかしいな」というレベルの問題に対して作成することが多いです。
記載内容の違い
始末書と顛末書では、書くべき内容にも大きな違いがあります。
始末書に記載すべき内容
始末書には以下のような内容を記載します:
- 問題が発生した日時や場所
- 問題の概要(簡潔に)
- 問題が発生した経緯
- 自分の責任の所在
- 反省の言葉と謝罪
- 再発防止に向けての誓約
特に反省と謝罪の部分が重要で、自分の行動を振り返り、真摯に反省する姿勢を示すことが求められます。「本当に申し訳ありませんでした。今後は絶対に同じ過ちを繰り返さないよう、細心の注意を払います」といった表現が必要になってきますね。
顛末書に記載すべき内容
顛末書には以下のような内容を記載します:
- 問題が発生した日時や場所
- 問題の詳細な内容
- 問題発生から解決までの経緯(時系列で詳細に)
- 原因の分析
- 現在の対応状況
- 再発防止策
顛末書では客観的な事実関係の報告が重要で、感情的な表現や主観的な意見は避けるべきです。「〇月〇日〇時に〇〇が発生。原因は△△であると推測される。再発防止のため□□の対策を講じる」というような、スッキリとした事実ベースの記述が求められます。
提出先と影響の違い
始末書と顛末書では、提出先や書類が与える影響も異なります。
提出先の違い
始末書は通常、当事者が直属の上司に提出します。場合によっては、社外(取引先やお客様など)に公表されることもあります。
一方、顛末書は基本的に社内向けに作成され、問題の内容によっては部門の責任者や経営層に提出されることもあります。
人事評価への影響
始末書は懲戒処分につながる可能性が高く、人事評価にマイナスの影響を与えることが多いです。会社によっては人事ファイルに保管されることもあります。
顛末書は基本的に事実確認と再発防止が目的なので、必ずしも人事評価に直接影響するわけではありません。ただし、同じようなミスを繰り返し顛末書の提出が複数回に及ぶ場合は、評価に影響することもあるでしょう。
書き方のポイント
それぞれの書類を効果的に作成するためのポイントをご紹介します。
始末書の書き方ポイント
- 手書きで作成するのが一般的(誠意を示すため)
- 敬語を正しく使用し、丁寧な文体で書く
- 事実関係は簡潔に、反省と謝罪は具体的に書く
- 言い訳や弁解は避ける
- 再発防止の誓約は具体的に記載する
顛末書の書き方ポイント
- パソコンで作成するのが一般的(客観性を保つため)
- 時系列に沿って論理的に記述する
- 専門用語は避け、誰が読んでも理解できる表現を使う
- 事実と推測を明確に区別する
- 再発防止策は具体的かつ実行可能なものを提案する
提出する際の注意点
最後に、これらの書類を提出する際の注意点をお伝えします。
- 事態が落ち着いてから提出する(感情的になっている状態での作成は避ける)
- 提出前に内容を再確認し、誤字脱字や事実誤認がないか確認する
- 会社の規定やフォーマットがある場合は、それに従う
- 上司や先輩に相談し、アドバイスを求めることも大切
- 提出後も再発防止に向けた行動を実践する
皆さん、始末書と顛末書の違いについて理解できましたか? 似ているようで全然違う二つの書類、いざというときに慌てないよう、今のうちに違いを押さえておくといいですね。
ボクたちの仕事人生では、ミスやトラブルは避けられないものです。大切なのは、ミスをしたときにどう対応するか。適切な書類を作成し、誠実に対応することで、むしろ信頼を高めるチャンスにもなります。
「失敗は成功の母」- トーマス・エジソン
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!ミスを恐れず、前向きに仕事に取り組んでいきましょう!