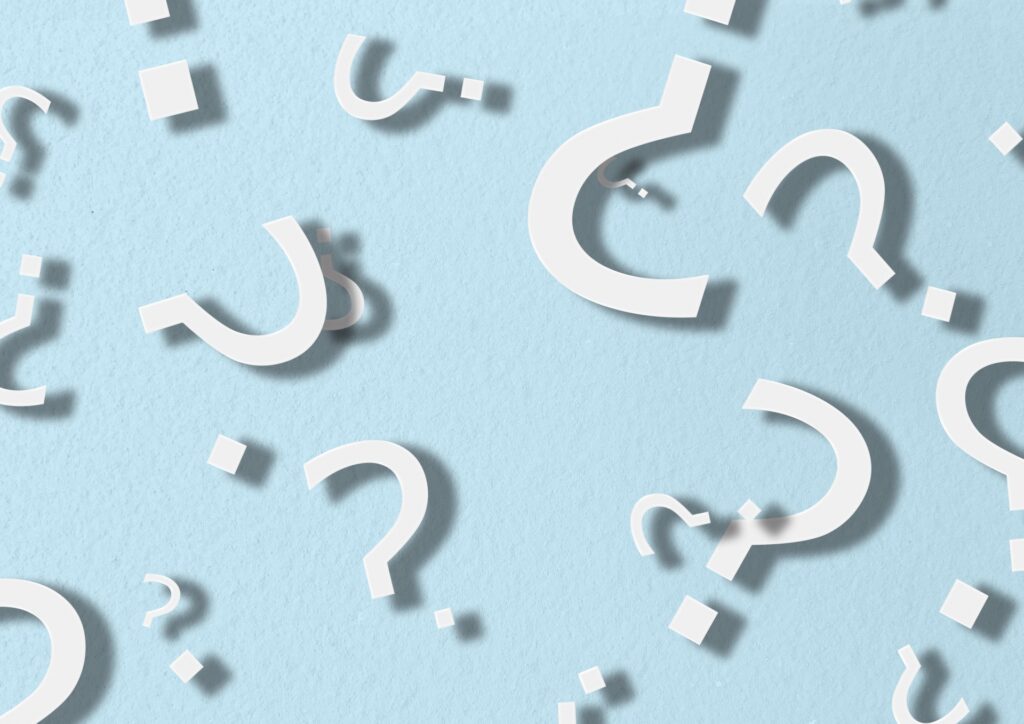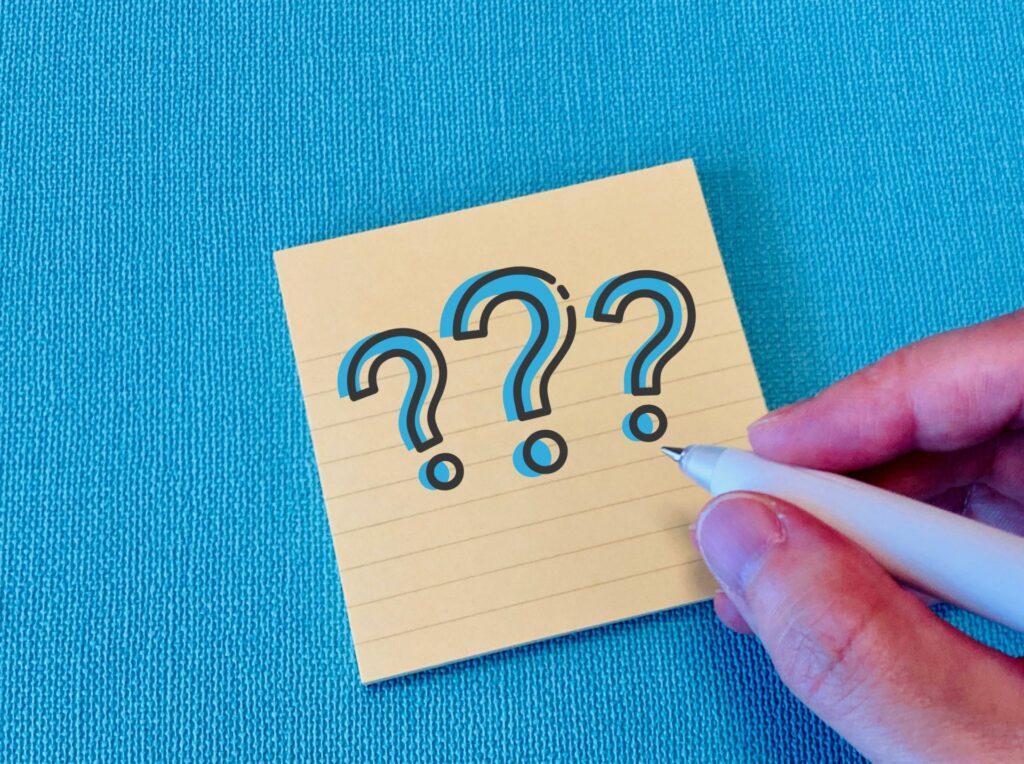こんにちは!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日は皆さんに「神宮」と「神社」の違いについてお話ししたいと思います。実は、ボクも最近まで「なんとなく格式が違うんだろうな〜」くらいにしか思っていなかったんですよね。でも調べてみると、これがスゴく奥深い!皆さんも初詣や観光で神社仏閣を訪れることがあると思いますが、その違いを知ると参拝の気持ちも変わってくるかもしれませんよ。
神社と神宮の基本的な違い
まず基本中の基本!神社と神宮の違いは「社号(しゃごう)」と呼ばれる格式の違いなんです。社号というのは神社の名前の最後につく「神社」「神宮」「大社」「宮」などの部分のこと。これらは明治時代以降に整理されたもので、それぞれに意味があるんですよ。
神社は日本古来の宗教である「神道」の祭祀を行う施設で、全国に約85,000社も存在しています。一方、神宮は皇室または皇室と縁が深い方を祀っている神社のことを指します。実は元々「神宮」という呼び方は伊勢神宮だけを指す名前だったんですよ!
伊勢神宮には天皇の祖先とされる天照大神(アマテラスオオカミ)が祀られています。現在、日本全国で神宮の社号を持つ神社は24社しかないんです。かなり限定的ですよね!
神宮の種類と代表的な神宮
神宮には大きく分けて3つのタイプがあります。
皇祖神を祀る神宮
皇祖神とは、天皇家の祖先神のことです。代表的なものとしては:
- 伊勢神宮(三重県):天照大神、豊受大神
- 伊弉諾神宮(兵庫県淡路市):伊弉諾尊・伊弉冉尊
- 霧島神宮(鹿児島県):瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)
伊勢神宮は特に格式が高く、内宮の「皇大神宮」と外宮の「豊受大神宮」は「大神宮」と呼ばれる最高格式の神宮なんですよ。
歴代天皇を祀る神宮
こちらは歴代の天皇を祀っている神宮です:
- 橿原神宮(奈良県):神武天皇
- 明治神宮(東京都):明治天皇、昭憲皇太后
- 平安神宮(京都府):桓武天皇、孝明天皇
明治神宮は毎年初詣で日本一の参拝客を集めることで有名ですよね!ボクも家族で行ったことがありますが、人の多さにビックリしました。
皇室と関係の深い神を祀る神宮
- 熱田神宮(愛知県):天叢雲剣(草薙の剣)をご神体としています
- 石上神宮(奈良県):日本最古の神宮と言われています
石上神宮は『古事記』にも登場する最古の神宮で、伊勢神宮よりも古いとされているんですよ!古事記に登場する神宮は伊勢大神宮と石上神宮のふたつだけなんだそうです。
神宮と神社の見分け方
「じゃあ実際に行ったとき、どうやって見分ければいいの?」と思いますよね。一番簡単なのは名前を確認することです!名前に「神宮」とついていれば神宮、「神社」とついていれば神社です。シンプル!
でも、鳥居の形式にも違いがあるんですよ。神宮の鳥居は一般的に「明神鳥居」と呼ばれる形式が多く、神社よりも格式高い雰囲気を感じることができます。平安神宮の大きな朱色の鳥居なんかは遠くからでも目立ちますよね!
他の社号についても知っておこう
神宮と神社以外にも、様々な社号があります。
宮(みや)
「宮」は皇室の皇子や皇孫(親王)を祭神とする神社や、歴史上の要人を祀る神社に使われます。例えば:
- 鎌倉宮:護良親王
- 天満宮:菅原道真公
- 東照宮:徳川家康公
大社(たいしゃ)
「大社」は古くから格式の高い神社に与えられた社号です。出雲大社が最も有名ですね!縁結びのパワースポットとして知られていますよね。
参拝する際の心構え
神宮と神社の違いを知ったところで、参拝する際の心構えも少し変わってくるかもしれません。特に神宮は皇室とゆかりの深い場所なので、より一層丁寧な参拝を心がけたいところです。
基本的な参拝方法は「二拝二拍手一拝」が一般的ですが、神社によって作法が異なる場合もあります。例えば出雲大社では「二拝四拍手一拝」が正式な作法です。参拝前に調べておくとより良いですね!
ボクの子どもたちも最初は「なんで神社によって拍手の回数が違うの?」と不思議がっていましたが、それぞれの神社の歴史や祀られている神様によって違うんだよと説明したら、「へぇ〜!」と目をキラキラさせていました。子どもに日本の文化を伝えるいい機会にもなりますね。
神宮と神社の違いを知ると、参拝するときの気持ちも少し変わってくるものです。ただなんとなく手を合わせるだけでなく、そこに祀られている神様や歴史を意識すると、より深い参拝体験ができるんじゃないでしょうか。
次回の初詣や観光で神社仏閣を訪れる際には、ぜひその社号にも注目してみてくださいね!きっと新しい発見があるはずです。
案ずるより産むが易し。心配するよりも、実際に行動してみれば意外と簡単にできるものだ。 – 諺
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!皆さんの参拝がより素敵なものになりますように!