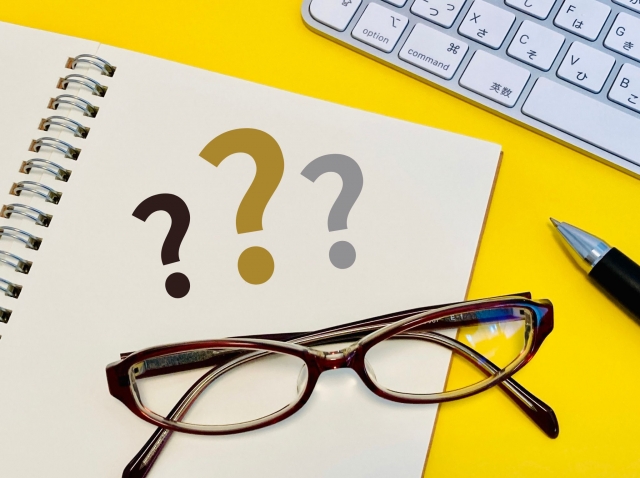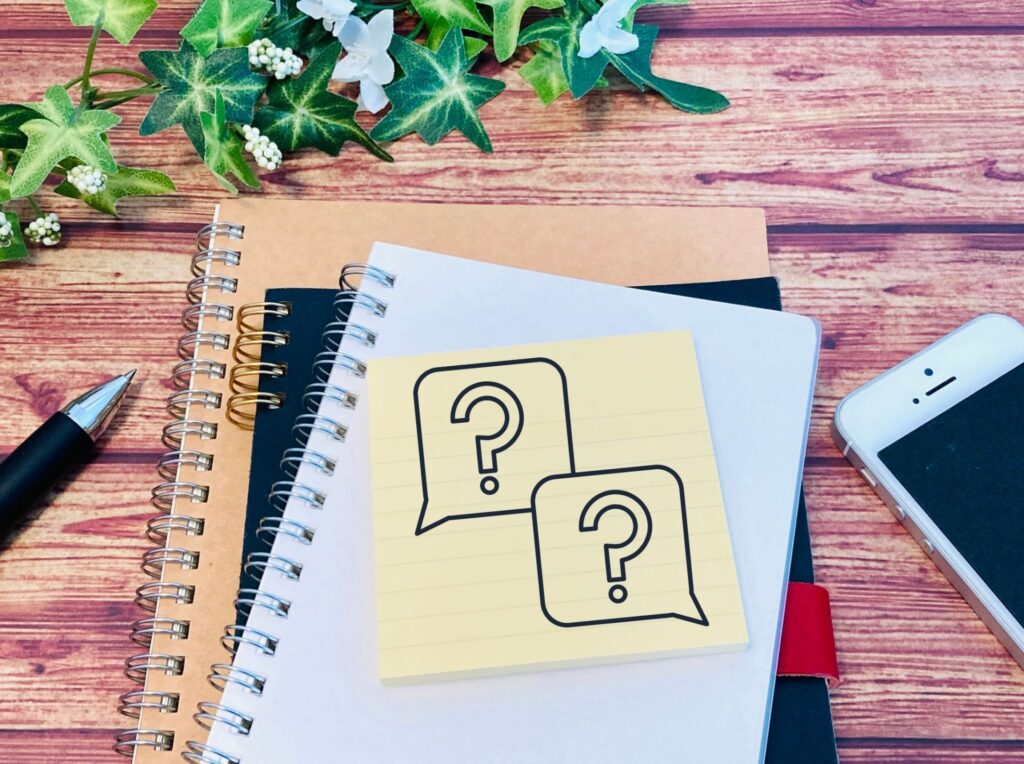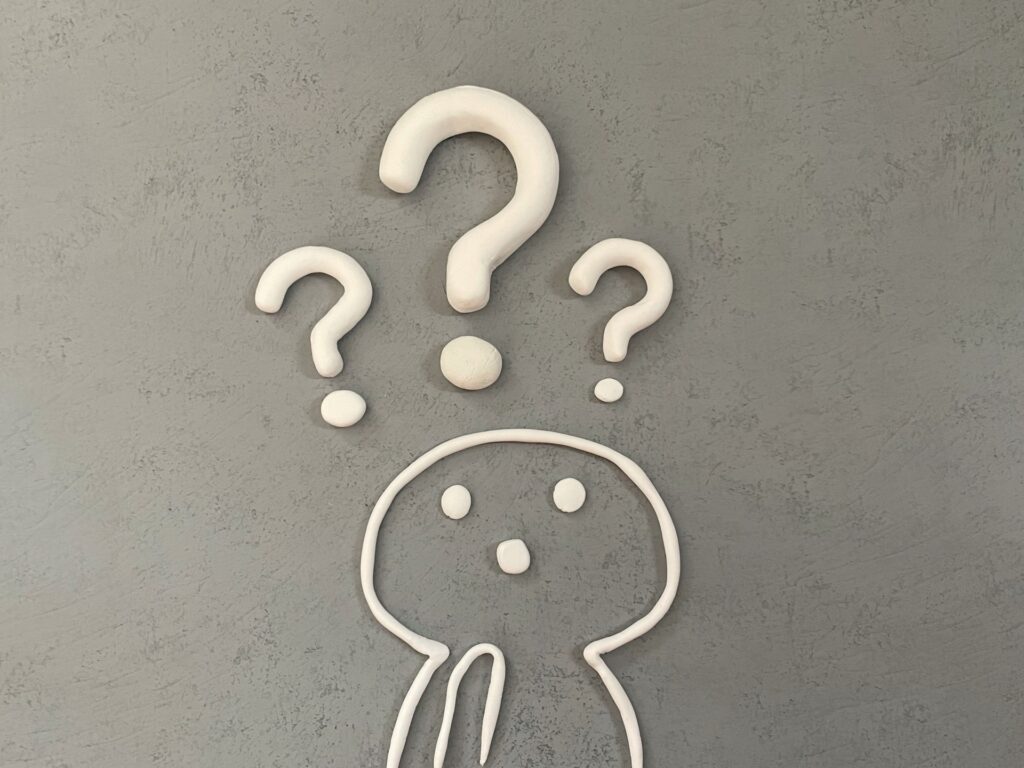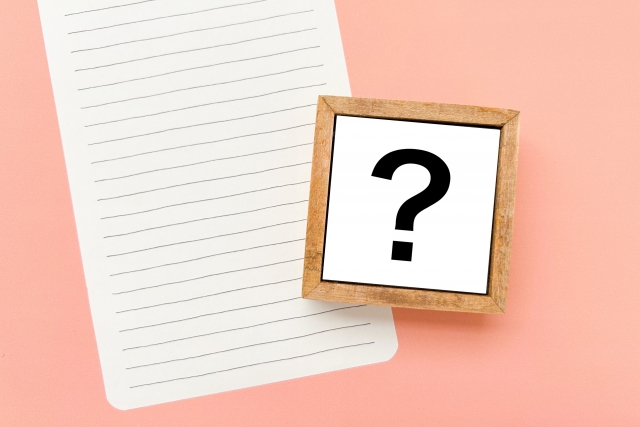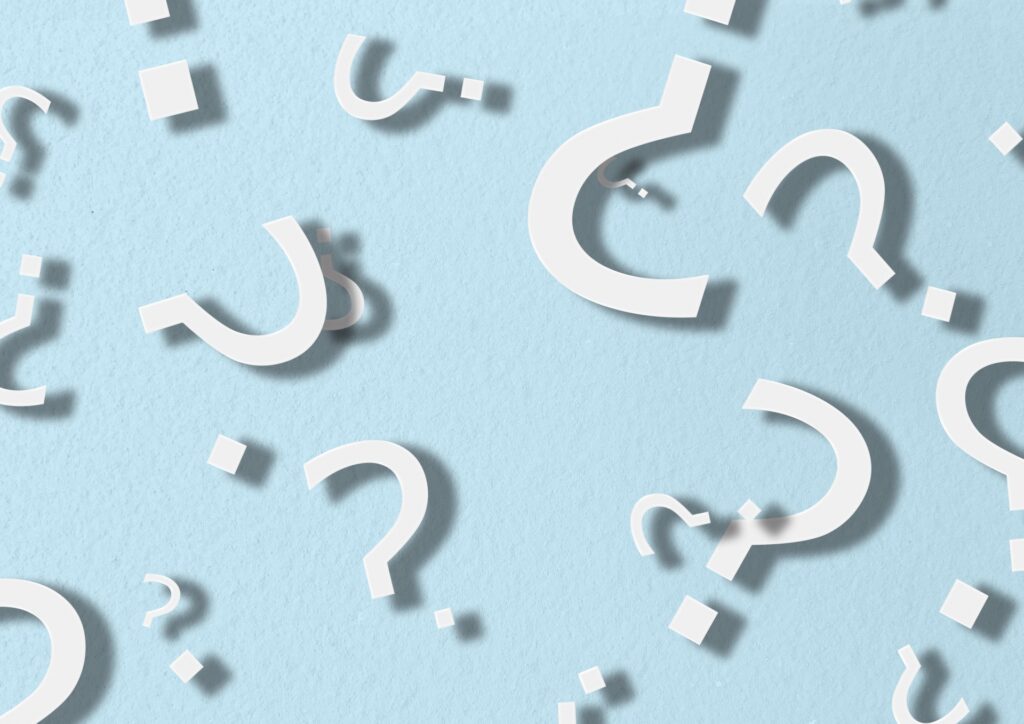こんにちは!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日は皆さんにとって意外と知らない「ODM」と「OEM」の違いについてお話ししたいと思います。ビジネスの世界ではよく耳にする言葉ですが、実はこの2つ、混同されがちなんですよね。ボクも最初は「なんだか似たようなもの?」と思っていましたが、実はしっかりとした違いがあるんです。皆さんのビジネスにも関わる可能性のある内容なので、ぜひ最後までお付き合いください!
ODMとOEMの基本的な違い
まず、それぞれの言葉の意味から確認していきましょう。
OEMとは「Original Equipment Manufacturing(Manufacturer)」の略で、委託者のブランド名で製品を製造することを指します。一方、ODMは「Original Design Manufacturing」の略で、委託者のブランドで製品を設計・製造することを意味します。
最大の違いは「誰が設計するか」という点にあります。OEMは委託側が設計・デザインを行い、製造のみを外部に依頼するのに対し、ODMは設計から製造までを一括して外部に依頼する方式なんです。
つまり、OEMは「作り方を教えるから作って」という関係性で、ODMは「こんな感じの商品が欲しいから考えて作って」という関係性と言えるでしょう。
業務範囲から見るODMとOEMの違い
ODMとOEMの業務範囲を具体的に比較してみましょう。
OEMの業務範囲
OEMの場合、委託者は以下の業務を担当します:
- 商品の企画・開発
- 商品の設計・デザイン
- 仕様の決定
一方、受託者(製造側)は:
- 委託者の指示に基づく製造
- 品質管理
- 納品
OEMでは委託者が主導権を握り、製造に関する指示を出します。時には委託者が技術指導を行うこともあり、いわゆる「垂直分業」の形態をとることが多いです。
ODMの業務範囲
ODMの場合、委託者の業務は:
- 商品コンセプトの提示
- ブランディング
- 販売・マーケティング
受託者(製造側)の業務は:
- 商品の企画・開発
- 設計・デザイン
- 製造・品質管理
- 納品
ODMでは受託者が商品開発の大部分を担当するため、委託者は販売やマーケティングに集中できるというメリットがあります。最近では、マーケティングまでサポートしてくれるODMメーカーも増えてきているんですよ!
メリットとデメリットから見るODMとOEM
それぞれの方式にはメリットとデメリットがあります。ビジネスの状況に応じて選ぶことが大切です。
OEMのメリット
- 初期費用を抑えてオリジナル商品を販売できる
- 工場管理や製造のための人件費が不要
- 自社のノウハウを活かした商品開発ができる
- 製造工程の一部を委託するため、社内に製造ノウハウが蓄積される
OEMのデメリット
- 社内のノウハウやデザインが流出するリスクがある
- 製造工程を細かくコントロールするのが難しい
- 設計から製造までの知識が必要
ODMのメリット
- ノウハウがなくてもすぐにブランドを展開できる
- 短期間で商品ラインナップを増やせる
- 専門的な知識や技術を持つメーカーのノウハウを活用できる
- 企画・開発から製造までをワンストップで依頼できる
ODMのデメリット
- 社内にノウハウが蓄積しにくい
- メーカー側に強く依存してしまう
- 委託する業務範囲が広いため、コストが高くなりがち
- メーカーが倒産や休業した場合のリスクが大きい
ODMとOEMはどちらを選ぶべき?
「どっちがいいの?」と思われる方も多いと思いますが、これは自社の状況によって変わってきます。
OEMが適している場合
- 自社に商品開発のノウハウがある
- 長期的に製造ノウハウを蓄積したい
- 独自性の高い商品を作りたい
- 事業規模が小さい場合
ODMが適している場合
- 短期間で商品ラインナップを増やしたい
- 自社に商品開発のノウハウがない
- 薄利多売のビジネスモデルを採用している
- 販売・マーケティングに集中したい
例えば、アパレル業界では商品ラインナップをとにかく増やす必要があるため、デザイナーが足りない場合もあります。そんな時はODMが適しているでしょう。一方、独自性の高い商品で勝負したい場合はOEMの方が向いています。
業界によるODMとOEMの違い
実は業界によってOEMやODMの内容も微妙に異なります。いくつか例を見てみましょう。
アパレル業界の場合
アパレル業界でのOEMは、デザインや企画を行うアパレルメーカーと生産工場を仲介する企業がほとんどです。生産設備を保有していないOEM企業も珍しくありません。
化粧品業界の場合
化粧品業界でのOEMは、生産設備を保有していなくても、オリジナル商品を生産できます。品質管理は厳しいですが、小ロットでの生産を受注してくれる企業も多くあります。
健康食品・サプリメント業界の場合
この業界では、OEMとODMの境界が曖昧なケースも多いです。原料選定だけは製造側が行うこともあり、どこまでが委託者の業務でどこからが受託者の業務かが明確でないことも。実際には「OEM」と紹介されていても、実質的には「ODM」のサービスを提供している企業も少なくないんですよ。
ODMとOEMの契約時の注意点
OEMやODMを利用する際は、契約内容をしっかり確認することが大切です。特に以下の点に注意しましょう:
- 委託者と受託者の権利義務を明確に規定する
- 知的財産権の帰属を明確にする
- 品質基準や納期について具体的に定める
- 秘密保持条項を設ける
- トラブル発生時の対応方法を決めておく
特に知的財産権については、後々のトラブルを避けるためにも、契約書で明確に定めておくことをオススメします。ボクの知人も契約内容があいまいだったために、後でモメてしまったケースがありました。ギュウギュウに詰まった契約書を読むのは大変ですが、この部分はスッキリさせておきたいですね!
まとめ:ODMとOEMの違いを理解して最適な選択を
ODMとOEMの違いをまとめると:
- OEMは製造のみを委託する方式
- ODMは設計から製造までを委託する方式
- 主導権がどちらにあるかが大きな違い
- 業界によって内容が異なる場合もある
- 自社の状況に応じて最適な方式を選ぶことが重要
ビジネスモデルや自社のノウハウ、予算などを考慮して、最適な方式を選びましょう。どちらが良い悪いではなく、自社の状況に合った選択をすることが成功への近道です!
「選択の自由があるということは、選択する責任があるということだ」 – エリノア・ルーズベルト
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!皆さんのビジネスが成功することを心より願っています。何か質問があれば、いつでもコメントしてくださいね!