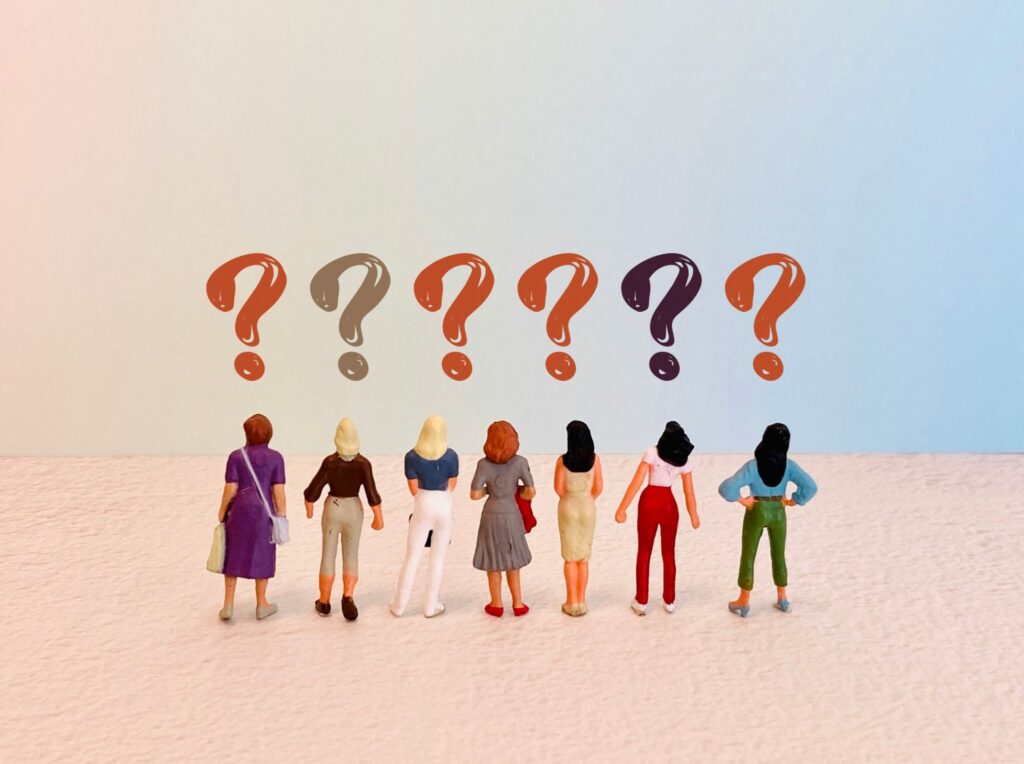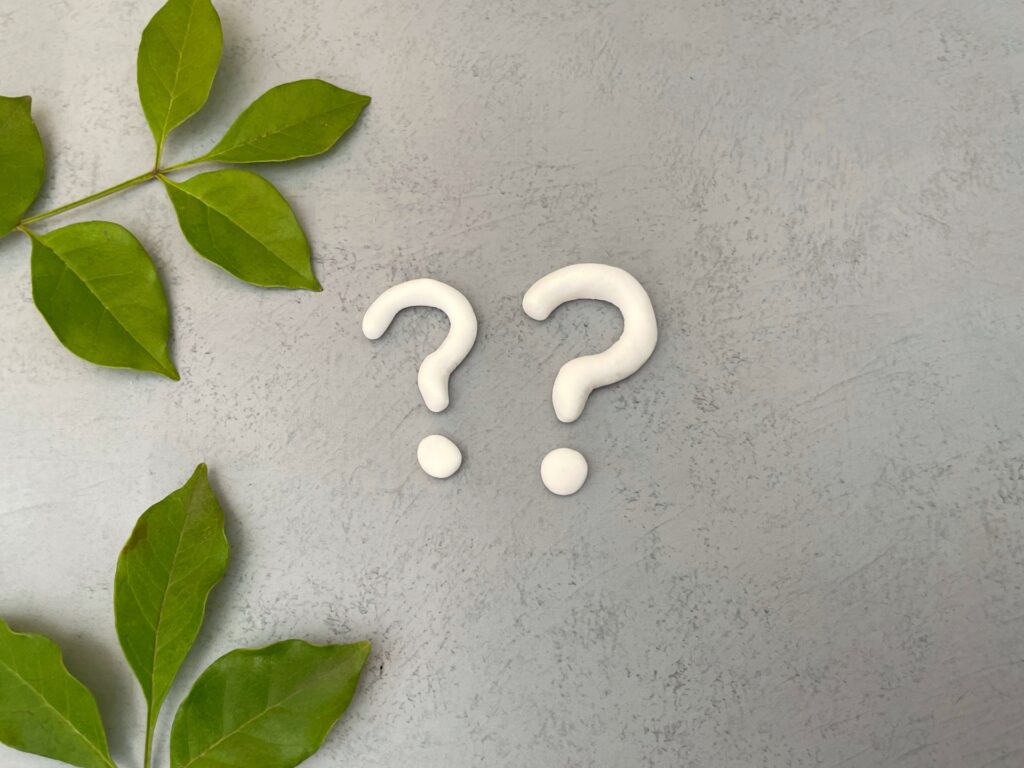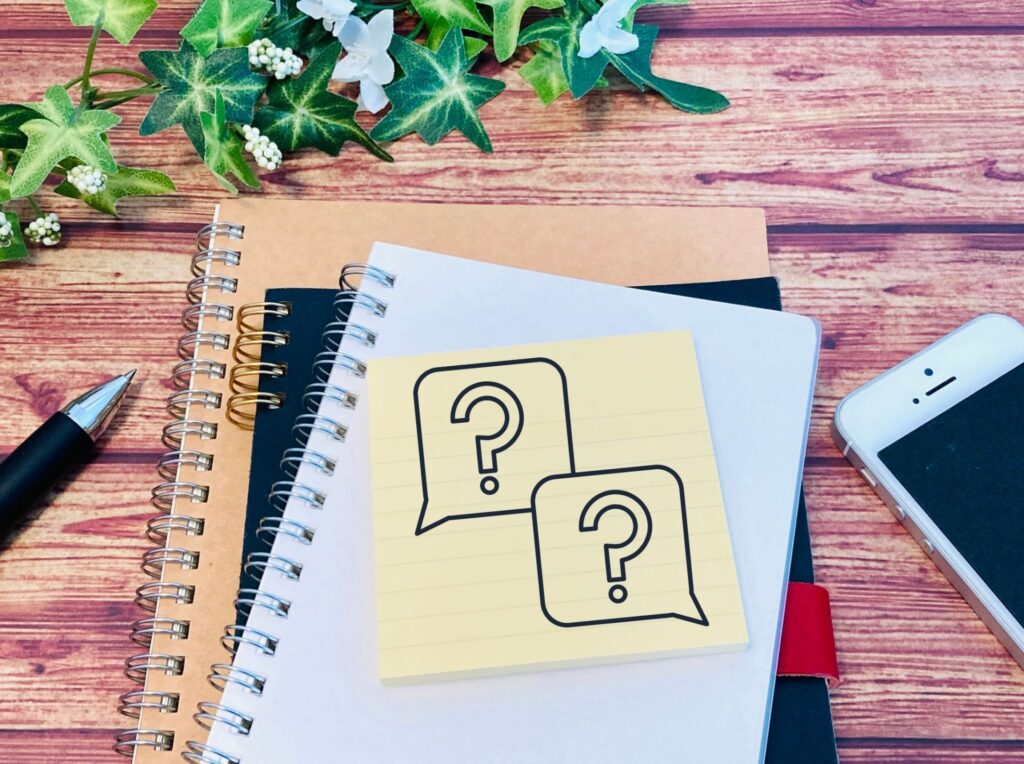こんにちは!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日は皆さんにとって意外と紛らわしい「改定」と「改訂」の違いについてお話ししたいと思います。ビジネスの現場でも頻繁に使われるこの二つの言葉、同じ「かいてい」と読むけれど、使い方が違うんですよね。ボクも以前は間違えて使っていたことがあります。お恥ずかしい!
さて、皆さんは「価格改定のお知らせ」と「マニュアル改訂版」、この違いがパッと説明できますか?今日はそんな細かいところをスッキリ解説していきますよ!
「改定」と「改訂」の基本的な意味の違い
まずは基本中の基本!この二つの言葉の意味をしっかり押さえておきましょう。
「改定」(かいてい)は、「法律や制度、価格など、今まで決まっていたものを新しく定め直すこと」を意味します。つまり、何かのルールや基準を変更する時に使う言葉なんですね。
一方、「改訂」(かいてい)は、「書物や文章の内容を訂正して書き改めること」を意味します。文書の内容を正しくするために手を加える場合に使います。
この違いは漢字の成り立ちを見るとわかりやすいんです。「改定」の「定」は「定める」、「改訂」の「訂」は「訂正する」という意味があります。ボクはこれを知った時、「なるほど!」と膝を打ちましたよ。
「改定」の具体的な使い方と例文
「改定」は主に制度や料金などの変更に使われます。具体的には以下のような場面で使いますよ。
- 料金や価格を変更する場合 例:「4月から電気料金の改定を実施します」
- 社内規則やルールを変える場合 例:「就業規則の改定について説明会を開催します」
- 制度を新しくする場合 例:「年金制度の改定により、支給開始年齢が引き上げられました」
ボクの息子が通う高校でも、「校則改定のお知らせ」というプリントが配られたことがありました。このように、何かの決まりごとを変える時には「改定」を使うんですね。
「改訂」の具体的な使い方と例文
「改訂」は文書や書籍の内容を修正する際に使います。例えば次のような場面です。
- 教科書や参考書の内容を更新する場合 例:「新学習指導要領に合わせて教科書が改訂されました」
- マニュアルの内容を修正する場合 例:「業務マニュアルの改訂版が完成しました」
- 書籍の内容を更新して再発行する場合 例:「この辞書は10年ぶりの改訂となります」
ボクの娘が使っている小学校の教科書も、時々「改訂版」として新しくなりますね。内容が古くなったり、誤りが見つかったりした場合に、文書を改訂するわけです。
「改正」との違いも押さえておこう
「改定」「改訂」に加えて、似た言葉に「改正」(かいせい)があります。これは主に法律や条例などを正しく改めることを指します。
「改正」は特に法令関係で使われることが多く、「憲法改正」「道路交通法改正」などの使い方をします。「正しくする」というニュアンスが強いのが特徴です。
ちなみに「改定」「改訂」が同じ「かいてい」と読むのに対して、「改正」は「かいせい」と読みます。ここも間違えやすいポイントですよね!
実践!正しい使い分けのポイント
では、実際にどう使い分ければいいのか、簡単なチェックポイントをご紹介します。
- 文書や書籍の内容を直す → 「改訂」
- 料金やルールを変更する → 「改定」
- 法律や条例を変える → 「改正」
例えば、「価格改訂のお知らせ」は間違いで、正しくは「価格改定のお知らせ」です。逆に「マニュアル改定」ではなく「マニュアル改訂」が正しいんですよ。
ボクの子どもたちにも、「言葉の使い方は大事だよ」とよく言っています。特にビジネスの場では、こういった細かい言葉の使い分けができると、「おっ、できる人だな」と思われるかもしれませんね。
まとめ:日常でも役立つ知識を身につけよう
いかがでしたか?「改定」と「改訂」の違い、少しはスッキリしましたか?
- 「改定」:制度や料金などを新しく定め直すこと
- 「改訂」:文書や書籍の内容を訂正して書き改めること
- 「改正」:法律や条例などを正しく改めること
ビジネス文書を作成する際はもちろん、日常会話でも正しく使い分けられると、コミュニケーションがよりスムーズになりますよ。
ボクも46歳になりましたが、まだまだ学ぶことはたくさんあります。皆さんも「知らなかった」で終わらせず、新しい知識をどんどん吸収していきましょうね!
本日の名言をご紹介して締めくくります。
「学ぶことをやめたら、教えることをやめなければならない」 – ハワード・ヘンドリックス
それでは、また次回のミーミルメディアでお会いしましょう!