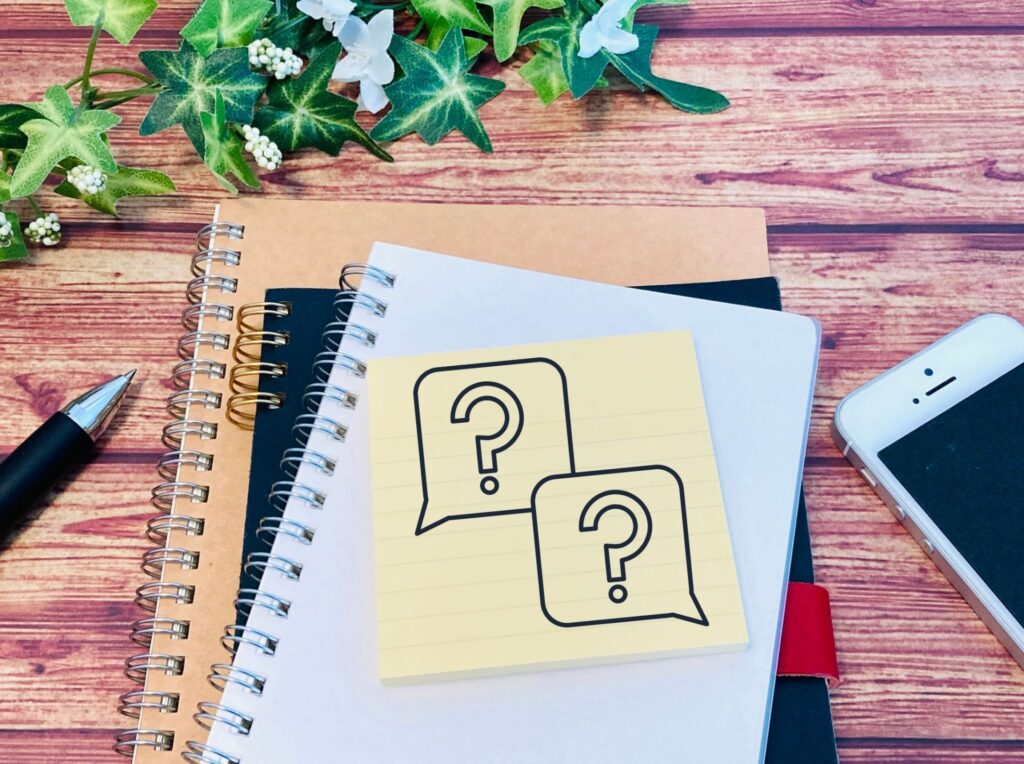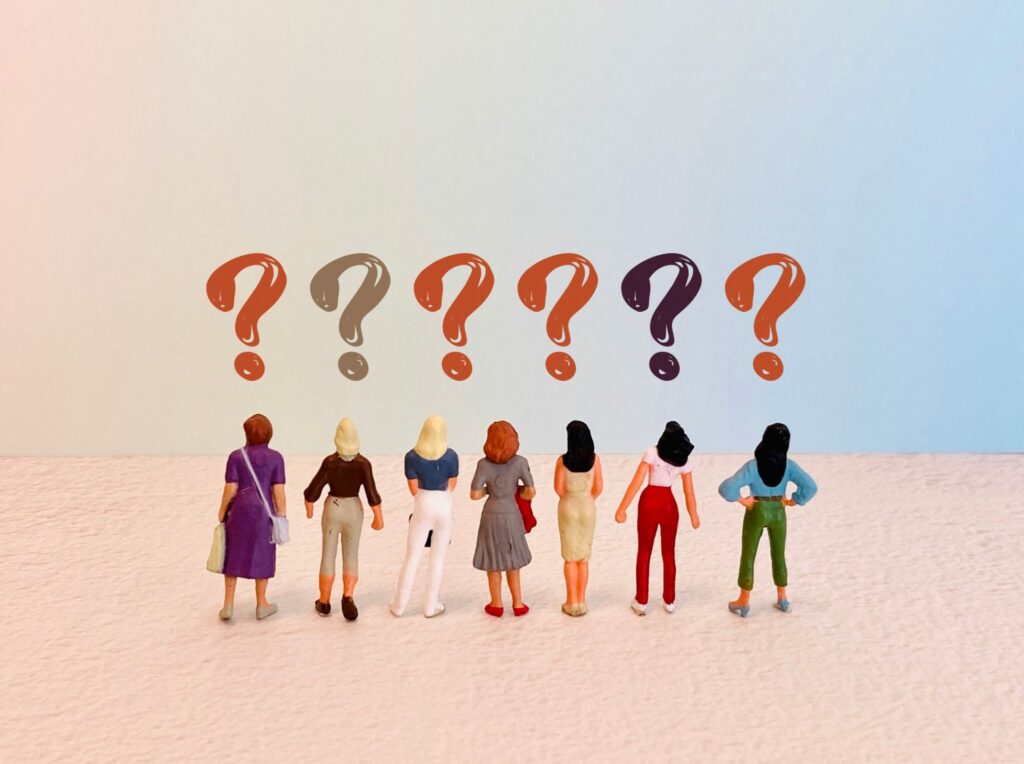こんにちは!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日は皆さんに発達障害の中でもよく耳にする「ASD」と「ADHD」の違いについてお話ししたいと思います。お子さんの行動が気になる方や、自分自身の特性について知りたい方も多いのではないでしょうか?ボクも子育ての中で「うちの子、ちょっと落ち着きがないかも?」と思ったことがあります。でも、心配しすぎる前に、まずは正しい知識を身につけることが大切ですよね!それでは早速、ASDとADHDの違いについて見ていきましょう!
ASDとADHDの基本的な違い
まず最初に、ASDとADHDはどちらも「発達障害」という大きなカテゴリーに含まれる障害です。でも、その特徴や症状はかなり異なります。
ASD(自閉スペクトラム症)は、主にコミュニケーションの難しさや特定のことへの強いこだわりが特徴です。一方、ADHD(注意欠陥・多動性障害)は、注意力が続かなかったり、じっとしていられなかったり、衝動的に行動してしまったりする特徴があります。
ASDとADHDの最も大きな違いは、ASDは「社会性の障害」が中心なのに対し、ADHDは「注意力や行動のコントロール」に関する障害という点です。
注意力と集中力の違い
ADHDの方は一般的に注意力が散漫で、集中力が続かないことが多いです。例えば、授業中にすぐ気が散ってしまったり、仕事中に何度も中断してしまったりします。忘れ物が多かったり、ミスを繰り返したりすることもよくあります。
一方、ASDの方は特定のことに対して非常に強い集中力を発揮することがあります。自分の興味のある分野には驚くほど詳しくなることも!ただし、興味のない分野には全く関心を示さないこともあります。
社会性とコミュニケーションの違い
ASDの方は社会的なコミュニケーションが苦手なことが多いです。相手の気持ちや表情から感情を読み取ることが難しかったり、会話のキャッチボールがうまくできなかったりします。
ADHDの方は社会的な知識自体はあるものの、衝動的な発言や行動によってトラブルになることがあります。例えば、順番を待てずに割り込んでしまったり、相手の話を最後まで聞けなかったりすることがあります。
「うちの子はADHDかなと思っていたけど、友達との関係づくりが苦手なのはASDの特徴なのかも。両方の特性があるのかな?」(女性/40代前半/専業主婦)
ADHDとASDの症状例
それでは、具体的な症状例を見ていきましょう!
ADHDの主な症状例
ADHDの症状は大きく分けて「不注意」「多動性」「衝動性」の3つのタイプに分けられます。
不注意の例としては、細かいミスが多い、物をよく失くす、指示を最後まで聞けない、課題や活動を最後までやり遂げられないなどがあります。
多動性の例としては、じっと座っていられない、常に何かをいじっている、静かに遊べない、過度にしゃべるなどがあります。
衝動性の例としては、質問が終わる前に答えてしまう、順番を待てない、他人の会話や活動に割り込むなどがあります。
ASDの主な症状例
ASDの症状は「社会的コミュニケーションの障害」と「限定された興味と反復的な行動」の2つに大きく分けられます。
社会的コミュニケーションの障害の例としては、アイコンタクトが少ない、表情が乏しい、会話が一方的になりがち、友達関係を築くのが難しいなどがあります。
限定された興味と反復的な行動の例としては、特定のものに強いこだわりがある、同じ行動を繰り返す、ルーティンの変更に強い抵抗を示す、感覚過敏(音や光、触感などに敏感)があるなどです。
ADHDとASDの診断時期の違い
診断時期にも違いがあります。ASDは通常、3歳までに症状が現れることが多く、早期に診断されることがあります。特に、言葉の遅れや社会的な相互作用の問題が早くから気づかれやすいです。
一方、ADHDは学校に入ってから症状が目立つようになることが多いです。集団生活の中で、じっとしていられない、授業に集中できないなどの特徴が顕著になるからです。そのため、小学校入学後に診断されることが多いです。
併存することも多い
実は、ADHDとASDは併存することも少なくありません。両方の特性を持っている方も多いのです。例えば、ADHDと診断された後、薬物療法などで症状が改善した後に、ASDの特性が見えてくることもあります。
「最初はADHDと診断されて薬を飲み始めたら落ち着いてきたけど、それでも人間関係でつまずくことが多くて。後からASDの診断も受けて、やっと自分の特性が理解できました。」(男性/30代前半/会社員)
ADHDとASDの対応方法の違い
それぞれの障害に対する対応方法も異なります。
ADHDの場合は、環境調整(集中しやすい環境づくり)や、時間管理のサポート、タスクの細分化などが効果的です。また、薬物療法も選択肢の一つとなります。
ASDの場合は、社会的スキルトレーニングやコミュニケーション支援、感覚過敏への配慮などが重要です。予測可能な環境や明確なルーティンを作ることも助けになります。
強みを活かすアプローチ
どちらの障害も、「障害」という側面だけでなく、「特性」として捉えることが大切です。ADHDの方は創造性や発想力が豊かだったり、ASDの方は細部への注意力や記憶力に優れていたりすることがあります。
これらの強みを活かせる環境や仕事を見つけることで、充実した生活を送ることができるでしょう。ボクの知り合いにも、ADHDの特性を活かしてクリエイティブな仕事で活躍している人がいますよ!
まとめ:理解と適切なサポートが大切
ASDとADHDは、どちらも脳の発達に関わる障害ですが、その特徴や症状は大きく異なります。ADHDは注意力や行動のコントロールに関する障害、ASDは社会性やコミュニケーション、こだわりに関する障害と言えるでしょう。
大切なのは、これらの違いを理解した上で、それぞれの特性に合った適切なサポートを提供することです。早期発見・早期支援が重要ですが、「個性」として尊重する視点も忘れないようにしましょう。
皆さんの周りにもADHDやASDの特性を持つ方がいるかもしれません。この記事が少しでも理解の助けになれば嬉しいです!
「人生に完璧な準備などない。今日という日に全力を尽くすだけだ」- ウィル・スミス
今日も皆さんにとって素晴らしい一日になりますように!案ずるより産むが易し、まずは一歩踏み出してみましょう!
しげっちでした!また次回の記事でお会いしましょう!