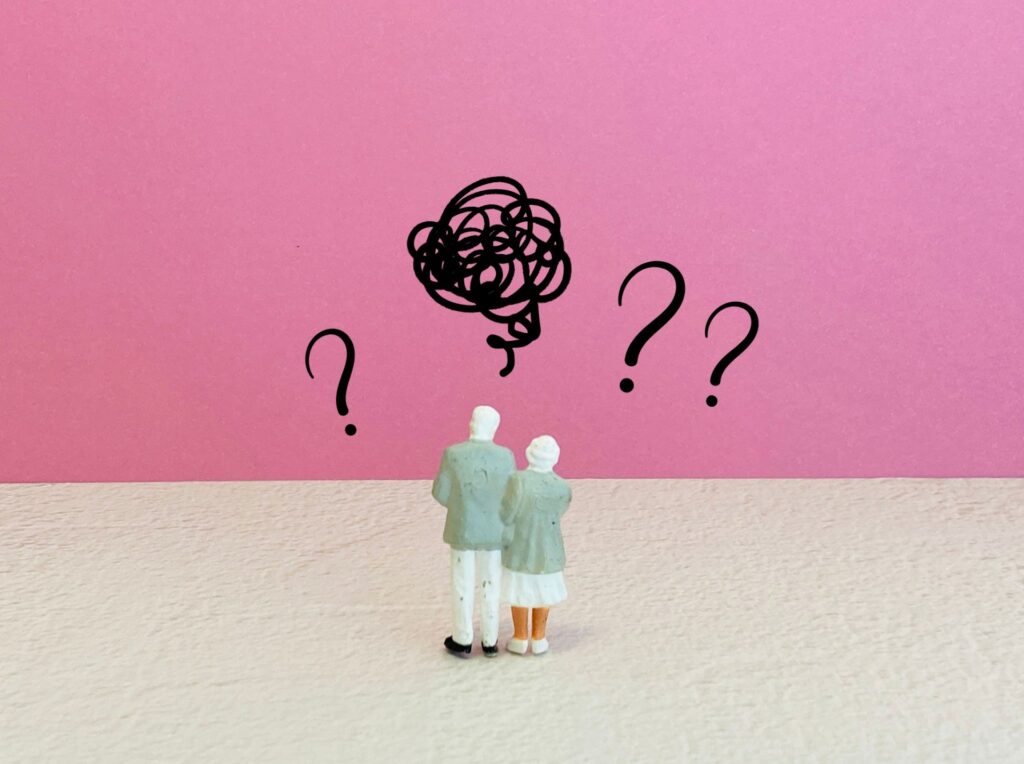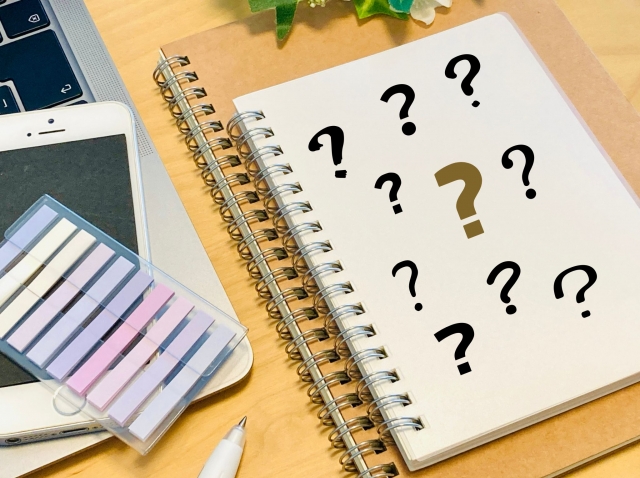こんにちは!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日は暑い夏を彩る東北の風物詩、「ねぷた」と「ねぶた」の違いについてお話ししたいと思います。「あれ?どっちがどっちだっけ?」と混乱した経験はありませんか?実は皆さん、この二つ、名前が似ているだけでなく、起源も同じなんですよ。でも、それぞれに個性があって、知れば知るほど面白い!さあ、一緒に青森の夏祭りの世界を覗いてみましょう。
「ねぷた」と「ねぶた」の基本的な違い
まず結論から言うと、「ねぷた」と「ねぶた」の違いは地域による呼び名の違いなんです。形や特徴で区別されるわけではないんですよ。
一般的に、弘前市を中心とした地域では「ねぷた(neputa)」、青森市を中心とした地域や下北地区では「ねぶた(nebuta)」と呼ばれています。「ねぷた」と「ねぶた」の語源は同じで、「眠い」「眠たい」が訛った「ねぶて」や「ねぷて」からきているとされています。つまり、地域の方言や訛りによって呼び名が分かれたというわけです。
よく「ねぷたは扇型で、ねぶたは人形型(立体的)」という説明を聞くことがありますが、これは誤りです。これは「弘前ねぷた」と「青森ねぶた」の特徴を混同したものなんですね。実際には、弘前ねぷたまつりや黒石ねぷた祭りにも人形型のねぷたがありますし、つがる市ネブタにも扇形と人形型の両方が存在しています。
青森県内のねぷた・ねぶた祭りの広がり
青森県内だけでも40を超える地域でねぷた・ねぶた祭りが行われているんですよ!驚きですよね。代表的なものとしては、青森市の「青森ねぶた祭」、弘前市の「弘前ねぷたまつり」、五所川原市の「五所川原立佞武多(たちねぷた)」などがあります。
それぞれの祭りには独自の特色があり、囃子や掛け声、ねぷた・ねぶたの形状なども異なります。例えば、青森ねぶた祭の掛け声は「ラッセラー」、弘前ねぷたまつりの掛け声は「ヤーヤドー」、五所川原立佞武多の掛け声は「ヤッテマレ」と、地域によって違うんです。
青森ねぶた祭の特徴
青森市で行われる「青森ねぶた祭」は、東北地方でもトップクラスの来場者数を誇る大規模なお祭りです。多い年には期間中に270万人近くが訪れるんですよ!
青森ねぶた祭の特徴は以下の通りです:
- 人形型のねぶたが中心で、立体的な造形が特徴
- 高さは4~5m、横幅は約9mの大型ねぶた
- 掛け声は「ラッセラー」
- 「ハネト(跳人)」と呼ばれる踊り手が特徴的
- 最終日には「ねぶたの海上運航」が行われる
- 開催期間は8月2日~7日
青森ねぶたは豪快で華やかな雰囲気があり、ハネトたちの踊りがお祭りの熱気を高めています。ハネトの衣装を購入またはレンタルして身につければ、観光客でも祭りに参加できるんですよ!これはワクワクしますね。
弘前ねぷたまつりの特徴
弘前市で行われる「弘前ねぷたまつり」も、毎年150万人以上が訪れる人気のお祭りです。
弘前ねぷたまつりの特徴は以下の通りです:
- 扇型のねぷたが中心
- 高さは大型のもので6~10m弱
- 掛け声は「ヤーヤドー」
- 重厚感のある太鼓の響きが特徴的
- 開催期間は8月1日~7日
弘前ねぷたは、下はキュッと細く、上は大きくアーチを描くような扇型が特徴的です。ねぷた絵には、臨場感あふれる戦の絵や幽霊・妖怪の絵など、おどろおどろしいものが多い傾向があります。青森ねぶたと比べるとややしっとりとした雰囲気があるのも特徴ですね。
五所川原立佞武多の特徴
五所川原市で行われる「五所川原立佞武多(たちねぷた)」は、その巨大さで有名です。
五所川原立佞武多の特徴は以下の通りです:
- 縦長で人形型の佞武多が特徴
- 高さは最大で20m以上(7階建てビル相当)
- 掛け声は「ヤッテマレ」
- 開催期間は8月4日~8日
「立」という漢字が入っている通り、立ち上がった姿のねぷたが運行するのが特徴です。その巨大さは圧巻で、見上げるとその迫力に圧倒されること間違いなしです!
ねぷた・ねぶたの呼称が統一された経緯
実は昔、呼び名はそれほど厳密に区別されていなかったんです。1954年(昭和29年)の弘前市のポスターには「弘前ねぶた」、1957年(昭和32年)の青森市のポスターには「青森ねぷた」と書かれていたという記録もあります。
それが、弘前市は1957年(昭和32年)から「ねぷた」に、青森市は1958年(昭和33年)から「ねぶた」に統一されました。そして、決定的になったのは1980年(昭和55年)に国の重要無形民俗文化財に指定されたときです。正式に登録されることになったので、青森市は「ねぶた」、弘前市は「ねぷた」として登録されたのです。
ねぷた・ねぶたの呼称が分かれた理由
なぜ二つの呼び名が生まれたのかについては諸説あります。津軽弁では「眠い」ということを「ねぷて」や「ねぷたい」と言います。このことから話し言葉として「ねぷた」という発音が行われてきたと考えられています。
また、当時は「゜(半濁点)」の表記がなかったため、「ぷ」ではなく「ふ」や「ぶ」などで代用したという説もあります。元は「ねぷた」だったのが、記録として残していく過程で「ねぶた」という読み方が生まれたとも考えられています。
青森県内の様々なねぷた・ねぶた祭り
青森県内には、主要な3つの祭り以外にも多くのねぷた・ねぶた祭りがあります。例えば、平川市の「平川ねぷたまつり」は毎年8月2日~3日に開催され、水墨画のような白黒の色合いを基調としたねぷたが特徴です。
黒石市の「黒石ねぷたまつり」は毎年7月30日~8月5日に開催され、人形ねぷたと扇ねぷたを同時に見ることができるのが特徴です。掛け声は「ヤーレヤーレヤーレヤ」が基本となっています。
このように、青森県内の各地域で行われるねぷた・ねぶた祭りは、それぞれに独自の特色を持っています。開催期間が重なっていることも多いので、時間に余裕があれば複数の祭りを巡ってみるのも楽しいですよ!
まとめ:ねぷた・ねぶた祭りを楽しむポイント
「ねぷた」と「ねぶた」の違いは地域による呼び名の違いであり、形状による区別ではないことがわかりました。青森県内の各地域で行われるねぷた・ねぶた祭りは、それぞれに独自の特色があり、囃子や掛け声、ねぷた・ねぶたの形状なども異なります。
ねぷた・ねぶた祭りの共通点は、会場の熱気が圧倒的で、夏の夜空を明るく照らすねぷた・ねぶたが幻想的なことです。一カ所だけピンポイントで見るのはもちろん、開催期間が重なっていることを活かして複数の祭りを巡るのもおすすめです。
青森の夏祭りは、その地域ならではの文化や歴史を感じられる貴重な機会です。ぜひ一度、青森の熱気あふれるねぷた・ねぶた祭りを体験してみてください!きっと忘れられない思い出になりますよ。
「伝統とは、革新の連続である」- 小泉八雲
今日も最後まで読んでくださり、ありがとうございました!皆さんの毎日が、ねぷた・ねぶた祭りのように明るく輝くものでありますように。次回もお楽しみに!