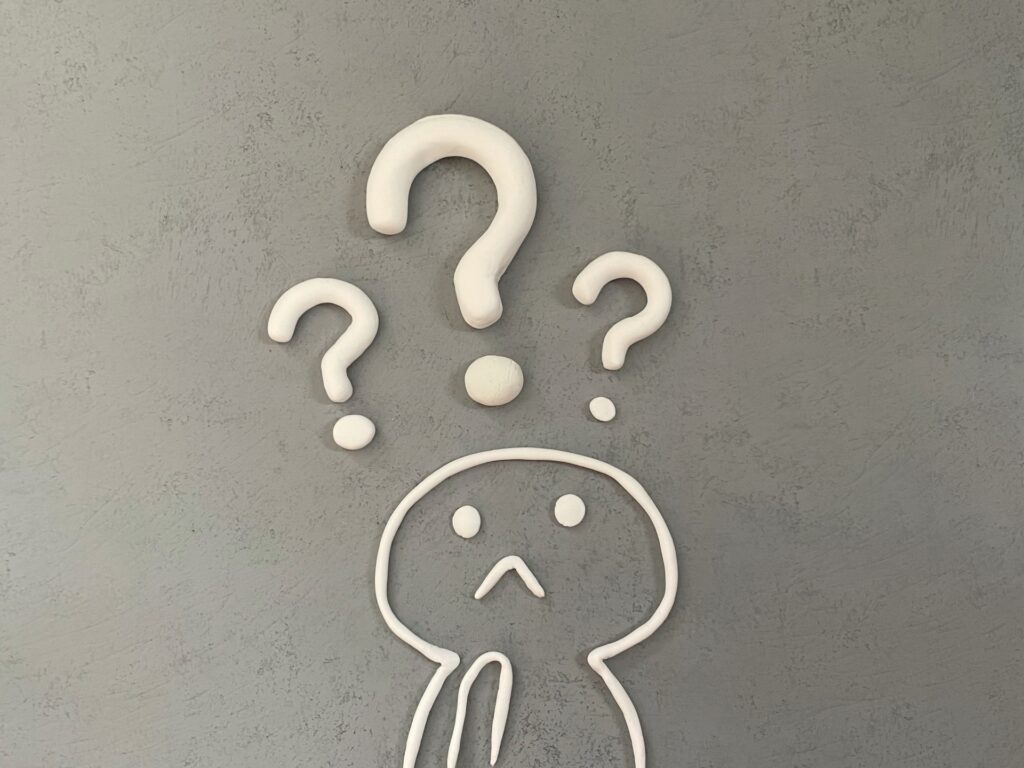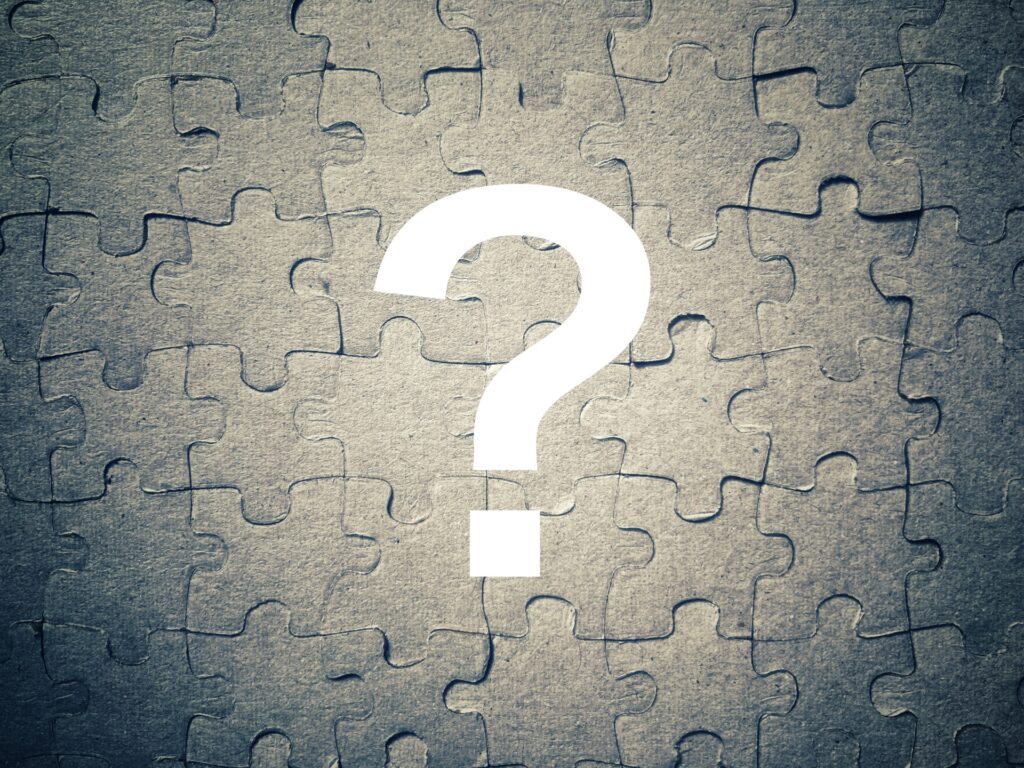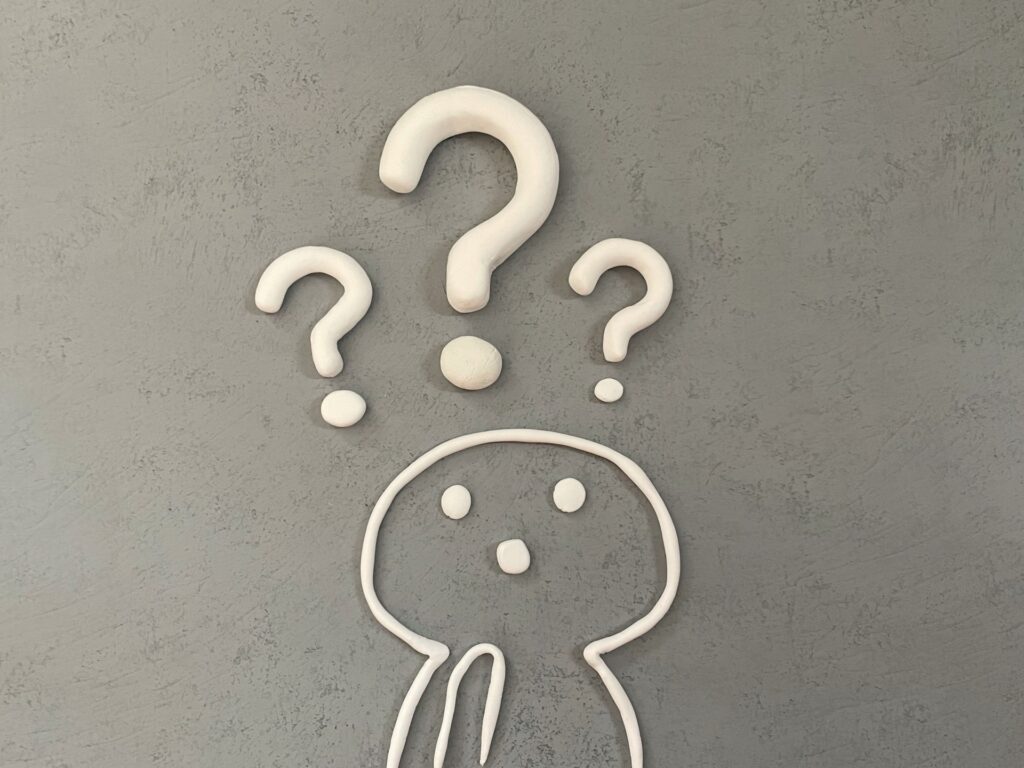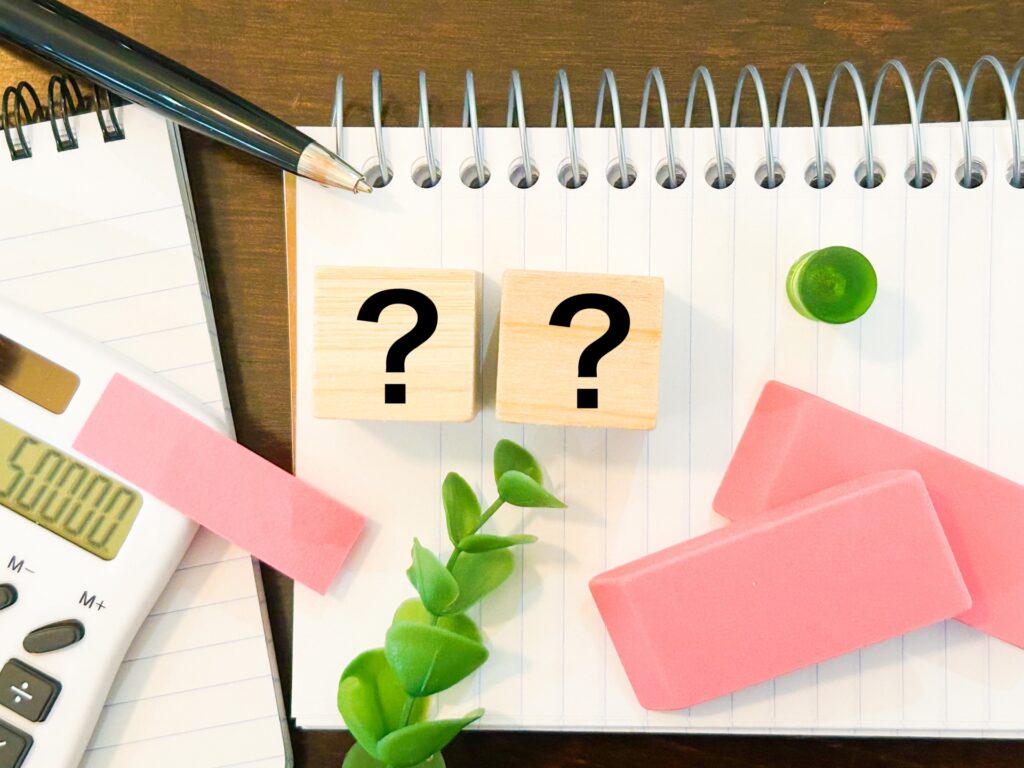こんにちは!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日は寒い季節になるとよく話題になる「トナカイ」と、日本でもおなじみの「鹿」について、その違いを詳しく解説していきますね。
「トナカイってサンタさんのソリを引いているあの動物でしょ?」「鹿と何が違うの?」なんて疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。実は両者、見た目は似ていますが、いろいろな違いがあるんですよ。ボクも調べてみて「へぇ~!」と驚くことがたくさんありました。
それでは早速、トナカイと鹿の違いについて見ていきましょう!
トナカイと鹿の基本的な関係
まず最初に押さえておきたいのが、トナカイと鹿の関係です。結論から言うと、トナカイは鹿の一種なんです!
両方とも偶蹄(ぐうてい)目シカ科に属する動物で、トナカイはその中の一種類というわけです。ただし、日本で単に「鹿」と言うと、多くの場合はニホンジカを指しています。
ちなみに、トナカイは英語では「reindeer」と呼ばれ、北アメリカに生息しているものは特に「caribou(カリブー)」と呼ばれることもあります。
角の特徴の違い
トナカイと鹿(ニホンジカ)の最も大きな違いのひとつが「角」です。
鹿(ニホンジカ)の角
鹿の場合、オスにしか角が生えません。この角は毎年生え変わり、春に生え始めて秋の繁殖期に立派な角になります。最初は軟らかい皮膚に覆われた「袋角」という状態で、徐々に成長して硬い角になっていくんですよ。
鹿の角は1本の角から枝分かれしていく棒状の形をしています。これが鹿の特徴的な見た目を作り出しているんですね。
トナカイの角
一方、トナカイはシカ科の中で唯一、オスもメスも角が生える動物なんです!これはかなり特殊な特徴と言えますね。
さらに面白いのが、角が生えている時期が雌雄で異なること。オスの角は春に生え始め、繁殖期が終わる秋から冬にかけて抜け落ちます。これはオスにとって角がメスを争奪するための武器だからなんですね。
対してメスの角は冬に生え、夏に抜け落ちます。これには理由があって、冬の間、雪に埋もれたエサ(トナカイゴケという地衣類)を掘り起こすために角が必要なんです。トナカイゴケはタンパク質が豊富で栄養価が高く、厳しい冬を乗り切るための大切な食料源なんですよ。
また、トナカイの角には「額角」と呼ばれる、雪を掘りやすいようにシャベルのような形をした部分があります。自然の厳しい環境に適応した結果なんですね。
体の大きさと特徴の違い
トナカイと鹿は体の大きさや特徴にも違いがあります。
鹿(ニホンジカ)の体
ニホンジカの体長は約90cm~190cmで、トナカイに比べると小さめです。
体毛の色は季節によって変化し、冬は灰褐色、夏は褐色に白い斑点がある体毛に生え変わります。この夏の白い斑点があるかないかが、トナカイと見分ける際のポイントになりますよ。
トナカイの体
トナカイの体長は約120cm~220cmほどで、ニホンジカより大柄です。オスはメスの2倍ほどの大きさになることもあります。
体毛も季節によって変わりますが、冬は灰褐色、夏は褐色で、ニホンジカのような白い斑点はありません。また、寒冷地に適応するため、保温性の高い厚い体毛に覆われています。
さらに、トナカイの蹄(ひづめ)は平べったい形をしていて、これが積雪の上を移動するのに役立っているんです。自然環境への適応力がすごいですね!
生息地と生活習慣の違い
トナカイと鹿は生息している場所も全く異なります。
鹿(ニホンジカ)の生息地
ニホンジカは名前の通り日本全国の森林に生息しています。北海道から沖縄の慶良間列島まで広く分布していて、奈良公園の鹿が特に有名ですよね。
トナカイの生息地
トナカイは北極圏周辺の寒帯、亜寒帯地域に生息しています。具体的には北極地方、グリーンランド、アラスカ、カナダ、フィンランド、デンマークなどのヨーロッパ北部からアジア東部にかけての地域です。
生活習慣も興味深くて、トナカイは季節によって大群で移動したり、小さなグループに分かれて生活したりします。特に夏には蚊やアブを避けるために高地へ、冬には積雪の少ない低地へと長距離を移動します。その移動能力は高く、1000km以上を移動することもあるんですよ!
また、繁殖期以外はオスとメスは別々に生活していて、小グループは基本的に同じ性別の個体で構成されています。
人間との関わり
鹿(ニホンジカ)と人間
ニホンジカは古事記にも登場するほど、古くから日本人と関わりのある動物です。奈良時代には神の使いとして大切にされてきました。
肉は柔らかくて食用にされることもあり、皮は滑らかで手袋や靴、ソファーなどに加工されます。オスの角は古くから民間療法の薬としても利用されてきました。
トナカイと人間
トナカイは北欧を含むユーラシア大陸北部では古くから家畜化されていて、乳をしぼったり、肉を食べたり、毛皮を採取したりするために利用されてきました。
そして何といっても、クリスマスシーズンになるとサンタクロースのソリを引く動物として世界中で親しまれていますよね!
ところで、サンタのソリを引くトナカイについて面白い話があります。冬にはオスの角は抜け落ちるので、冬に角があるのはメスだけのはず。でも、サンタのソリを引くトナカイには角があるオスも含まれています。これはなぜかというと、去勢されたオスは冬でも角を持っているからなんです!サンタのトナカイは去勢されているという説もあるんですよ。
まとめ:トナカイと鹿の違い
ここまでトナカイと鹿の違いについて見てきましたが、改めて整理してみましょう。
- 基本的な関係:トナカイは鹿の一種
- 角の特徴:鹿はオスだけに角があるが、トナカイはオスもメスも角がある
- 体の大きさ:トナカイの方が鹿より大柄
- 体毛の特徴:夏の体毛は鹿には白い斑点があるが、トナカイにはない
- 生息地:鹿は日本の森林、トナカイは北極圏周辺の寒帯・亜寒帯地域
- 生活習慣:トナカイは季節によって大群で長距離移動する
いかがでしたか?トナカイと鹿、似ているようで実はいろいろな違いがあることがわかりましたね。特に角の生え方の違いは、自然環境への適応の結果として非常に興味深いですね。
皆さんもクリスマスシーズンにトナカイの話題が出たときは、「実はトナカイと鹿はこんなに違うんだよ」と話のネタにしてみてはいかがでしょうか?
本日の名言をご紹介して締めくくりたいと思います。
「自然は最高の教師である」 – レオナルド・ダ・ヴィンチ
トナカイと鹿の違いを見ていると、自然環境に適応して進化してきた生き物の素晴らしさを感じますね。皆さんも自然の不思議に触れる機会を大切にしてくださいね!
それではまた次回の記事でお会いしましょう!ミーミルメディア編集長のしげっちでした!