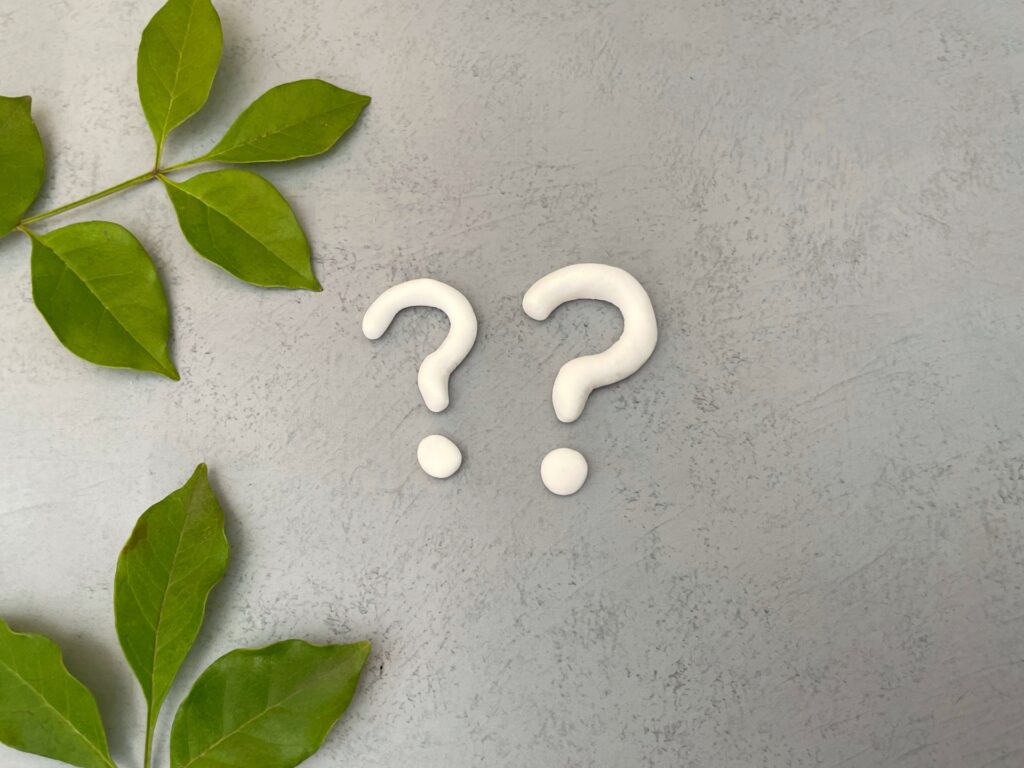こんにちは!ミーミルメディア編集長のしげっちです。最近、息子が高校に入学して、将来のことを考える機会が増えてきました。皆さんの中にも、親から財産を引き継いだり、子どもに財産を渡したりすることを考えている方もいるのではないでしょうか?
今回は「贈与税と相続税の違い」について詳しく解説していきます。この2つの税金、なんとなく似ているけど違いがよく分からない…という方も多いはず。ボクも調べるまではスッキリ理解できていませんでした。でも、この違いを知っておくことで、将来の税負担を大きく減らせる可能性があるんですよ!
贈与税と相続税の基本的な違い
まず基本から押さえておきましょう。贈与税と相続税は、どちらも財産を移転する際にかかる税金ですが、そのタイミングや方法が大きく異なります。
発生するタイミングが違う
相続税は、人が亡くなった後に財産が相続人に移る際に発生します。つまり、被相続人の死亡がきっかけとなります。
一方、贈与税は生きている人から財産をもらった時に発生します。当事者同士の合意によって財産が移転するときにかかるんですね。
課税対象の違い
相続税は、亡くなった方の財産総額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を引いた金額に対して課税されます。例えば、法定相続人が2人の場合、4,200万円までは相続税がかかりません。
贈与税は、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った贈与財産の合計額から基礎控除額110万円を引いた金額に課税されます。つまり、年間110万円までの贈与なら税金はゼロということですね。
税率の違い
同じ金額の財産を一度に引き渡す場合、相続税よりも贈与税のほうが税率が高く設定されています。これは、生前贈与によって相続税を回避することを防ぐための仕組みなんです。
相続税と贈与税の税率を比較してみよう
具体的な税率を見てみましょう。同じ金額でも、相続と贈与では税負担が大きく異なります。
相続税の税率
相続税は、課税対象額に応じて10%〜55%の累進課税となっています。基礎控除額が大きいのが特徴です。
贈与税の税率
贈与税も累進課税で、最大55%まで税率が上がります。ただし、親や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与には特例税率が適用されることもあります。
具体的な計算例で比較してみよう
例えば、5,000万円の財産を18歳以上のお子さん一人に渡す場合を考えてみましょう。
相続の場合:
- 基礎控除額:3,000万円+600万円=3,600万円
- 課税対象額:5,000万円−3,600万円=1,400万円
- 相続税額:1,400万円×15%−50万円=160万円
贈与の場合(特例税率適用):
- 基礎控除額:110万円
- 課税対象額:5,000万円−110万円=4,890万円
- 贈与税額:4,890万円×55%−640万円=2,049.5万円
この例では、相続税が160万円に対して贈与税は2,049.5万円と、大きな差があることがわかりますね!
税負担を減らすための特例制度
でも、実はこれだけで「相続の方が得」と判断するのは早計です。それぞれに税負担を軽減できる特例があるからです。
相続税の主な特例
- 配偶者の税額軽減:配偶者が相続する財産が1億6千万円または法定相続分までなら相続税がかかりません
- 小規模宅地等の特例:自宅の土地の評価額を最大80%減額できる特例があります
贈与税の主な特例
- 暦年贈与:毎年110万円までの贈与は非課税です
- 相続時精算課税制度:60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与で、2,500万円まで贈与税がかかりません(ただし相続時に相続財産に加算されます)
- 住宅取得資金の贈与:一定の条件を満たせば、住宅取得資金の贈与に非課税枠があります
どちらが得?状況別の選び方
「結局どっちが得なの?」という疑問に対する答えは、「ケースバイケース」です。
財産額が相続税の基礎控除額以下なら、相続の方が税金はかかりません。一方、財産額が大きい場合は、計画的な生前贈与を組み合わせることで、トータルの税負担を減らせる可能性があります。
例えば、毎年110万円ずつ贈与していけば、10年で1,100万円を非課税で渡すことができます。これを「暦年贈与」と呼びます。
ただし、贈与を受けた日から3年以内(令和6年以降は段階的に7年に延長)に贈与者が亡くなった場合は、その贈与財産は相続財産に含めて計算されるので注意が必要です。
まとめ:賢い財産の引き継ぎ方
贈与税と相続税の違いを理解したうえで、自分の状況に合った方法を選ぶことが大切です。一般的には、以下のような方針がおすすめです。
- 相続税がかからない範囲内なら、相続で引き継ぐ
- 相続税がかかる見込みなら、計画的な生前贈与も検討する
- 特例制度を上手に活用する
- 早めに専門家に相談する
税制は複雑で、個人の状況によって最適な方法は異なります。早めに税理士などの専門家に相談して、自分に合った対策を立てることをおすすめします。
皆さんの大切な財産を、次の世代に少しでも多く残せるよう、今日からできることから始めてみませんか?
本日の名言です。
「準備する時間は決して無駄にはならない」 – アブラハム・リンカーン
財産の引き継ぎも、早めの準備が大切です。今日から少しずつ考えていきましょう!