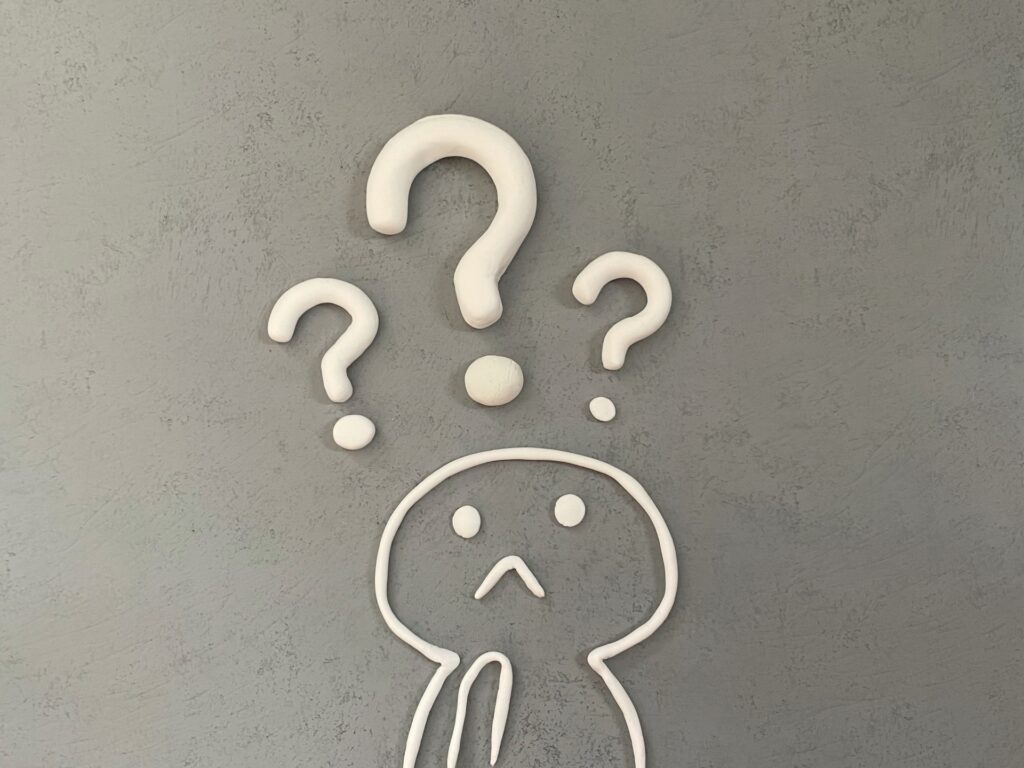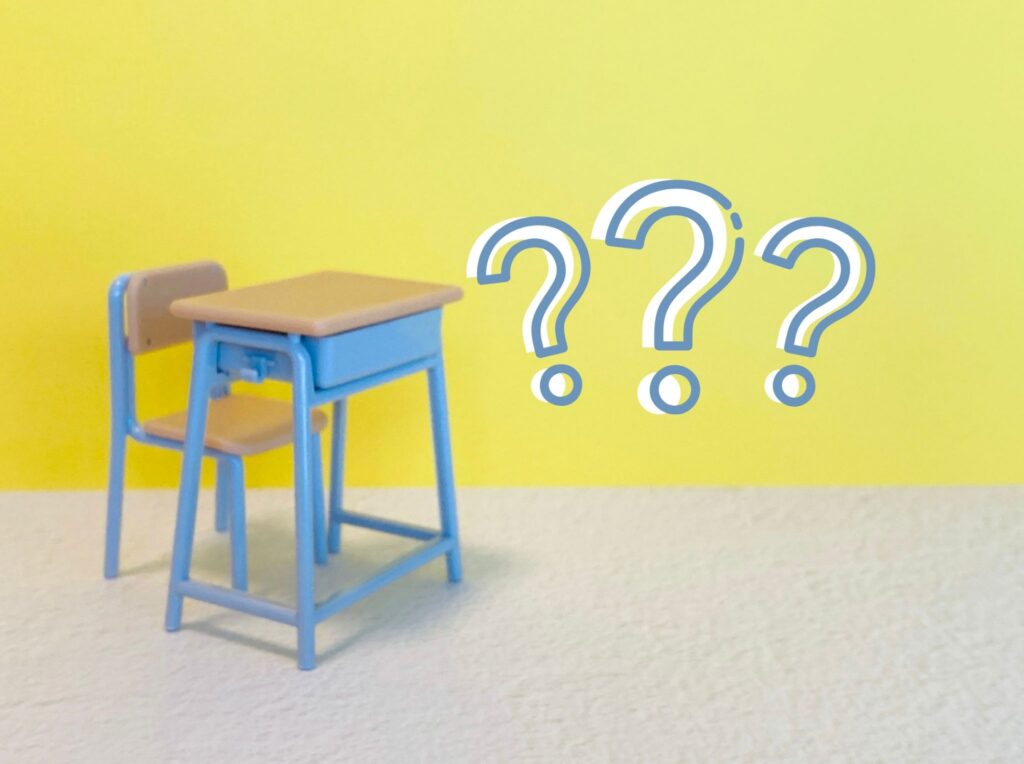こんにちは、皆さん!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日は日常生活でよく目にする「苗字」と「名字」について、その違いや由来を詳しく解説していきたいと思います。実は、ボクも最近まで正確な違いを知らなかったんですよね。皆さんはどちらの表記が正しいと思いますか?
「苗字」と「名字」の基本的な違い
結論から言うと、「苗字」と「名字」はどちらも間違いではなく、指し示す意味も同じなんです!つまり、ある人の上の名前(家族名)を意味します。例えば「山田太郎」さんであれば「山田」の部分ですね。
ただし、由来はそれぞれ異なります。ここがポイントなんですよ。
「名字」の由来と歴史
「名」という漢字には「なまえ、よびな、なづける」など、名前に関わる意味があります。また「字」という漢字は「あざな」とも読み、「実名のほかに付ける呼び名」という意味合いがあるんです。
「名字」は平安時代ごろから既に使われていたとされています。当時は「同一の氏(うじ)から分かれ出て、その住む地名などにちなんで付けた名」という意味でした。例えば、藤原氏の人がたくさんいて紛らわしかったため、国名の一字と「藤」を組み合わせ、「加賀国」で「加藤」、「下野国佐野庄」で「佐藤」といった具合に名字ができたんですよ。
「苗字」の由来と広まり
一方、「苗」という漢字には名前に関連した意味は特にありませんが、「血筋、子孫」という意味があります。
江戸時代には、「苗字帯刀」という武士の特権があり、庶民は上の名前を公称することが禁止されていました。この頃から「名字」と同じ意味として、「苗字」という表記がよく使用されるようになったようです。
なぜ「苗字」という表記が江戸時代から一般的になったのかについて詳しくはわかっていませんが、特権階級が使用するものとして、より血筋に対する意識が色濃くなった結果なのかもしれません。ちょっと面白い歴史ですよね!
公的文書では「名字」が使われる理由
現在、公的文書や新聞などでは「名字」の方がよく使われています。これには明確な理由があります。
「みょう」という読み方が、常用漢字表での「苗」の読み方として認められていない、つまり表外読みだからなんです。常用漢字表では、「苗」の読み方は「びょう」「なえ」「なわ」しか認められていません。そのため、公的表記としては「名字」が正しい、とされているわけです。
でも日常生活では、どちらを使っても間違いではないので安心してくださいね!
「氏」「姓」との違いと関係
「名字」「苗字」と並んでよく使われる「氏」「姓」についても触れておきましょう。
「氏」について
「氏」とは、「うじ」と読み、古くは日本の古代社会で使用されていた、大きな家族の名前のようなものです。もともとは血縁で結ばれた、または祖先を同じくするとされる一族、つまり氏族のそれぞれの呼称でした。
しかし同じ氏の人が多くややこしいため、後に名字が誕生します。現在では、「名字」と同じ意味で使用されています。
「姓」について
「姓」とは、もともと「かばね」と読み、古代の権力者たちが、「氏」に付け加えて名乗っていた、家柄や職業・政治的地位を表すものでした。最初のうちは、身分の上下を表す意味は特になかったのですが、大和朝廷の支配の世で、序列や地位が組織編成のために必要となり、その結果として身分の上下を表すようになりました。
現代においては「姓」も、「姓(せい)」として、「名字」と同じ意味で使われています。
歴史上の人物の正式な名前
昔は「名字(苗字)」「氏」「姓」が併存していました。例えば、徳川家康の正式な名前は「徳川次郎三郎源朝臣家康」です。
- 徳川:名字(苗字)
- 次郎三郎:通称
- 源:氏
- 朝臣:姓
- 家康:諱(いみな・実名)
「朝臣(あそん)」は、平安時代以降は姓の中で最も上の位置付けであり、多くの氏が称した姓です。織田信長も源頼朝も、実は姓は「朝臣」で共通しているんですよ。ビックリですよね!
日本の苗字の数と数え方
日本の名字(姓)の数は、苗字研究家であり文学博士丹羽基二氏著の「日本苗字大辞典」によると30万件弱あるとされています。
苗字の数え方には諸説あり、「伊藤、伊東、井藤、依藤、井東」など同じ「いとう」でも漢字構成の違いにより各1件とカウントする数え方や「伊藤」でも「いとう、いふじ」など「読み方の異なるもの」を各1件とカウントする数え方などがあります。
たくさんの苗字を出している他のサイトとの違いとしては、新字体で置き換えられるものは置き換え、まとめて数えるという考え方もあります。これは、「渡辺」さんと「渡邊」さんと「渡邉」さんは全て「渡辺」さんとして扱うということです。戸籍上では旧字体で登録されている場合でも新字体を使うか旧字体を使うかは全く本人の自由なので、総数がわかりにくくなるという理由からですね。
苗字に対する思い入れ
苗字には強い思い入れを持つ方も多いです。特に女性の場合、結婚によって苗字が変わることに抵抗を感じる方もいらっしゃいます。
年齢的にも孫の顔を見たいからもう苗字はいいから、土地だけでも維持してくれればと両親が言ってくれるので、恋愛結婚で長男で親族の中で男が1人だけの夫と半年前に結婚しました。夫にも結婚にあたって私は自分の名字を残したいと懇願しましたが、「自分は長男だから、君には兄がいるじゃないか」と受け入れてもらえませんでした。
このように、代々続いた土地や家名を守りたいという思いから、選択的夫婦別姓の導入を望む声も少なくありません。苗字は単なる記号ではなく、アイデンティティや家族の歴史と深く結びついているんですね。
まとめ:「苗字」と「名字」はどちらも正しい
「苗字」と「名字」は由来は違えど、本質的な意味は同じです。つまり、使い分けは必要ありません。ただ、公的書類では「名字」が使われることが多いという違いがあります。
また、「氏」「姓」も現代では同じような意味で使われていますが、歴史的には異なる意味を持っていました。日本の名前の歴史はとても奥深いですね!
皆さんの苗字にはどんな由来があるのでしょうか?ちょっと調べてみると、家族の歴史に思いを馳せるきっかけになるかもしれませんよ♪
本日の名言をご紹介します。
「名は体を表す」 – 古代中国の思想
名前には意味があり、その人の本質を表すという考え方です。皆さんの名前も、きっと素敵な意味があるはずですよ!それでは、また次回のミーミルメディアでお会いしましょう!