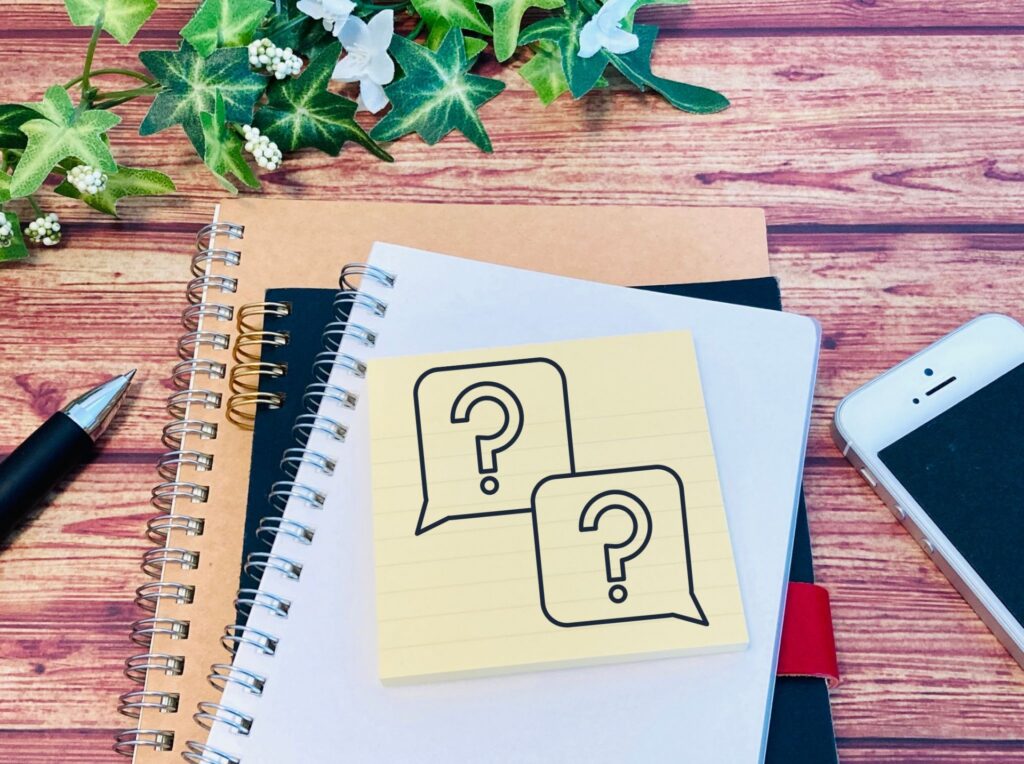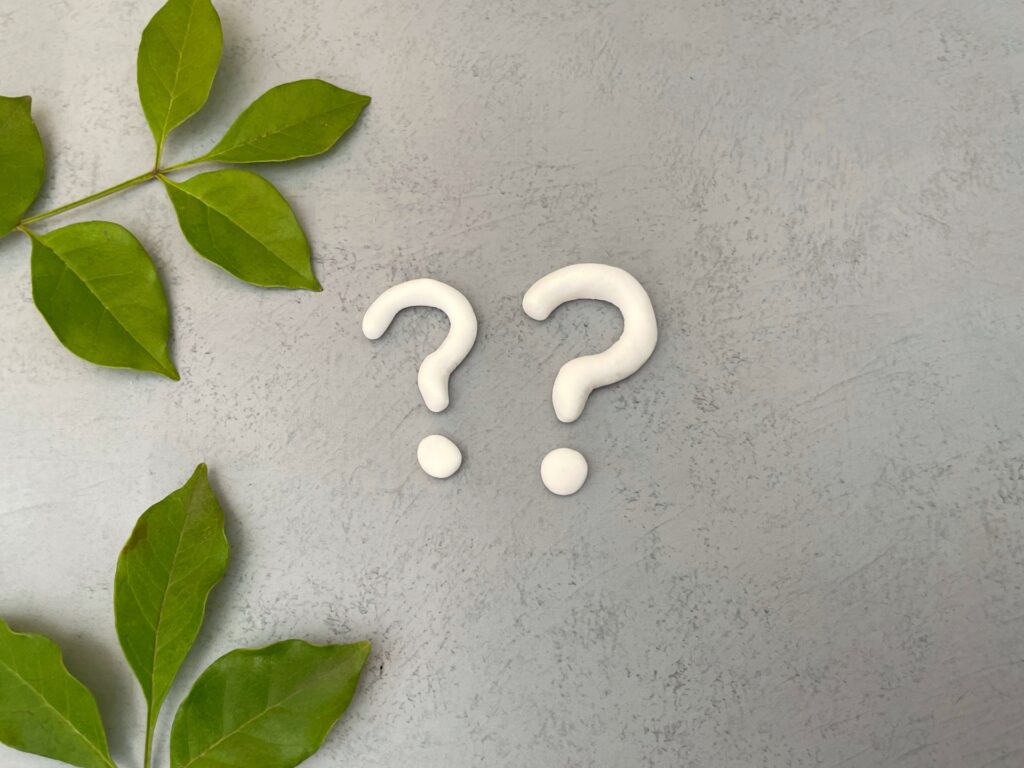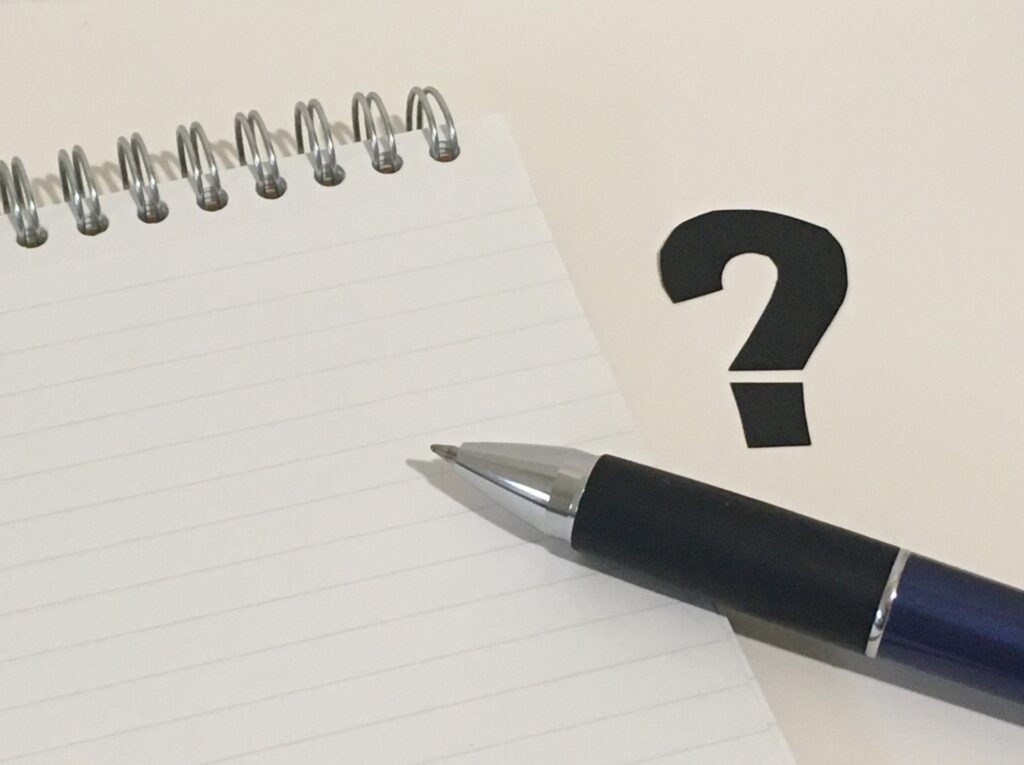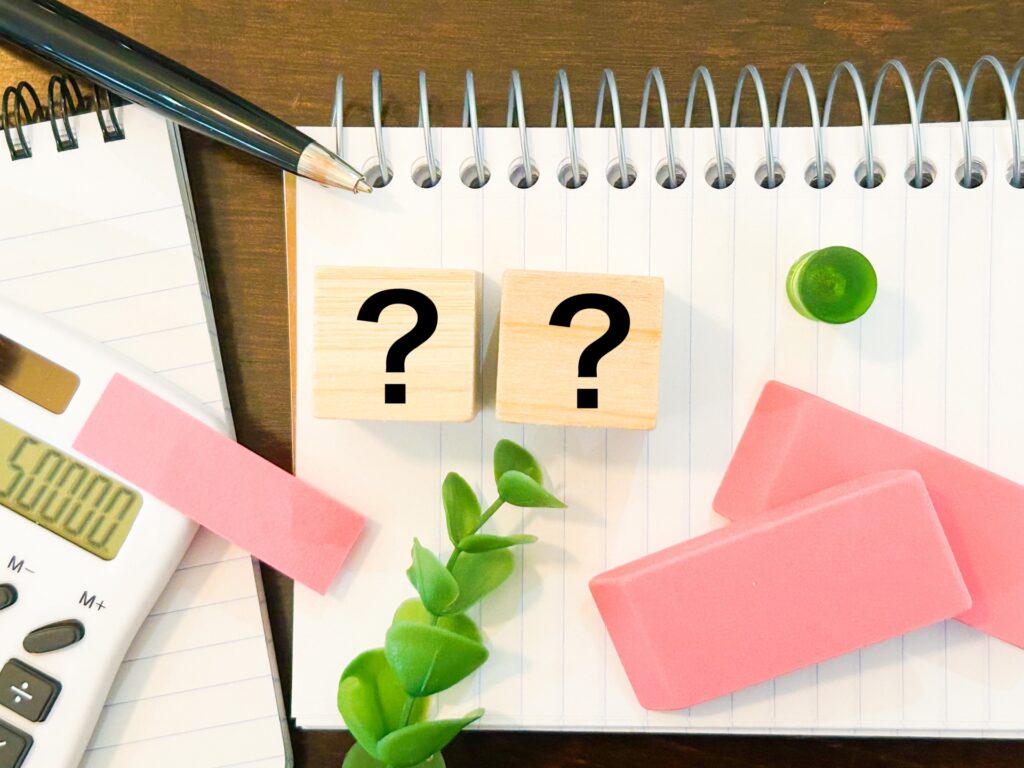こんにちは!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日は春のガーデニングに欠かせない「パンジー」と「ビオラ」の違いについてお話しします。この2つ、よく似ていて混同しがちですよね。ボクも最初は「同じ花の別名じゃないの?」なんて思っていました。でも実は、しっかりとした違いがあるんですよ!
パンジーとビオラの基本的な違い
まず最も分かりやすい違いは花の大きさです。一般的に園芸の世界では、花の直径が4cm以上のものをパンジー、4cm未満のものをビオラと区別しています。パンジーの中でも小輪は4~5cm、中輪は5~7cm、大輪は7cm以上で、中には10cm以上の超大輪種もあるんですよ!対してビオラは小輪で2~3cm、中輪で3~4cm程度が多く、小指の爪サイズの極小輪種まであります。
でも実は、植物学的には両者は同じビオラ属の植物なんです。ヨーロッパ各地に自生するビオラ属の野生種を何種類もかけ合わせた同じ祖先から作り出されたもので、大型犬と小型犬くらいの違いしかないんですね。
パンジーとビオラの性質の違い
花の大きさだけじゃなく、性質にも違いがあります。
開花の特徴
ビオラはパンジーに比べて「多花性」という特徴があります。つまり、一度にたくさんの花を咲かせるんですね。ビオラは成長が早く、長期にわたって次々と花を咲かせてくれます。一方、パンジーは一輪一輪が豪華で存在感がありますが、咲く花の数ではビオラには及びません。
環境への適応力
どちらも寒さに強い植物ですが、ビオラのほうがやや丈夫で育てやすい傾向があります。パンジーもビオラも日当たりと風通しの良い場所を好みますが、多少の環境変化にはビオラのほうが強いかもしれませんね。
最近のトレンド:ハイブリッド種の登場
近年の品種改良によって、パンジーとビオラの区別がますます難しくなっています。「パンジーの豪華さ」と「ビオラの多花性」を兼ね備えた「ハイブリッド種」が次々と誕生しているんです。
例えば「中輪パンジー」と呼ばれる新しいカテゴリーの花は、パンジーほど大きくなく、ビオラほど小さくない、ちょうど中間サイズの花を咲かせます。「よく咲くすみれ」というシリーズなども、パンジーとビオラの良いとこ取りをした品種です。
カラーバリエーションの豊富さ
パンジーもビオラも色のバリエーションが非常に豊富です。紫、白、クリーム、赤、ピンク、オレンジ、黄色、アプリコット、ブラウン、黒、そして複色まで、ほとんどの色を網羅していると言われるほど!最近は一つの花の中に複数の色が存在する複色カラーが人気で、明るく華やかな色からシックで大人っぽいものまで、様々な雰囲気を演出できます。
パンジーとビオラの育て方のポイント
どちらも基本的な育て方は同じですが、いくつか押さえておきたいポイントがあります。
日当たりと水やり
パンジーもビオラも日当たりと風通しの良い場所で育てるのがベスト。水やりは午前中に鉢の表面が渇いたらたっぷりと与えましょう。午後の水やりは避けたほうが良いです。なぜなら、夜までに土が適度に乾かず、根が霜でやられてしまう可能性があるからです。
肥料と花がら摘み
半年以上咲き続けるため、定期的な追肥が必要です。液体肥料でも固形肥料でもOK!それから、花がら摘みをまめにすることも大切です。花がらをそのままにしておくと、植物は種をつけることにエネルギーを使ってしまい、新しい花が咲きにくくなります。花がらを摘むことで、次々と新しい花を咲かせることができるんですよ。
冬の管理
冬の低温期は花数が少なくなりますが、一つの花が咲いている期間は長くなります。これは自然なことなので心配いりません。春になると再び次々と花を咲かせてくれますよ。
おすすめの楽しみ方
パンジーとビオラは単体でも素敵ですが、寄せ植えにするとさらに魅力が増します。同じ開花期間の草花と組み合わせると、長く楽しめる寄せ植えになりますよ。また、切り花としても楽しめます。最近は切り花用に改良された花茎の長いパンジーも流通しているので、小さな花瓶に飾ってみるのもステキですね!
ガーデニング初心者さんには、育てやすいビオラから始めるのがおすすめです。経験を積んだら、豪華なパンジーにも挑戦してみてくださいね。
今日のお話はいかがでしたか?パンジーとビオラ、それぞれの魅力を知って、ぜひお庭やベランダで育ててみてくださいね。春の訪れを感じさせてくれる、この可愛らしい花たちとの時間を楽しんでください♪
「花を育てることは、希望を育てること」 – ルーシー・モード・モンゴメリ
今日も最後まで読んでくださってありがとうございました!皆さんの毎日が花のように明るく彩られますように!