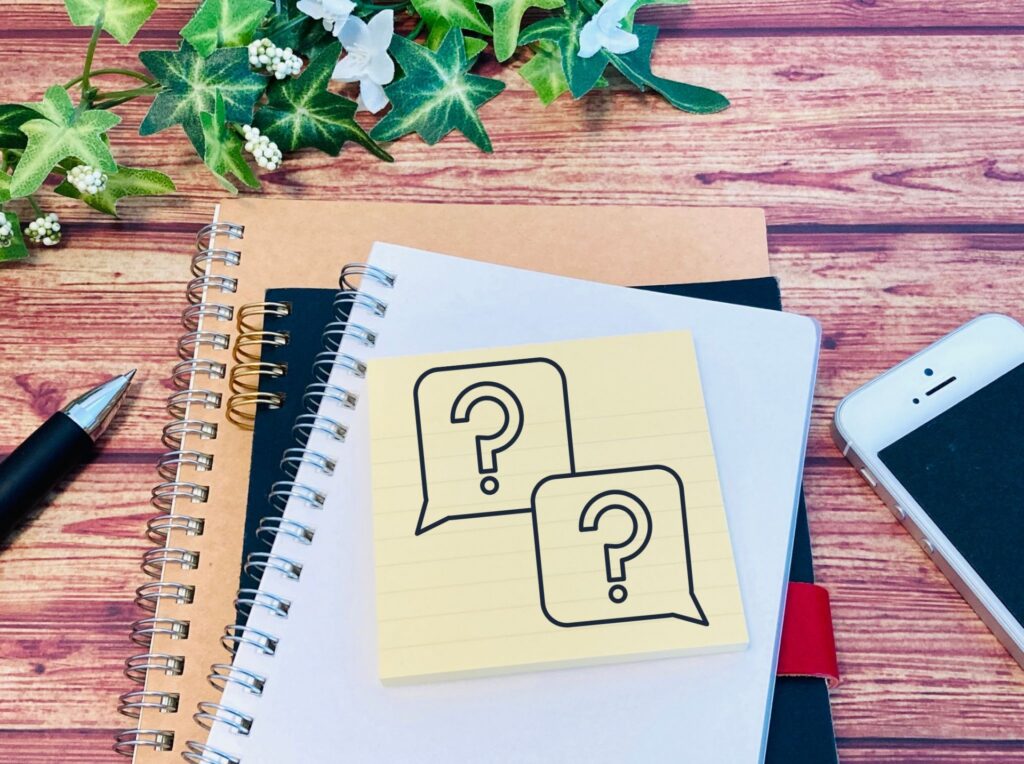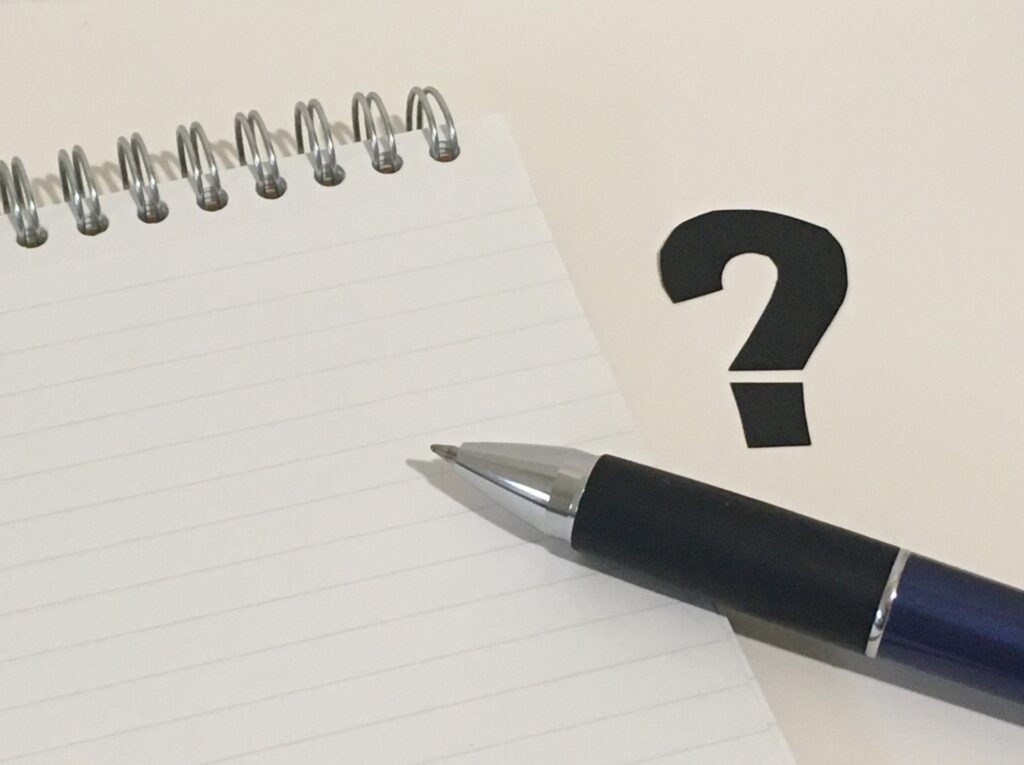こんにちは、皆さん!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日は日本のお茶文化の中でも特に混同されがちな「番茶」と「ほうじ茶」について詳しくお話ししていきますね。
実は先日、息子が学校の宿題で日本のお茶について調べることになり、「パパ、番茶とほうじ茶って何が違うの?」と聞かれたんです。そこでボクも改めて調べてみたら、意外と奥が深くて!これは皆さんにもシェアしたいと思いました。
お茶好きの方も、「なんとなく飲んでるけど違いはよく分からない」という方も、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
番茶とほうじ茶の基本的な違い
まず最初に、番茶とほうじ茶の決定的な違いをスッキリ説明しましょう。
番茶とほうじ茶の最大の違いは「焙じているかいないか」です。つまり、製法の違いなんですね!
番茶は、茶摘み後に茶葉を蒸してから乾燥させ、その後に茶葉を揉んで砕いたり、煎ったりすることで製造されます。一方、ほうじ茶は茶葉(煎茶や番茶、茎茶など)を高温(約200℃)で5〜10分ほど焙煎して作られるお茶です。
簡単に言うと、「番茶=材料」、「ほうじ茶=加工品」と考えるとわかりやすいかもしれませんね。
見た目や味わいの違い
番茶とほうじ茶は見た目でもハッキリ区別できます。
番茶の特徴
番茶は葉っぱが緑色で、お茶を入れると黄色っぽい色になります。味わいはさっぱりとしていて苦味も少なく、非常に飲みやすいのが特徴です。
ほうじ茶の特徴
一方、ほうじ茶は焙煎によって茶葉が茶色になり、お茶を入れると赤褐色の液体になります。「病院でよく出される赤っぽいお茶」というとピンとくる方も多いのではないでしょうか?
ほうじ茶の最大の魅力は香ばしい香り!この香りの正体は「ピラジン」という成分で、茶葉に含まれるアミノ酸と糖が加熱されることで生成される香気成分なんです。このピラジンには、脳をリラックスさせる効果もあるといわれています。
味わいは、香ばしさに加えて、まろやかな甘みとコクが感じられます。これも焙煎の影響で、もともとの茶葉に含まれるカテキンなどの渋み成分が水に溶けにくい成分へと変化し、さらに焙煎によって茶葉の糖分がカラメル化して甘みが増しているんですよ。
地域による認識の違い
面白いことに、番茶とほうじ茶の認識は地域によって異なります。
北海道や東北、北陸地方では、「番茶」といえばほうじ茶のことを指すことが多いんです。そのため、「ほうじ茶と番茶は全然違う!」という人もいれば、「同じだと思っていた」という人もいるのは当然のことなんですね。
また、京都の「京番茶」は一般的な番茶と味も異なり、独特の燻製のような香ばしい味が特徴的で、全国的にも有名です。
カフェイン量の違い
お茶を選ぶ際に気になるのがカフェイン量ですよね。
まろやかな味わいのほうじ茶は、なんとなく普通の煎茶よりもカフェイン量が少ないと思われがちですが、実はその量は普通煎茶とほとんど同じなんです。確かに、焙煎の過程で一部のカフェインは気化するのですが、それもごくわずかなので、「ほうじ茶はカフェインが少ない」というのは誤りなんですよ。
一方の番茶は、ほうじ茶よりもカフェインの含有量が少なく、種類によってはノンカフェインのものもあるので、刺激が少なく体に優しいお茶といわれています。
これは、茶葉は摘み取り時期によってカフェインの含有量が変わるためです。一般的に摘み取り開始時期の新茶が最もカフェイン含有量が多く、摘み取りの回数を重ねるにつれて、茶葉のカフェイン含有量は少なくなっていきます。三番茶や秋以降に収穫される茶葉を使って作られる番茶は、含まれるカフェイン量が少なくなるんです。
カテキン量の違い
カテキンといえば、お茶の健康効果で有名な成分ですよね。
ほうじ茶の場合は、焙煎によって茶葉に含まれるカテキンが、水に溶けない成分へと変化します。そのため、他のお茶に比べるとカテキン量は圧倒的に少なくなります。
一方の番茶はカテキン量が多いことが特徴です。茶葉にもともと含まれているテアニンは、太陽光を浴びてカテキンへと変化していきます。つまり、古い葉ほど、長い時間をかけてテアニンからカテキンが生成されているため、カテキン量が多くなるのです。
一番茶のようなうまみは期待できないのですが、カテキン豊富なため、渋みや苦みが引き立ち、きりっとした味わいになります。
番茶とほうじ茶の選び方
では、どんなときにどちらのお茶を選べばいいのでしょうか?
番茶がおすすめな場面
- カフェインを控えたい方
- 就寝前のリラックスタイム
- さっぱりとした味わいを楽しみたいとき
- カテキンの健康効果を期待するとき
ほうじ茶がおすすめな場面
- 香ばしい香りを楽しみたいとき
- 脂っこい食事の後
- リラックス効果を期待するとき
- 子どもにもおいしく飲んでもらいたいとき
ボクの家では、夕食後は香ばしいほうじ茶、寝る前は番茶と使い分けています。子どもたちも「今日はどっちのお茶にする?」と楽しんでいますよ。
まとめ:番茶とほうじ茶、それぞれの魅力
いかがでしたか?番茶とほうじ茶の違いについて理解が深まったでしょうか。
番茶は茶葉そのものを指し、ほうじ茶はその茶葉を焙煎して作られるお茶です。見た目、香り、味わい、カフェイン量、カテキン量など、さまざまな点で違いがあることがわかりましたね。
地域によって認識が異なる点も面白いですね。皆さんの地域では、番茶とほうじ茶はどのように呼ばれているでしょうか?
日本のお茶文化は本当に奥が深く、同じ茶葉からでも製法によって全く異なる味わいが生まれるのは素晴らしいことだと思います。ぜひ、番茶とほうじ茶を飲み比べて、それぞれの魅力を発見してみてくださいね!
「人生は一杯のお茶のようなもの。その味わい方で価値が決まる」 – 中国のことわざ
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!皆さんの毎日が香り高いお茶のように、豊かな味わいに満ちていますように。