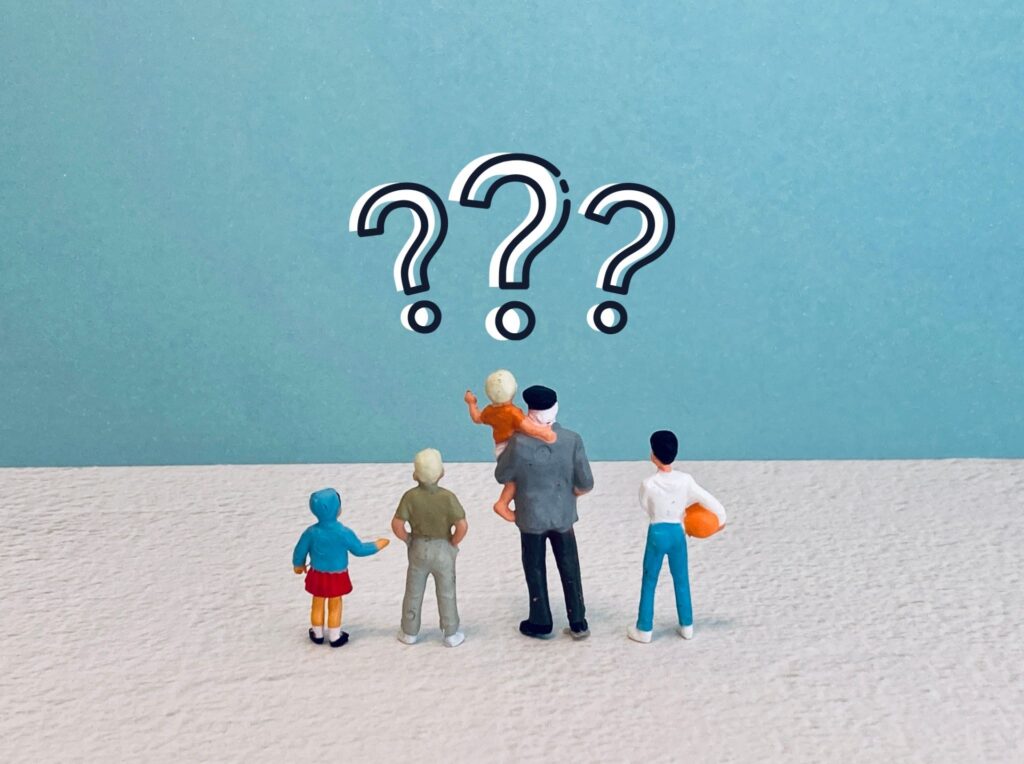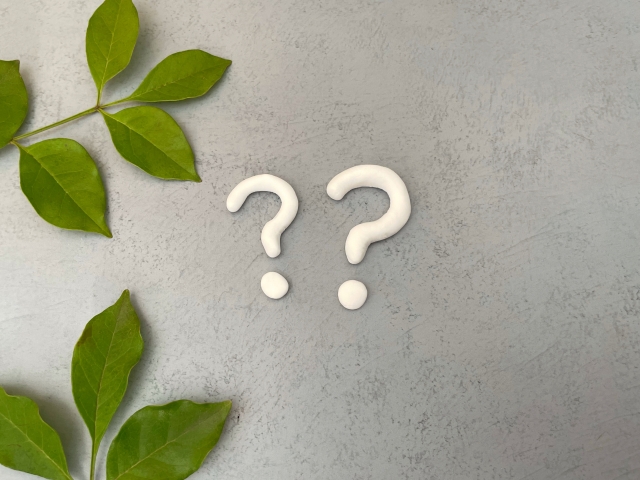こんにちは!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日は皆さんに、日本の歴史を形作った二つの重要な憲法について、わかりやすくお伝えしていきますね。大日本帝国憲法と日本国憲法、この二つの違いを知ることで、現代の日本がどのように形成されてきたのかが見えてくるんですよ!
ボクの息子(高1)が先日、「パパ、学校で憲法について習ったけど、昔の憲法と今の憲法って全然違うんだね」と言ってきたんです。そこで改めて調べてみたら、本当に面白いほど違いがあったので、皆さんにもシェアしたいと思いました。それじゃあ、さっそく見ていきましょう!
主権者の違い:天皇から国民へ
大日本帝国憲法と日本国憲法の最も大きな違いは、主権者が誰なのかという点です。
大日本帝国憲法では、主権者は天皇でした。国の政治を最終的に決める権利は天皇にあり、立法・行政・司法のすべての権限を天皇が持っていたんです。国民は「臣民(しんみん)」と呼ばれ、天皇に服従する立場にありました。
一方、日本国憲法では主権者は国民に変わりました。天皇は「国および国民統合の象徴」という立場になり、政治的な権限はなくなったんです。これって、国の形が根本から変わったということですよね!
憲法の制定方法:欽定憲法から民定憲法へ
憲法の制定方法にも大きな違いがあります。
大日本帝国憲法は「欽定(きんてい)憲法」といって、天皇から国民に与えられたものでした。1889年(明治22年)2月11日に発布され、翌年から施行されました。日本で初めての憲法だったんですよ!
対して、日本国憲法は「民定憲法」といって、議会が定めたものです。1946年11月3日に公布され、1947年5月3日から施行されています。つまり、誰が憲法を定めるかという点でも、両者は正反対なんですね。
人権保障の違い:制限付きから基本的人権の尊重へ
人権に関する考え方も、両憲法では大きく異なります。
大日本帝国憲法では、人権は「臣民の権利」として、法律の範囲内でのみ保障されていました。居住・移転・信教・言論・出版などの自由や私有財産の保護は、あくまで法律で定められた範囲内でしか認められなかったんです。
日本国憲法では、基本的人権は「侵すことのできない永久の権利」として、最大限に尊重されるべきものとされています。人が生まれながらにして持つ権利として保障されており、公共の福祉に反しない限り制限されることはありません。
国民の義務:兵役から三大義務へ
国民の義務についても、両憲法では異なる規定がされています。
大日本帝国憲法では、国民の義務として「納税」と「兵役」が規定されていました。徴兵令によって、原則として満20歳以上のすべての男子に兵役義務が課されていたんです。
日本国憲法では、兵役義務は廃止され、代わりに「納税」「勤労」「教育」が国民の三大義務となりました。特に教育の義務は、子どもに教育を受けさせる保護者の義務なんですよ。これ、意外と知られていないポイントかもしれませんね!
平和主義:軍隊の位置づけ
平和に対する姿勢も、両憲法では大きく異なります。
大日本帝国憲法では、軍隊は天皇に直属するものとして、政府からも議会からも独立していました。外国と条約を結んだり、戦争を始めることもすべて天皇の権限でした。
日本国憲法では、第9条で戦争放棄と戦力不保持を定めています。「平和主義」は日本国憲法の三大原則の一つとなっており、国際紛争を解決する手段としての武力行使を放棄しているんです。
大日本帝国憲法が制定された背景
大日本帝国憲法が制定された背景には、明治政府の近代化への取り組みがありました。
江戸時代に欧米諸国と締結した「不平等条約」を改正するためには、日本が欧米と肩を並べる近代国家になる必要がありました。そのためには立憲政治の実現が不可欠だと考えた政府は、国会開設と憲法制定の準備を始めたんです。
1881年(明治14年)の「国会開設の勅諭(ちょくゆ)」によって、1890年(明治23年)に国会を開設することが決まり、徐々に立憲国家への枠組みが作られていきました。
憲法の条文作成の責任者に任命されたのは、後に日本初の内閣総理大臣となる伊藤博文でした。伊藤はヨーロッパ各国の憲法を調査し、特にドイツのプロイセン憲法を参考にして草案を作成しました。天皇中心の国づくりを目指していた明治政府にとって、皇帝が強い権力を持つプロイセン憲法は都合が良かったんですね。
日本国憲法の成立過程
日本国憲法は、第二次世界大戦後の占領下で制定されました。
終戦後、日本政府はGHQによってマッカーサー3原則に基づく民主的な憲法の作成を指示されました。しかし、政府が当初作成した松本案は明治憲法と大差ない内容だったため、GHQによって拒否されました。
その後、政府はGHQが作成した案をもとに憲法改正案を作成し、帝国議会での修正を経て、1946年11月3日に日本国憲法が公布されたんです。
まとめ:二つの憲法から見る日本の変化
大日本帝国憲法と日本国憲法の違いを見ると、日本という国がいかに大きく変わったかがわかります。主権者が天皇から国民へ、人権の扱いが制限付きから最大限の尊重へ、そして軍事国家から平和主義国家へと、根本的な変化を遂げたんですね。
皆さんは普段、憲法について考える機会はあまりないかもしれませんが、私たちの生活や権利は憲法によって守られています。たまには、日本の歴史を振り返りながら、現在の日本の姿について考えてみるのも良いかもしれませんね!
「歴史に学ぶ者は未来を制する」 – ウィンストン・チャーチル
今日のお話はいかがでしたか?ボクたちが当たり前のように思っている国の形は、実は長い歴史の中で大きく変化してきたものなんですね。これからも歴史を学びながら、より良い未来について考えていきましょう!