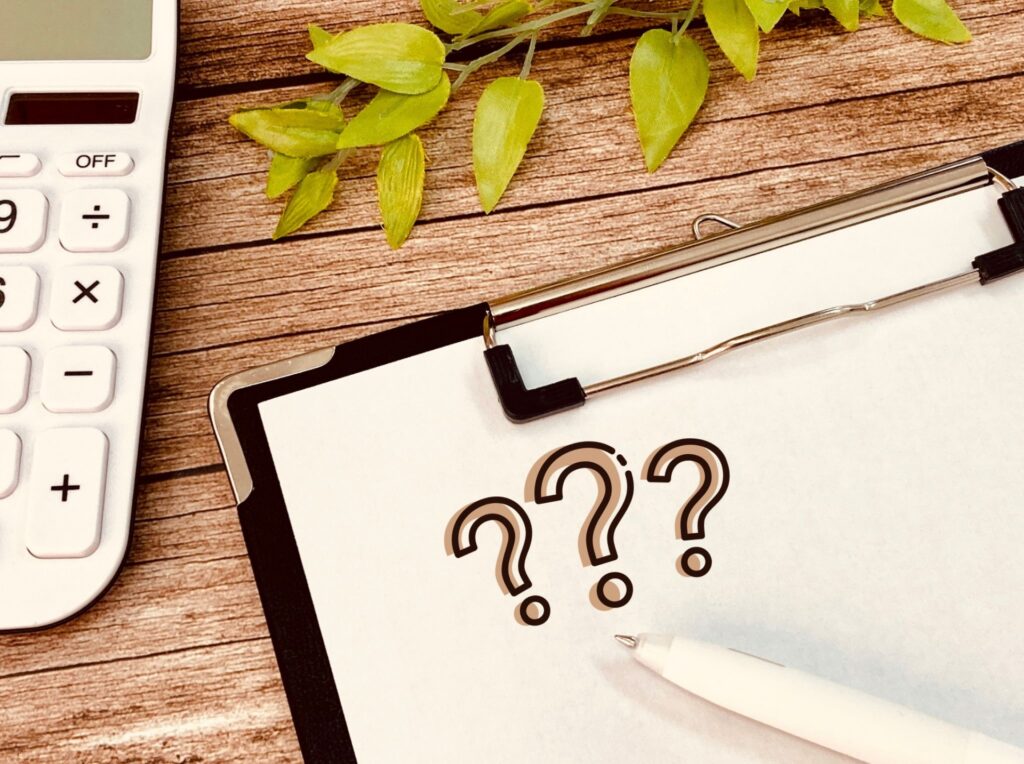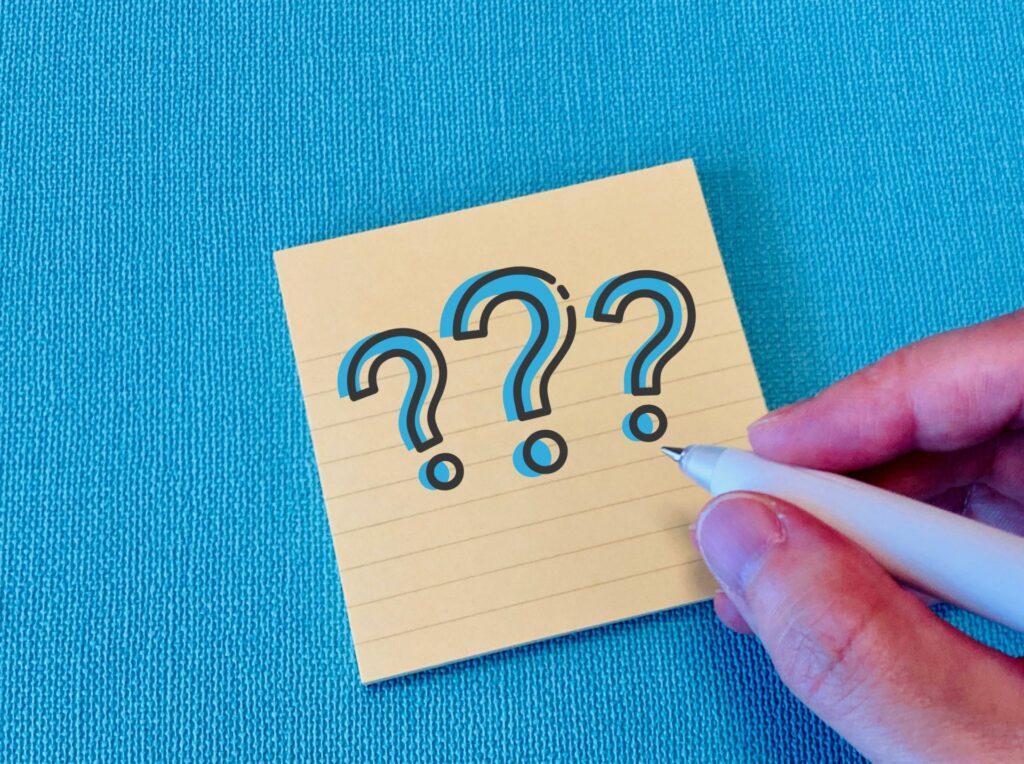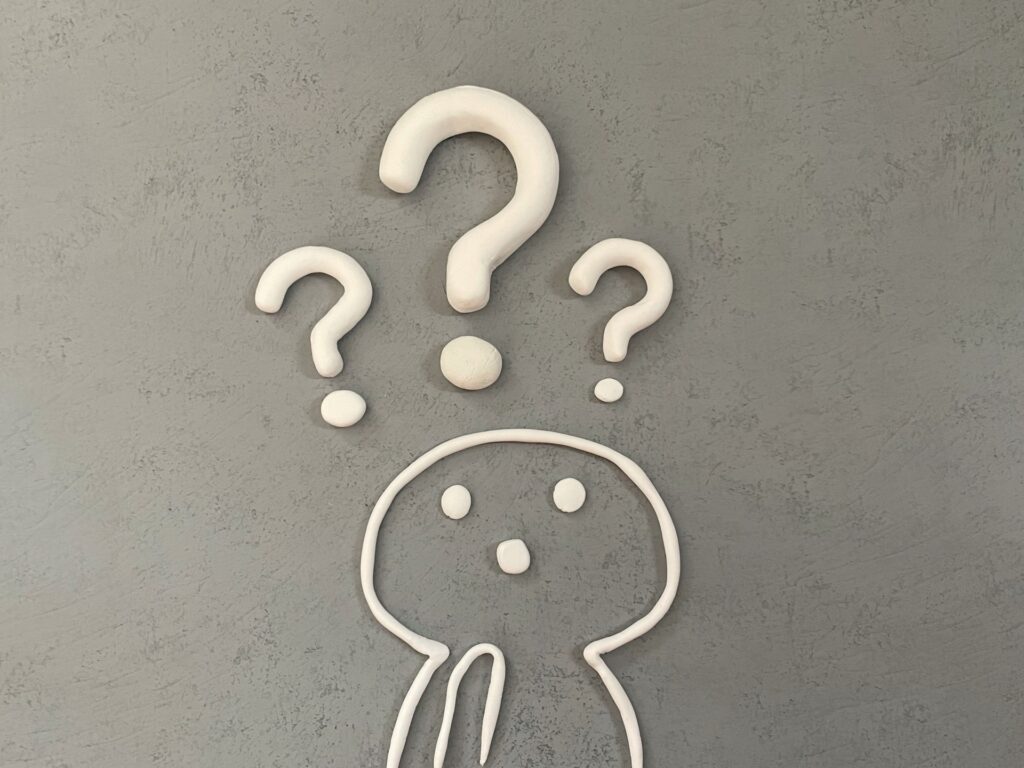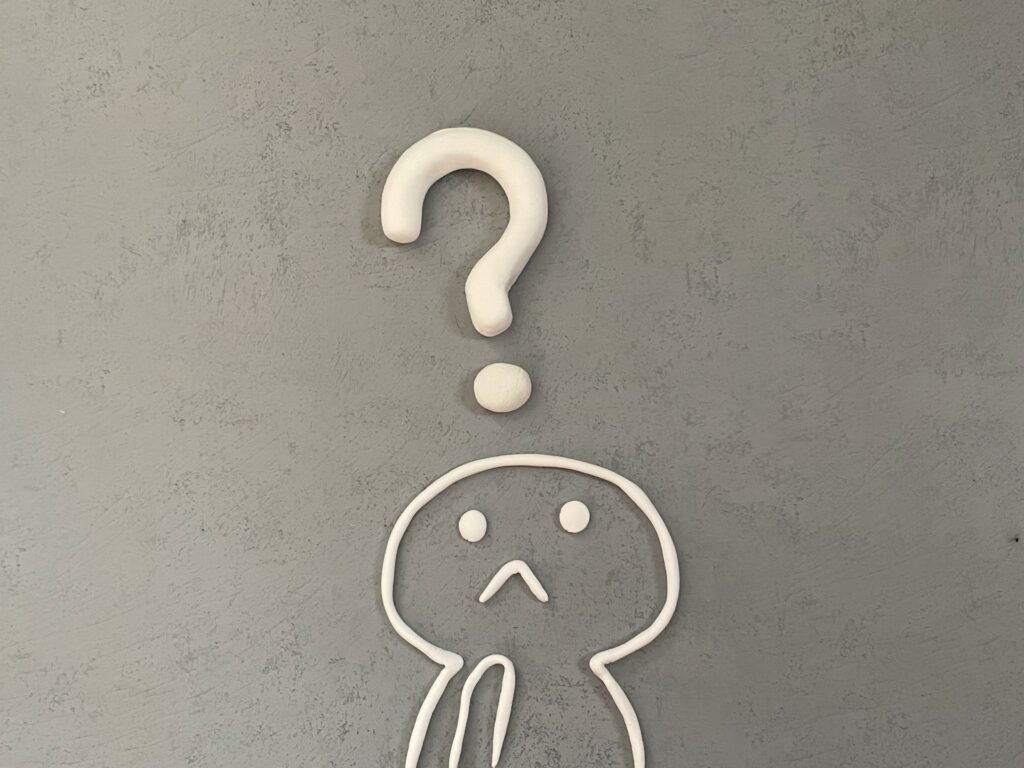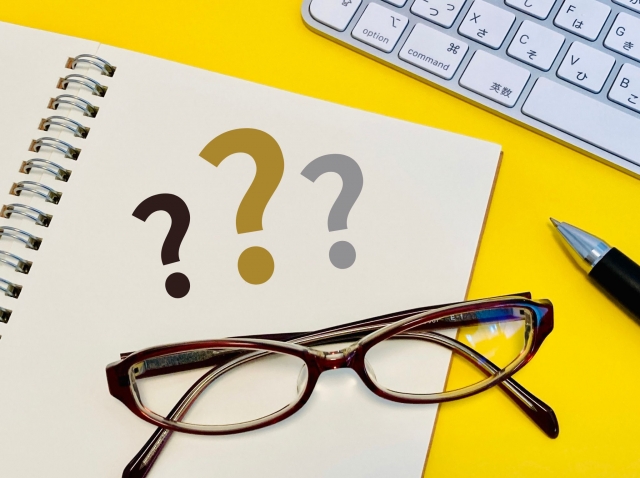こんにちは!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日は魚好きの皆さんにとって気になる「鱒と鮭の違い」について詳しくお話ししていきますね。実は、この違いって思ったよりも複雑で面白いんですよ。ボクも調べていくうちに「へぇ~!」と思うことがたくさんありました。皆さんは鮭と鱒の違いをはっきり説明できますか?意外と知らないことが多いかもしれませんよ。それでは早速見ていきましょう!
鮭と鱒の違いは実は曖昧?
結論から言うと、鮭と鱒の間には明確な区別がありません。これにはビックリしましたよね!実は生物学的に見ると、どちらもサケ科に属する魚で、厳密な区分がされていないんです。
かつては「海に下り産卵のために川に戻ってくるものを鮭、一生を川で過ごすものを鱒」と呼んでいました。しかし、生態がよく分からないうちに名付けられた魚もあり、現在では鮭と鱒の区別は曖昧になっているのが実状なんです。
例えば、カラフトマスは名前に「マス」とついていますが、実際には鮭の仲間です。また、同じ鱒でもヒメマスやニジマスのように川に残るタイプと海へ下るタイプの両方が存在します。
つまり、「鮭」と「鱒」という言葉は日本語の中で厳密な区別を持たない可能性が高いのです!
国際的な分類と日本での呼び方の違い
面白いことに、英語圏では「サーモン」と「トラウト」という言葉で区別しています。一般的に、海に下りて海洋生活を送る種を「サーモン(salmon)」、川や湖でその生涯を終える種を「トラウト(trout)」と呼びます。
しかし、日本では少し事情が異なります。日本では「鮭は海で獲れる大きなもの、鱒は淡水で獲れる小さなもの」という大雑把な分け方をしています。
さらに混乱の原因となっているのが、地域や漁獲される時期によって呼び名が変わることです。例えば、シロザケは地域によって「秋鮭」「シャケ」「時不知(トキシラズ)」「鮭児(ケイジ・ケンチ)」「ブナ」などと様々な名前で呼ばれています。
鮭と鱒の味の違い
味の面では、一般的に鮭は脂がのっており濃厚な旨味が特徴です。特に秋鮭は産卵前の栄養を蓄えているため、脂が豊富で濃厚な味わいを楽しめます。
一方、鱒は鮭に比べてあっさりとした味わいで、淡白な旨味が特徴です。特にニジマスは身が柔らかく、上品な味わいがあります。
いくらの違いも!
鮭のいくらと鱒のいくらにも違いがあるんですよ。鮭のいくらは粒が大きく、皮がしっかりとしていて、プチプチとした食感が特徴です。濃厚な味わいも魅力ですね。
対して鱒のいくらは粒が小さく、皮が薄いのが特徴です。ねっとりとした食感があり、鮭のいくらよりもあっさりとした味わいを楽しめます。
代表的な鮭の種類と特徴
鮭にはいくつかの種類があります。日本で一般的に食べられている鮭について見ていきましょう。
白鮭(シロザケ)
一般的に「鮭」と呼ばれるものは、この白鮭(シロザケ)のことを指します。身は薄いオレンジ色で、ほどよい脂乗りとクセのない味わいが特徴です。塩焼き、ムニエル、ちゃんちゃん焼きなど、様々な料理に利用できます。
紅鮭
名前の通り、身が鮮やかな紅色をしているのが特徴です。これはエビやカニにも含まれるアスタキサンチンという色素によるものなんですよ。身は引き締まっており、濃厚な味わいと強い旨味があります。塩焼きや焼き魚、粕漬けなどに向いています。
銀鮭
体が銀色をしていることから「銀鮭」と呼ばれます。身は脂がのっており、柔らかく、マイルドな味わいです。塩焼きやムニエル、フライなど、様々な料理に利用できますよ。
キングサーモン(マスノスケ)
別名マスノスケとも呼ばれ、最大で全長2mほどにもなる大型の鮭です。身はオレンジ色で、脂乗りが良く、濃厚な味わいが特徴です。日本で流通しているキングサーモンはアラスカ、カナダ、チリから輸入されているものがほとんどです。
代表的な鱒の種類と特徴
次に、代表的な鱒の種類についても見ていきましょう。
カラフトマス
カラフトマスは、鮭・鱒のなかでは全長60cm程度と、比較的小ぶりの種類です。国内で流通しているカラフトマスのほとんどが、北海道のオホーツク海沿岸で漁獲されています。筋肉があまりついていないため身がほぐれやすく、脂が少ないことが特徴です。
サクラマス
サクラマスは、もとは川で過ごすヤマメの一種で、ヤマメの中でも一部の個体が海に下り、大型に成長したものを指します。春の桜の時期に漁獲されることから「サクラマス」と呼ばれるようになりました。高級魚として上品な脂と濃厚な甘みが特徴で、雑味がほとんど感じられない味わいです。
ニジマス(トラウトサーモン)
国内で流通しているニジマスは、チリで海面養殖されたものがほとんどで、「トラウトサーモン」の名前で販売されています。サーモンの中では比較的安価で手に入りやすいのが特徴です。身はオレンジ色で、脂乗りが良く、クセのない弾力のある歯ごたえが楽しめます。
鮭とサーモンの違い
「鮭」と「サーモン」という言葉もよく混同されますが、これにも違いがあります。サーモンと鮭は同じサケ科に属する魚ですが、その大きな違いは生育環境にあります。
鮭は海水に生息し天然ものが多く、食べる際は加熱する必要があります。一方、サーモンは淡水で生息することが多く、養殖されたものは生食が可能です。
つまり、鮭とサーモンの違いは、生食できるかどうかが一つの判断基準となるんですね。
漁獲される時期による白鮭の呼び名の違い
日本で「鮭」といえば、一般的に白鮭(シロザケ)のことを指すことが多いですが、漁獲される時期によって呼び名が変わります。
秋鮭
秋鮭は、9~11月頃に生まれた川に戻ってくる鮭のことで、大量に漁獲する時期が白鮭の旬の時期です。産卵前の栄養を蓄えているため、脂がのっており、バランスの取れた味わいが特徴です。
時鮭(ときしらず)
春から初夏に獲れる鮭で、秋鮭のように秋の季節ではなく、時を忘れて戻ってくるため「ときしらず」という名がつきました。秋鮭とは違い、春から初夏にかけて水揚される鮭で、まだ成熟する前でお腹に卵や白子を抱えていない分、身に栄養がいきわたるため、身に脂がのっています。
鮭児(ケイジ)
鮭児(ケイジ)は秋鮭の定置網で、1万尾に1尾程度の割合でしか獲れないため、幻の鮭とも呼ばれ、高値で取引されています。「全身がトロ」と言われる程、脂肪の比率が極めて高く、刺身や寿司ネタで食べると舌の上でとろける味は絶品です。
メジカ鮭
メジカ鮭は、産卵前に漁獲される鮭のことで、産卵前のおよそ25~60日前に漁獲されます。定置網漁で「アキアジ」といっしょに漁獲されますが、「アキアジ」に比べて目と鼻先の間隔が短いことから「メジカ」(目近)と呼び名がつきました。若い鮭で、身はしっとりと脂のりの美味しい鮭です。
まとめ:鮭と鱒の違いを知って食卓を豊かに
いかがでしたか?鮭と鱒の違いについて詳しく見てきました。実は明確な区別がなく、生態や漁獲の時期などによって呼び方が変わる場合があることが分かりましたね。
それぞれの種類によって、味や食感、旬の時期などが異なり、様々な楽しみ方ができます。この記事を参考に、ぜひ色々な種類の鮭や鱒を味わってみてください。食卓がグッと豊かになりますよ!
「知識は力なり」 – フランシス・ベーコン
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!皆さんの食卓が、もっと楽しく、もっと美味しくなりますように!