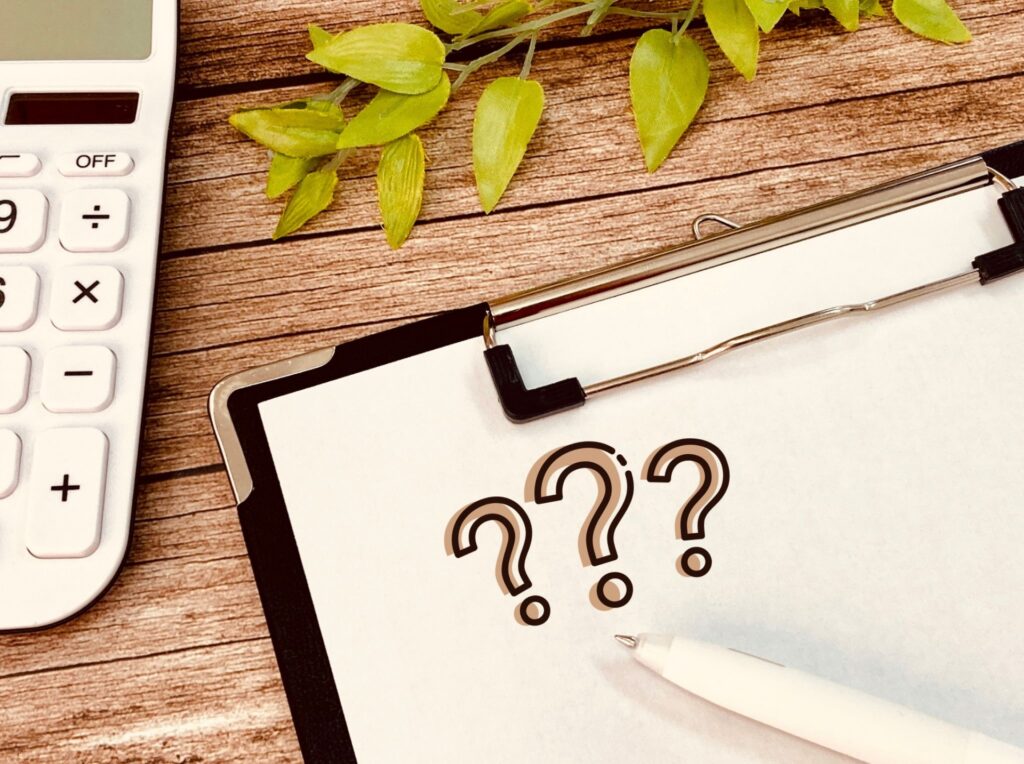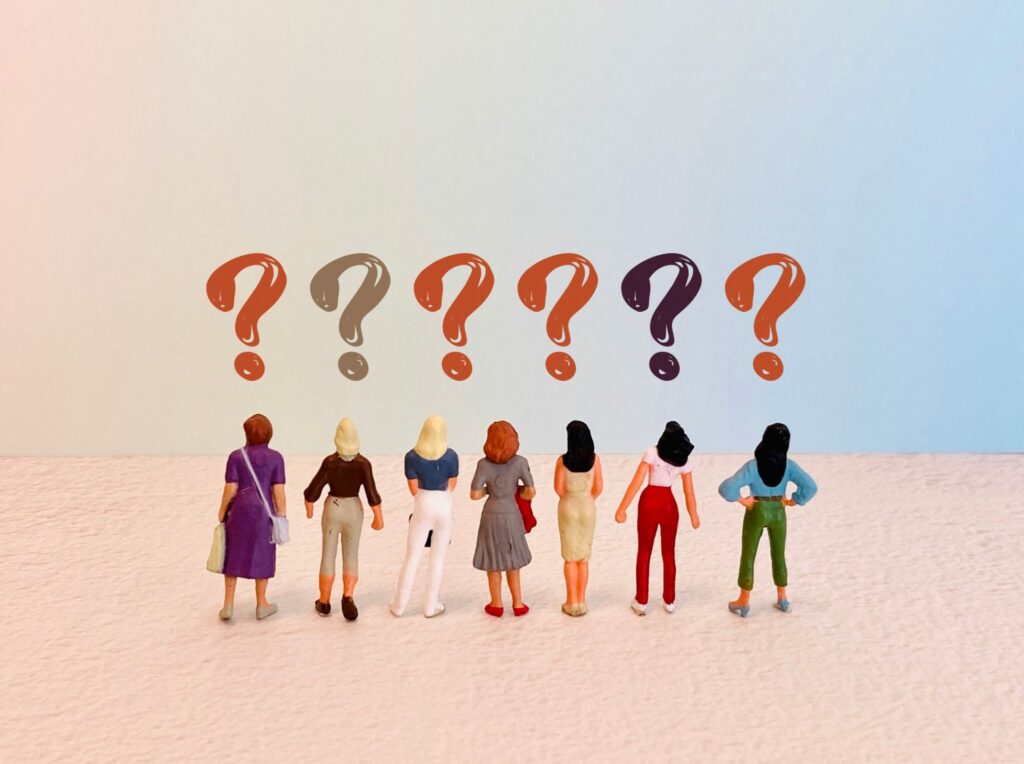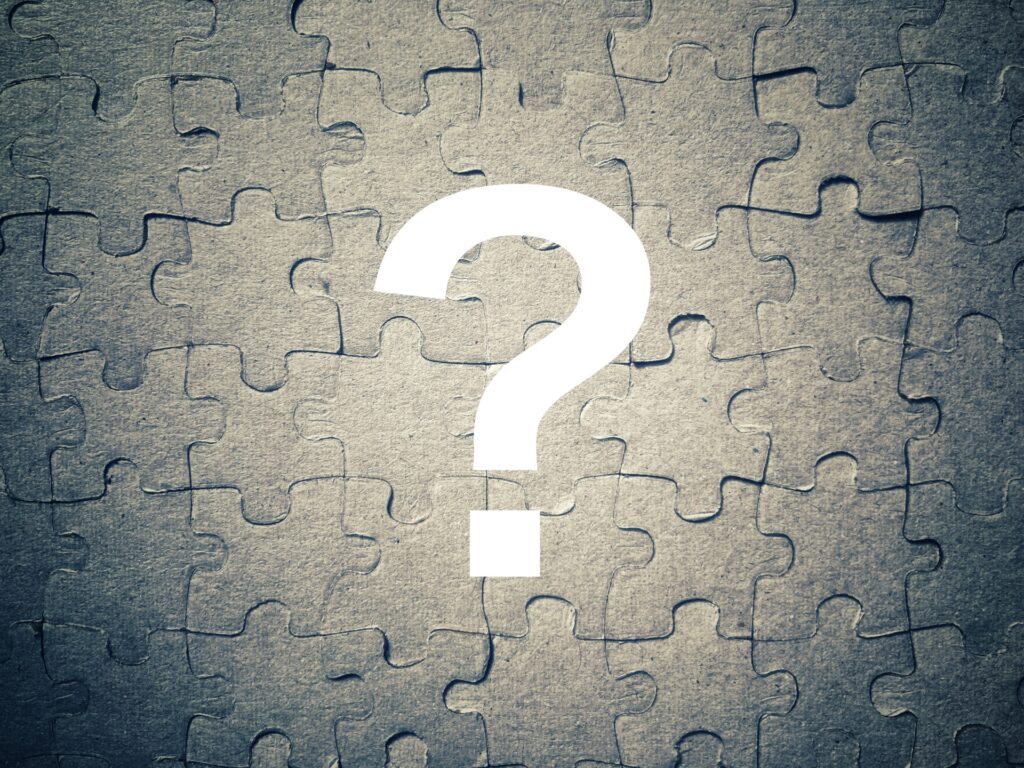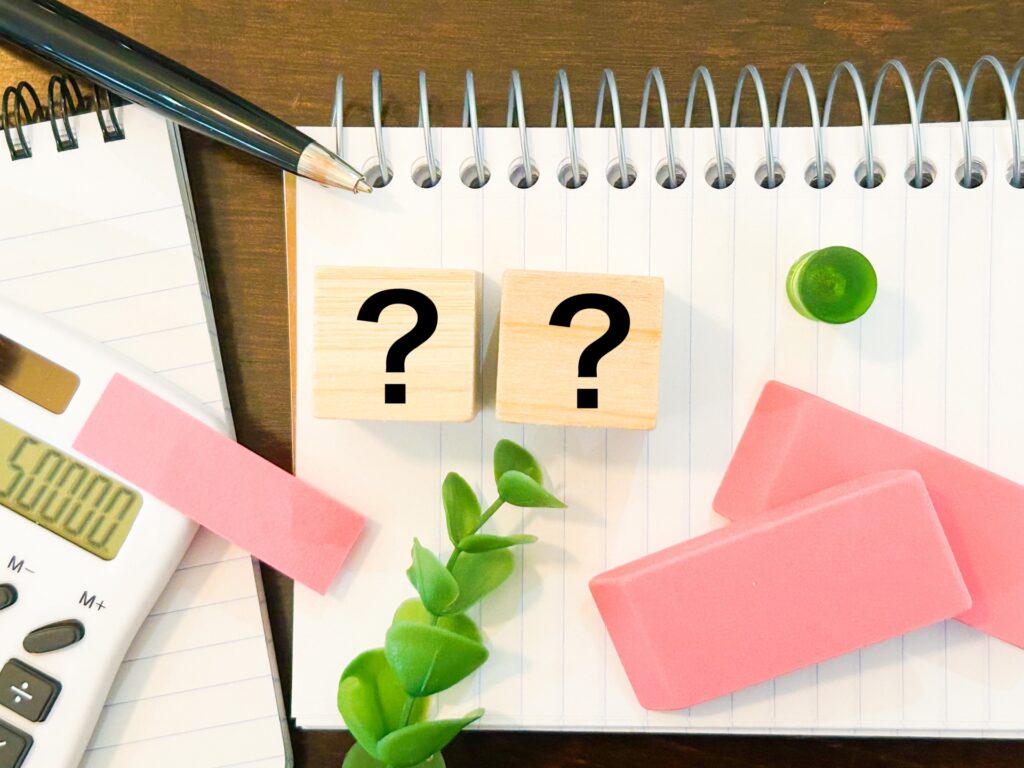こんにちは、皆さん!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日は春の陽気が気持ちいい一日ですね。子どもたちも元気に学校に行きました。さて、皆さんは「創業」と「設立」の違いをハッキリと説明できますか?ビジネスシーンでよく耳にするこれらの言葉、実は微妙に意味が違うんですよ。今日はそんな「創業」「設立」「創立」の違いについて、分かりやすく解説していきます!
ビジネスの世界では言葉の使い方一つで印象が変わることもありますよね。特に会社の歴史や成り立ちを説明する際に使われるこれらの言葉、正確に理解しておくと何かと役立ちます。それではさっそく見ていきましょう!
創業・創立・設立の基本的な意味の違い
まずは基本的な意味から整理していきましょう。
「創業」とは、シンプルに言うと「事業を始めること」を指します。個人でも法人でも、何らかの事業活動を開始した時点で「創業」と言えるんです。法人登記の有無は問いません。例えば、会社設立前の準備活動や原材料の仕入れなども創業活動に含まれます。
「創立」は「初めて組織や機関を立ち上げて事業を開始すること」です。こちらも登記や開業届は必要なく、会社だけでなく学校や団体にも使える言葉です。創業との大きな違いは組織の存在。個人事業主の場合は組織がないので「創立」とは言えないんですよ。
そして「設立」は「商業・法人を登記すること」を意味します。これが創業・創立と大きく異なるのは法的な手続きが必要な点です。定款作成、株主確定、取締役選任など一連の手続きを経て登記申請することを「設立」と言い、その申請日が会社の設立日となります。
創業者・創立者・設立者も意味が違う
人を表す言葉も微妙に違います。最初に事業を始めた人を「創業者」、初めて組織や機関を作った人を「創立者」と呼びます。「設立者」は法人登記する際の代表者として登記された人のことです。
面白いことに、創業から設立までの間に代表者が変わることもあるので、創業者と設立者が別人ということもあり得るんですよ。ボクの友人も個人で始めたビジネスを法人化する際に、奥さんを代表取締役にしたケースがありました。
法的に重要なのは「設立日」
創業・創立・設立の中で、法的な意味を持つのは「設立」です。設立日は会社法に則って設立登記をした日であり、会社が法人格を取得して社会的に認められた日として重要です。
設立日はどう決まる?
設立日は法務局に登記書類を提出した日になります。ただし、申請方法によって設立日が変わるので注意が必要です。
- 窓口申請の場合:法務局に申請書を提出した日
- 郵送の場合:法務局に申請書が届いた日
- オンライン申請の場合:登記所等にデータが受理された日
また、年末年始(12月29日~1月3日)や土日・祝日は法務局が休みなので、これらの日を設立日にすることはできません。法務局の開庁時間は平日8時30分~17時15分なので、この時間内に申請する必要があります。
設立日で変わる税金の負担額
ここで知っておきたいのが、設立日によって初年度の住民税(均等割)の負担額が変わるということ。住民税は1か月未満を切り捨てるため、設立日が1日である場合と2~31日である場合では、負担額が1か月分も変わってくるんです!
例えば、均等割額が年間7万円の会社の場合、1日に設立したか否かで年間約5,800円の差が生じます。節税を考えるなら、設立日は2日以降にした方がお得ですね。ギュウギュウに節約したい方は要チェックポイントです!
創業・創立・設立の使い分け方
これらの言葉、どんな場面で使い分ければいいのでしょうか?
歴史をアピールしたい場合
会社の長い歴史をアピールしたい場合は、「創業」や「創立」を使うと効果的です。例えば、創業が江戸時代の老舗企業でも、法人化したのは昭和以降というケースもあります。そんな時、「創業300年」とアピールすれば、会社の歴史の長さを強調できますね。
新規に会社を立ち上げる場合
新しく会社を立ち上げる場合は、「創立」や「設立」が一般的です。厳密には登記時点が「設立」ですが、広い意味では「創立」も使われます。
似ている言葉との違い
創業・創立・設立以外にも、新しくビジネスを始める際に使われる言葉がいくつかあります。これらも理解しておくと便利ですよ。
起業とは
「起業」は「事業を起こすこと」を意味します。創業と似ていますが、創業が過去の出来事を指すのに対し、起業は未来に向けて使われることが多いです。「これから起業する」というように、チャレンジするニュアンスも含まれます。
開業とは
「開業」は「新しく事業を始めること」を意味します。個人で事業を始める際によく使われる言葉です。個人事業主が税務署に「個人事業の開廃業届出書」(開業届)を提出することから、この言葉が定着したと言われています。医師や弁護士などの専門職が独立する際にも「開業」という言葉がよく使われますね。
独立とは
「独立」は「他からの束縛や支配を受けず、自分の意志で行動できること」を意味します。会社を退職して独り立ちするような場合が「独立」にあたります。他の言葉が「事業を始める」という意味を含むのに対し、独立はそこまでの意味は持っていません。
まとめ:正しい言葉の使い分けでビジネスをスッキリ進めよう
いかがでしたか?創業・創立・設立の違いについて理解できましたか?
- 創業は「事業を始めること」
- 創立は「組織や機関を立ち上げて事業を開始すること」
- 設立は「商業・法人を登記すること」
この違いを押さえておくと、ビジネスシーンでの会話や書類作成がスムーズになりますよ。特に設立日は税金にも関わる重要なポイントなので、しっかり理解しておきましょう!
ビジネスの世界では言葉の使い方一つで印象が変わることもあります。正確な知識を身につけて、自信を持ってコミュニケーションを取りましょう!
本日の名言として、こちらをご紹介します。
「知識があれば、道は開ける」- ベンジャミン・フランクリン
知識は力です。今日学んだことが、皆さんのビジネスライフに役立つことを願っています。それでは、また次回のミーミルメディアでお会いしましょう!