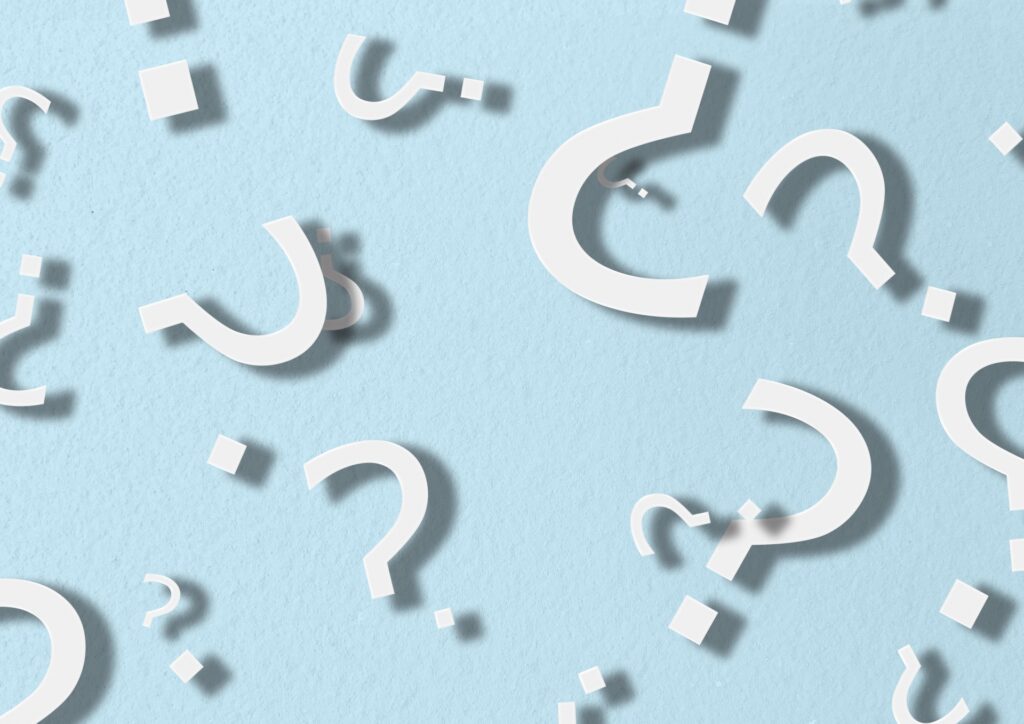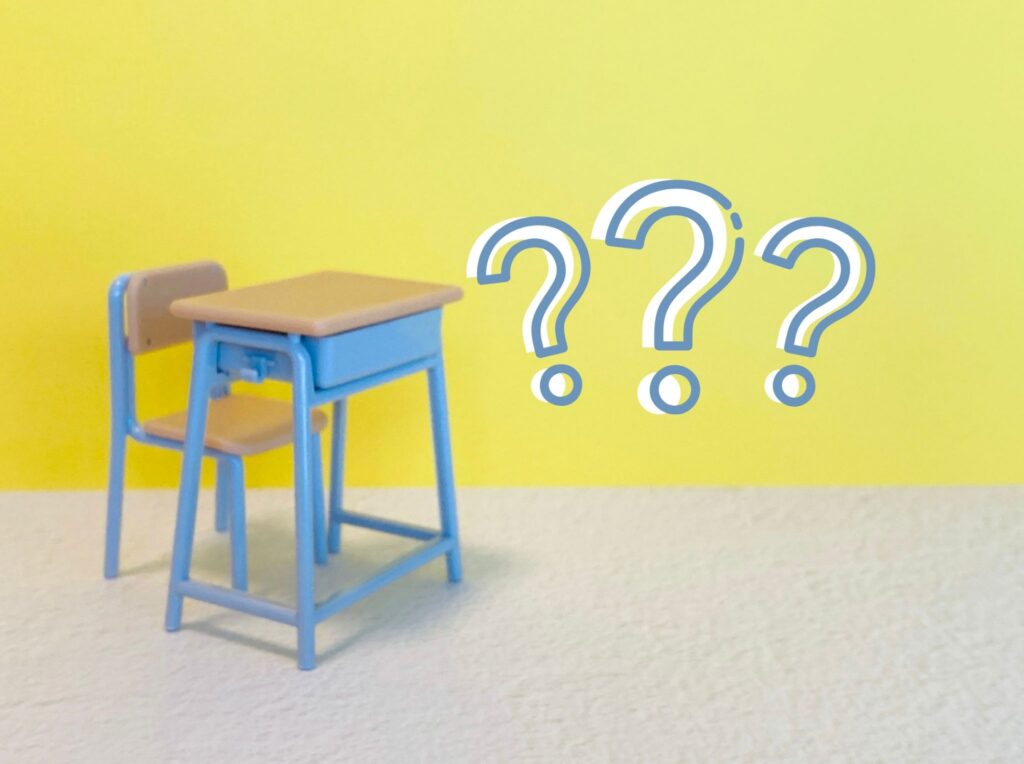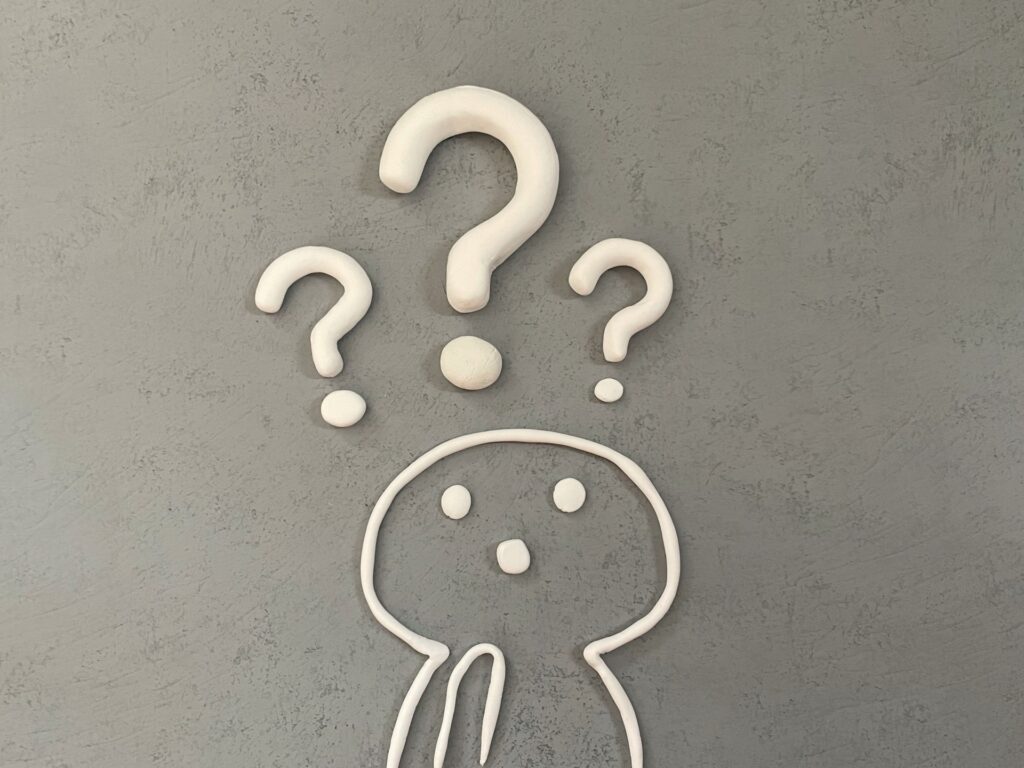こんにちは、皆さん!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日は選挙の季節になると必ず耳にする「公示」と「告示」の違いについてお話しします。この二つの言葉、なんとなく同じような意味に聞こえますが、実は明確な使い分けがあるんです。ボクも最近まで曖昧に理解していたので、しっかり調べてみました!
公示と告示の基本的な意味
まず基本的なところから整理しましょう。「公示」も「告示」も、行政機関などが一定の事項を広く一般に知らせる行為を指します。どちらも似たような意味合いを持っていますが、使われる場面や根拠が異なるんです。
公示(こうじ)とは
公示は「公の機関が広く一般に示すこと」を意味します。特に選挙においては、天皇の国事行為を伴う選挙の際に使われる用語なんです。
告示(こくじ)とは
一方、告示は「国家・地方公共団体などが広く一般に向けて行う通知」を指します。行政機関が法令や条例、規則に基づいて公示する場合に使われる言葉です。
選挙における公示と告示の使い分け
選挙の文脈では、この二つの言葉はとても明確に使い分けられています。その根拠は、なんと日本国憲法にあるんです!
公示が使われる選挙
日本国憲法第7条では、天皇の国事行為として「国会議員の総選挙の施行を公示すること」と定められています。つまり、天皇の国事行為を伴う以下の選挙では「公示」が使われます:
- 衆議院議員の総選挙
- 参議院議員の通常選挙
これらの選挙では、官報に天皇の詔書が掲載されるという特別な手続きが行われます。
告示が使われる選挙
一方、天皇の国事行為を伴わない以下の選挙では「告示」が使われます:
- 衆議院・参議院の補欠選挙や再選挙
- 都道府県知事選挙
- 都道府県議会議員選挙
- 市区町村長選挙
- 市区町村議会議員選挙
これらの選挙では、当該選挙の事務を管理する選挙管理委員会が官報や公報に掲載する方法で告示を行います。
公示日と告示日の意味
「公示日」や「告示日」という言葉もよく耳にしますよね。これらは選挙において、選挙が行われることを正式に知らせる日のことを指します。この日には立候補の届出が行われ、各候補者は選挙運動を開始します。
公職選挙法では、衆議院の総選挙の期日は「少なくとも12日前」に、参議院の通常選挙の期日は「少なくとも17日前」に公示することが決められています。
公示と告示の法的な重要性
公示や告示は単なる形式ではなく、法的に重要な意味を持っています。例えば、法令等が告示すべき旨を定めているのは、その事項が一般市民の利害に関係するため広く周知させることで、公正な行政を担保しようとするものです。法令等が告示すべき旨を規定しているにもかかわらず、これを行わずにした行為は、無効となる場合もあるんです。
入札における公示と告示
選挙以外の場面、例えば入札においても「公示」と「告示」は使い分けられています。
- 入札公告:一般競争入札を告知すること
- 入札公示:公募型指名競争入札や公募型競争入札(プロポーザル)の実施を知らせる際に使用
このように、法律に基づく一般競争入札の告知を表す記述である「公告」と区別するため、入札「公示」という表現が使われているんですね。
まとめ
「公示」と「告示」の違いをまとめると:
- 公示は天皇の国事行為を伴う選挙(衆議院総選挙・参議院通常選挙)で使用
- 告示はそれ以外の選挙で使用
- 公示は日本国憲法に根拠がある
- 告示は公職選挙法に基づいて選挙管理委員会が行う
ちょっとした言葉の違いですが、その背景には日本の憲法や選挙制度の仕組みが関わっているんですね。選挙報道を見るときに、この違いを知っておくと、より深く理解できるようになりますよ!
皆さんも次に「衆議院選挙の公示日は○月×日」とか「市長選挙の告示日は△月□日」というニュースを聞いたら、「あ、これは天皇の国事行為かどうかで使い分けているんだな」と思い出してくださいね!
「知識は力なり」 – フランシス・ベーコン
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!皆さんの毎日が知識と発見に満ちたものになりますように!