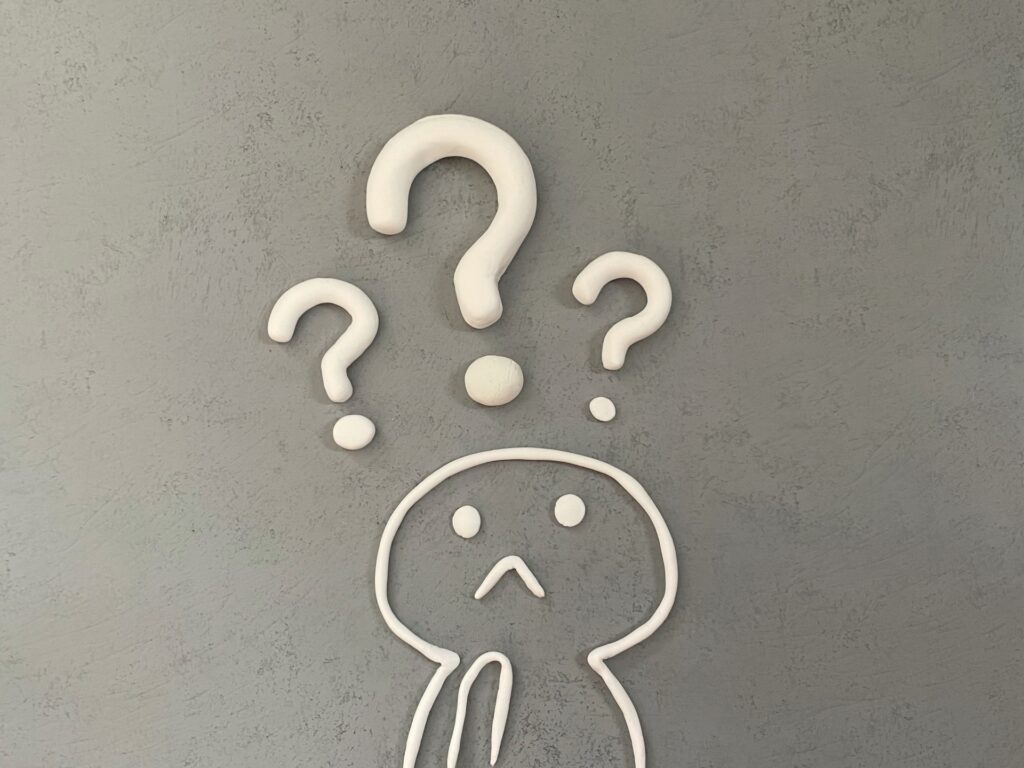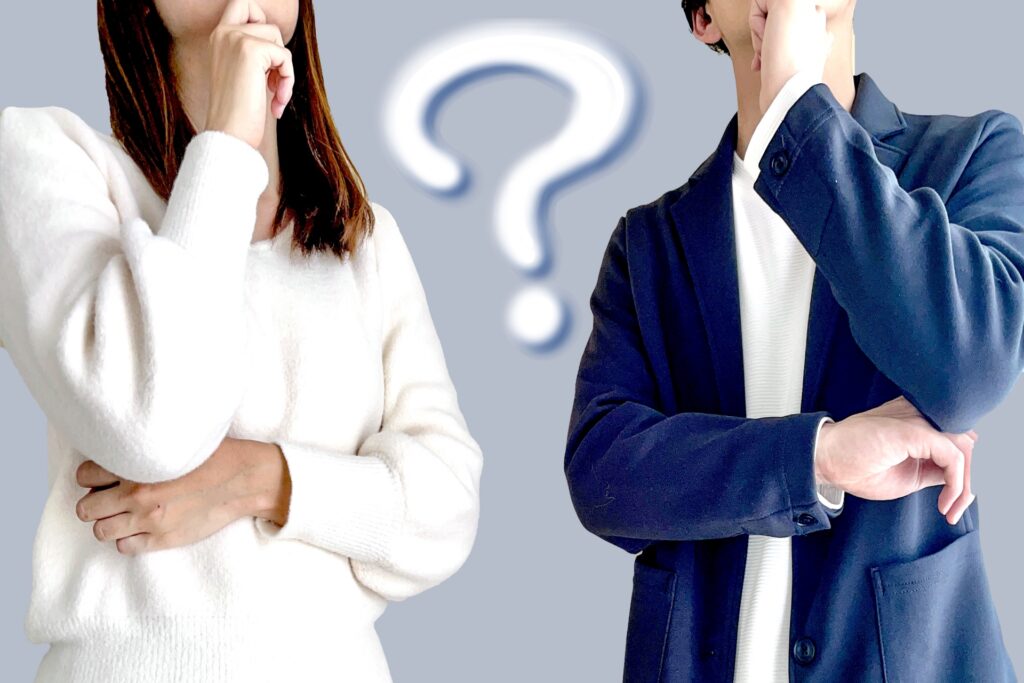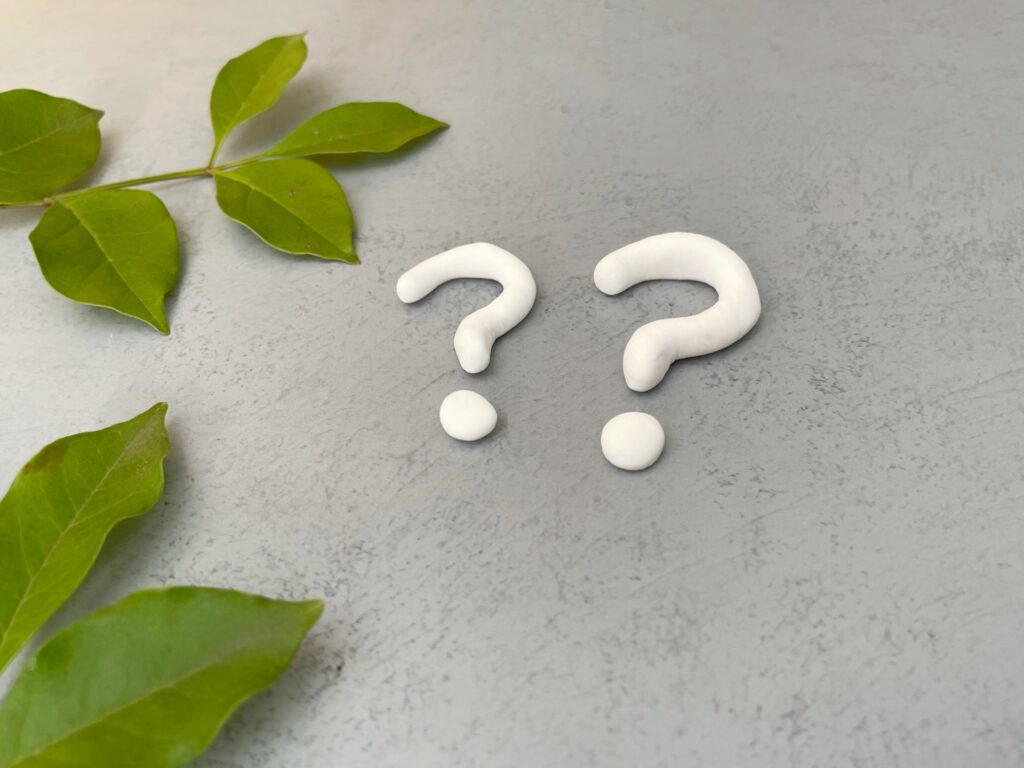こんにちは、皆さん!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日は首都圏で暮らす方なら誰もが一度は悩んだことがある「パスモとスイカの違い」について、じっくりとお話ししていきたいと思います。
「パスモ持ってるけど、スイカも必要?」「どっちがお得なの?」なんて疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?ボクも子どもたちの通学用にどちらを選ぶべきか、かなり悩んだ経験があります。そこで今回は、それぞれの特徴やメリット・デメリットをギュウギュウに詰め込んでご紹介します!
パスモとスイカの基本的な違い
まず最初に押さえておきたいのが、パスモとスイカの基本的な違いです。実は、この2つのカードの一番大きな違いは「発行元」なんです。
パスモ(PASMO)は株式会社パスモが発行しており、東急や京王、京急などの私鉄やバス会社が中心となっています。一方、スイカ(Suica)は東日本旅客鉄道(JR東日本)・東京モノレール・東京臨海高速鉄道が発行・販売しているんですね。
どちらも電子マネー機能つきのICカード乗車券ですが、それぞれ発行元と登録商標が異なっているというわけです。ちなみに、パスモという名前は、関東地域で使われていた磁気カード「パスネット」の「PAS」と、「もっと便利に」という意味の「MORE」の「MO」を組み合わせた造語なんだそうですよ!
相互利用はできるの?使えるエリアは?
「発行元が違うなら使えるエリアも違うの?」と心配される方もいるかもしれませんが、ご安心ください!パスモとスイカは相互利用が可能です。
パスモがあれば、首都圏をはじめ、交通系ICカードの「全国相互利用シンボルマーク」がついている全国の鉄道やバスで利用できます。スイカも同様に、首都圏だけでなく、「全国相互利用シンボルマーク」がついている全国の鉄道やバスで利用可能です。
ただし、相互利用する際にはいくつか注意点もあります。例えば、モバイルスイカをパスモ取扱事業者で利用する時、改札機以外での精算が必要になることがあります。また、異なるエリア間をまたぐ乗車の際には利用できないこともあるんですよ。
さらに、スイカは首都圏スイカ・パスモエリア、仙台エリア、新潟エリア以外ではオートチャージサービスを利用できないという制限もあります。払い戻しについても、スイカでは購入したICカード事業者のみでしか払いもどしできないので注意が必要です。
どっちを選ぶべき?選ぶポイント3つ
「結局どっちがいいの?」という疑問にお答えするために、選ぶポイントを3つご紹介します!
1. 定期券を購入する路線で選ぶ
通勤や通学で定期券を利用する予定がある方は、利用する路線の定期券を発行できるかどうかを確認しましょう。
パスモは「小田急電鉄」「京王電鉄」「東京メトロ」などの定期券を発行できます。一方、スイカは「JR東日本」の定期券を発行可能です。また、JR線単独定期券のほか、スイカエリア内からパスモエリア内までの連絡定期券も発売されています。
乗車券だけでなく定期券が買えるかどうかは、事前にしっかり確認しておくことをオススメします!
2. ポイント還元率で選ぶ
お買い物でポイントをためたい方は、よく利用する店舗でポイント還元率が良い方を選ぶと良いでしょう。
パスモは、東京メトロや東急、京王などの私鉄の乗車でポイントが貯まります。また、パスモ一体型のクレジットカードからのオートチャージや、提携する対象店舗での電子マネー利用でもポイント還元があります。パスモ一体型のクレジットカードには、「Tokyo Metro To Me CARD」や「京王パスポートPASMOカード」などがあります。
一方、スイカも鉄道の利用やJRE POINT加盟店での買い物、オートチャージなどで「JRE POINT」がたまります。JR東日本が中心となって発行しているので、新幹線の利用や、「えきねっと」経由で予約した列車付きの国内旅行・ツアー、レンタカーでもポイントがつきます。スイカ一体型のクレジットカードには、「ビュー・スイカ カード」「ビックカメラSuicaカード」などがあります。
3. オートチャージ上限額で選ぶ
パスモとスイカでは、1日あたりのオートチャージ上限額が異なります。
パスモのオートチャージ上限額は1日あたり10,000円、1ヶ月あたり50,000円となっています。一方、スイカのオートチャージ上限額は1日あたり20,000円で、1ヶ月あたりの上限額は特に記載がありません。
どちらも残額が20,000円を超えるチャージはできませんが、1日あたりのチャージ上限額が違うので、利用予定額に合わせて選ぶと良いでしょう!
パスモとスイカの比較表
ここで、パスモとスイカの違いを表にまとめてみました。
| 項目 | パスモ(PASMO) | スイカ(Suica) |
|---|---|---|
| 発行元 | 株式会社パスモ | JR東日本 |
| 主な利用路線 | 私鉄、地下鉄、バス | JR線 |
| オートチャージ上限 | 1日10,000円、月50,000円 | 1日20,000円、月の上限なし |
| ポイントサービス | PASMOポイントサービス | JRE POINT |
| 払い戻し手数料 | 無料 | 有料 |
パスモとスイカはどっちがおすすめ?
結局のところ、パスモとスイカのどちらがおすすめかは、皆さんの生活スタイルによって変わってきます。
JR線をよく利用する方なら、スイカの方が便利でしょう。特に、新幹線や特急列車をよく利用する方は、JRE POINTが貯まるスイカがお得です。
一方、私鉄や地下鉄、バスをよく利用する方は、パスモの方が便利かもしれません。特に、東京メトロや東急線などをよく利用する方は、各社のポイントサービスが利用できるパスモがおすすめです。
また、払い戻しの手数料が気になる方は、払い戻し手数料が無料のパスモの方が良いでしょう。スイカは一度入金すると払い戻し時に手数料がかかります。
ボクの場合は、家族でJR線と私鉄の両方を使うことが多いので、実は両方持っています。子どもたちには通学路線に合わせて選んであげました。息子はJR線で通学しているのでスイカ、娘は私鉄で通学しているのでパスモを持っていますよ!
まとめ:あなたに合った交通系ICカードを選ぼう
パスモとスイカの違いについて、いかがでしたか?ここで改めて重要ポイントをおさらいしましょう。
・パスモとスイカは発行元が異なる
・基本的な機能は同じで相互利用も可能
・定期券を購入する路線、ポイント還元率、オートチャージ上限額で選ぶと良い
・よく利用する路線や店舗に合わせて選ぶのがおすすめ
どちらも便利な交通系ICカードですが、自分のライフスタイルに合わせて選ぶことで、より快適な生活を送ることができますよ!
最後に、今日の名言をご紹介します。
「人生は選択の連続である。選択を恐れず、自分に合った道を選ぶことが大切だ。」 – スティーブ・ジョブズ
皆さんも、自分に合った交通系ICカードを選んで、スッキリとした毎日を過ごしてくださいね!それでは、また次回のミーミルメディアでお会いしましょう!