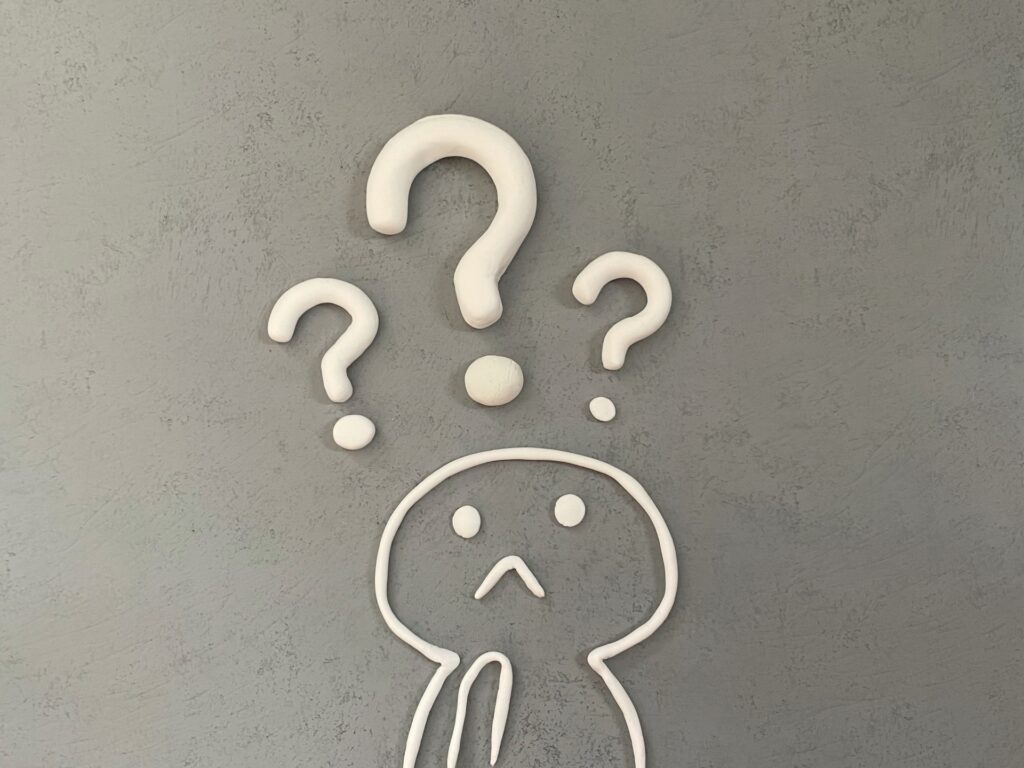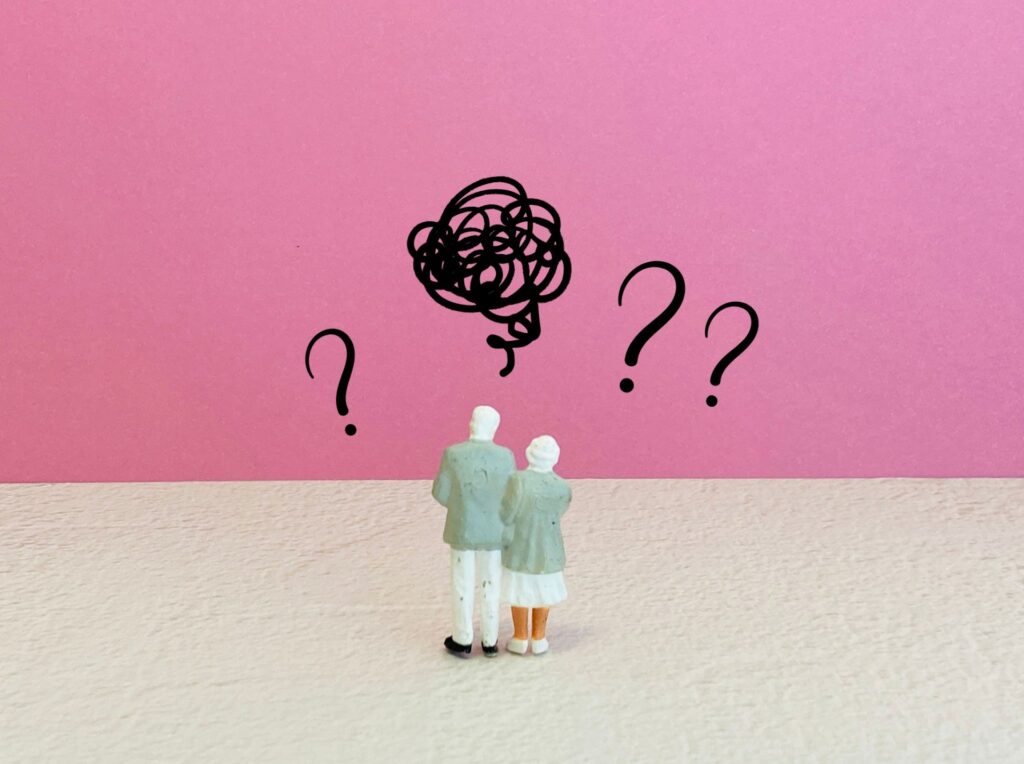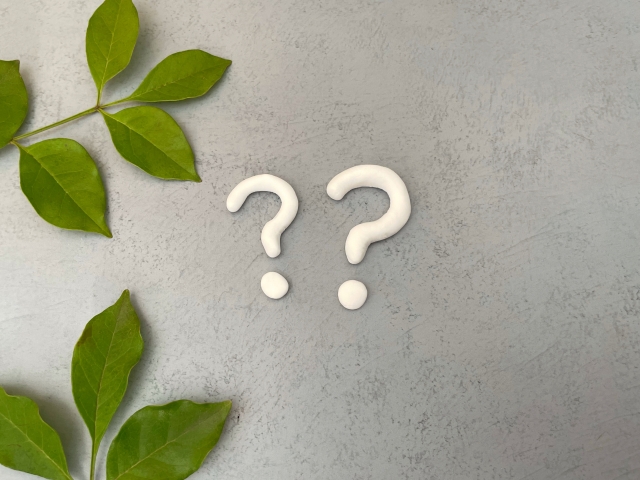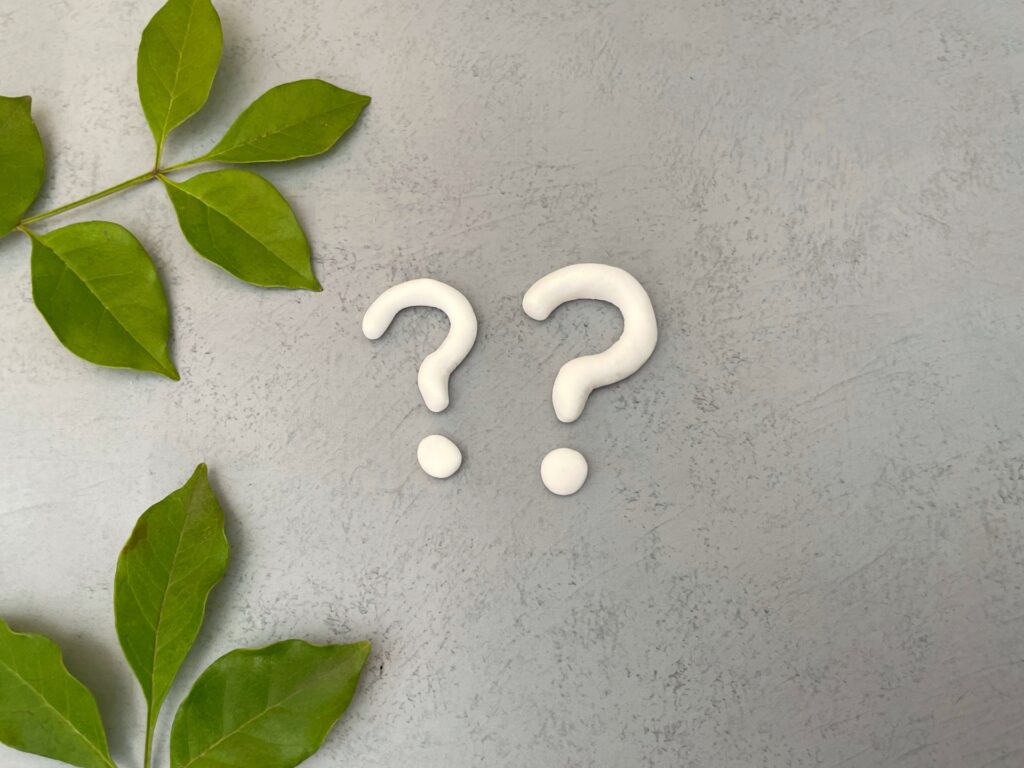こんにちは!ミーミルメディア編集長のしげっちです。春のお彼岸が近づくと、和菓子屋さんやスーパーの和菓子コーナーに並ぶ「牡丹餅」や「おはぎ」。「あれ?この二つって何が違うんだっけ?」と思ったことはありませんか?ボクも子どもたちに聞かれて「えーっと」と答えに詰まったことがあります。今日はそんな素朴な疑問をスッキリ解決していきましょう!
牡丹餅とおはぎの違いは季節にあり!
実は牡丹餅とおはぎ、見た目はそっくりなのに、食べる季節で呼び名が変わるんです。
春のお彼岸に食べるのが「牡丹餅(ぼたもち)」で、秋のお彼岸に食べるのが「おはぎ」なんです。これは、それぞれの季節に咲く花に由来しているんですよ。
春に咲く牡丹の花にちなんで「牡丹餅」、秋に咲く萩の花にちなんで「おはぎ」と呼ばれるようになったんです。江戸時代の文献「倭漢三才図会」には「牡丹餅および萩の花は形、色をもってこれを名づく」と記されているそうで、その名前の由来がハッキリしています。
あんこの種類も季節で違う?
「こしあんがおはぎで、粒あんが牡丹餅?」なんて思っている方も多いかもしれませんが、実はこれも季節が関係しているんです!
春の牡丹餅はこしあん、秋のおはぎは粒あんが基本なんです。
これには小豆の収穫時期が関係しています。小豆は秋に収穫されるので、秋のお彼岸では新鮮な小豆が手に入ります。新鮮な小豆は皮も柔らかいので、皮ごと使った粒あんにするのがピッタリ。
一方、春のお彼岸では冬を越した小豆を使うことになります。時間が経って皮が固くなった小豆は、皮を取り除いてこしあんにした方が食べやすいんです。なるほど!先人の知恵ですね!
形にも違いがあるって本当?
牡丹餅とおはぎは形にも違いがあるんですよ。
牡丹餅は、豪華な大輪の花を咲かせる牡丹をイメージして、丸く大きめに作るのが一般的。
一方、おはぎは萩の細長い花びらをイメージして、少し小ぶりで俵形に作ることが多いんです。
ただ、最近ではこの区別もあいまいになってきていて、年中「おはぎ」の名前で販売されているお店が多いようです。
夏と冬にも別の呼び名があった!?
実は春の「牡丹餅」、秋の「おはぎ」だけでなく、夏と冬にも別の呼び名があったんです!これはちょっとマニアックな知識かもしれませんね。
夏は「夜船(よふね)」、冬は「北窓(きたまど)」と呼ばれていたそうです。
「夜船」は、おはぎを作る時に餅をつく音が静かで、まるで夜の船がいつの間にか岸に着いたかのように気づかないことから名付けられたとか。
「北窓」は、北向きの窓からは月が見えないことから「月知らず」となり、それが「北窓」になったという説があります。
日本人って季節感を大切にする民族だなぁとしみじみ感じますね。一つの和菓子に四季折々の名前をつけるなんて、風情があって素敵じゃないですか?
今でも季節で使い分けるべき?
昔は厳密に季節で呼び分けていたようですが、現代では保存技術の発達や品種改良により、一年中どちらの呼び名でも通じるようになっています。
でも、日本の伝統や季節感を大切にするなら、春のお彼岸には「牡丹餅」、秋のお彼岸には「おはぎ」と呼び分けるのも素敵なことですよね。ボクの子どもたちにも、こういった日本の文化や季節感を伝えていきたいなと思います。
皆さんも次のお彼岸には、ぜひ季節に合わせた呼び名で家族と一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか?ちなみに今年の春のお彼岸は3月17日〜23日ですので、もうすぐ牡丹餅の季節がやってきますよ!
本日の名言:
「四季のある日本に生まれたことを誇りに思う。」 – 松尾芭蕉
季節の移り変わりを感じながら、日本の伝統文化を大切にしていきましょう!それでは、また次回の記事でお会いしましょう!