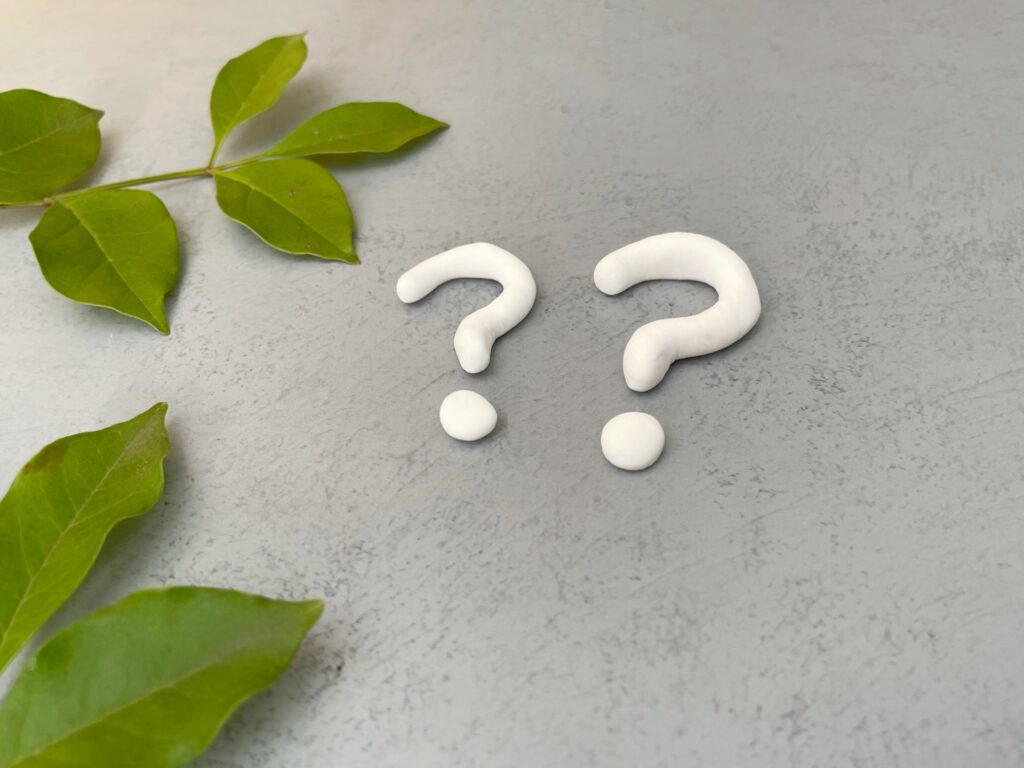こんにちは!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日は皆さんにとって身近なお茶について、ちょっと掘り下げてみたいと思います。
「煎茶」と「緑茶」、この二つの言葉、よく耳にしますよね。でも、実はこの二つの違いをハッキリと説明できる人って意外と少ないんです。ボクも最近まで「同じものでしょ?」なんて思っていました(笑)。子どもたちに聞かれて答えられず、ちょっと恥ずかしい思いをしたのがきっかけで調べてみたんですよ。
緑茶と煎茶の基本的な関係
まず最初に、結論から言っちゃいましょう!煎茶は緑茶の一種です。つまり、緑茶というのは大きなカテゴリーで、その中に煎茶や玉露、かぶせ茶などが含まれているんです。
緑茶とは何かというと、簡単に言えば「発酵させずに作るお茶」のこと。お茶の葉を摘んだ後、すぐに蒸したり炒ったりして酸化酵素の働きを止めるので、茶葉の色が緑色のまま保たれます。だから「緑茶」と呼ばれるわけですね。
一方、紅茶は茶葉をしっかり発酵させたもの、ウーロン茶は半分ほど発酵させたものです。プーアール茶のような後発酵茶もあります。お茶の世界、奥が深いですね~!
煎茶の特徴とは?
煎茶は日本で最も多く生産され、私たちが普段飲んでいる一般的なお茶です。煎茶の特徴は、茶葉が太陽の光をたっぷり浴びて育てられること。光合成によって旨味成分のテアニンが渋み成分のカテキンに変化するため、程よい渋みと爽やかな味わいが特徴なんです。
製造過程では、摘んだ茶葉をまず蒸して酸化を止め、その後、揉んで乾燥させていきます。この「蒸し」の時間によっても味が変わってくるんですよ。通常の煎茶は30~40秒ほど蒸しますが、60~120秒ほど長く蒸したものは「深蒸し煎茶」と呼ばれます。深蒸し煎茶は茶葉が細かくなり、お茶の色が濃く、味も濃くなるという特徴があります。
煎茶の美味しい淹れ方
せっかくなので、美味しい煎茶の淹れ方もご紹介しましょう!
2人分のお茶を淹れる場合、茶葉は4g、お湯は200mlほど用意します。ここで大事なのはお湯の温度!70℃くらいがベストなんです。
沸騰したお湯をそのまま使うのではなく、一度湯飲みに移し、さらに湯冷ましに移すことで温度を下げます。器を変えるごとに約10度温度が下がると言われていますよ。お湯の温度を下げることで、煎茶の旨味がより引き立ちます。
お湯を注いだら蓋を閉めて30秒ほど待ちましょう。一煎目を楽しんだ後は、二煎目も楽しめます。二煎目は熱いお湯をそのまま注いでOK!一煎目と二煎目の味の違いを楽しむのもオススメです♪
緑茶の種類とそれぞれの特徴
緑茶には煎茶以外にもいろいろな種類があります。それぞれの特徴を見ていきましょう。
玉露の特徴
玉露は緑茶の中でも高級なお茶として知られています。煎茶との大きな違いは栽培方法にあります。収穫の約3週間前から茶園に覆いをかけて日光を遮ります。
日光を遮ることで何が起こるかというと、旨味成分のテアニンが増加し、渋み成分のカテキンへの変化が抑えられるんです。結果として、渋みが少なく、旨味と甘みが豊かな味わいになります。
玉露は40~60℃という低めの温度でじっくり淹れるのがポイント!これは玉露特有の旨味をしっかり引き出すためなんですよ。
かぶせ茶について
かぶせ茶は玉露と同様に日光を遮って育てますが、遮光期間が玉露より短いのが特徴です。味わいは煎茶と玉露の中間といった感じで、程よい旨味と渋みを楽しめます。
番茶とは
番茶の定義は地域によって異なりますが、一般的には一番茶や二番茶の後に摘まれた茶葉で作られるお茶を指します。静岡では三番茶や四番茶が番茶になります。
番茶は煎茶に比べて葉が大きくて硬め。カテキン、テアニン、カフェインの含有量が煎茶より少ないため、すっきりとした味わいが特徴です。
地域によっては独特の製法で作られる番茶もあります。京都の「京番茶」は茶葉を乾燥させて炒るため、スモーキーな香りと味わいが楽しめます。
煎茶の歴史
現在私たちが飲んでいるような緑色の煎茶は、1738年に京都・宇治田原の農家、永谷宗円によって生み出されたと言われています。それまでの煎茶は茶色で粗末なものでしたが、永谷宗円が考案した「青製煎茶製法」によって、鮮やかな緑色で味と香りに優れた高品質の煎茶が誕生したんです。
この煎茶は江戸や近畿を中心に全国に広まり、煎茶の主流となりました。永谷宗円は「煎茶の祖」とも呼ばれています。ちなみに、お茶漬けでおなじみの「永谷園」の創業者は、この永谷宗円の子孫なんですよ!歴史的なつながりを感じますね。
まとめ:煎茶と緑茶の違い
さて、ここまで煎茶と緑茶について見てきましたが、整理しておきましょう。
緑茶は発酵させずに作るお茶の総称で、煎茶はその緑茶の一種です。緑茶には煎茶の他に、玉露、かぶせ茶、番茶、ほうじ茶、抹茶の原料となるてん茶などが含まれます。
煎茶は太陽の光をしっかり浴びて育てられ、程よい渋みと爽やかな味わいが特徴です。一方、玉露は日光を遮って育てられるため、旨味と甘みが豊かです。
ぜひ機会があれば、煎茶、玉露、番茶などを飲み比べてみてください。それぞれの個性の違いがより分かりやすくなりますよ!
皆さんのお茶ライフがもっと豊かになりますように。今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
「知識とは、自分が何かを知らないということを知ることから始まる」
– ソクラテス
今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように!