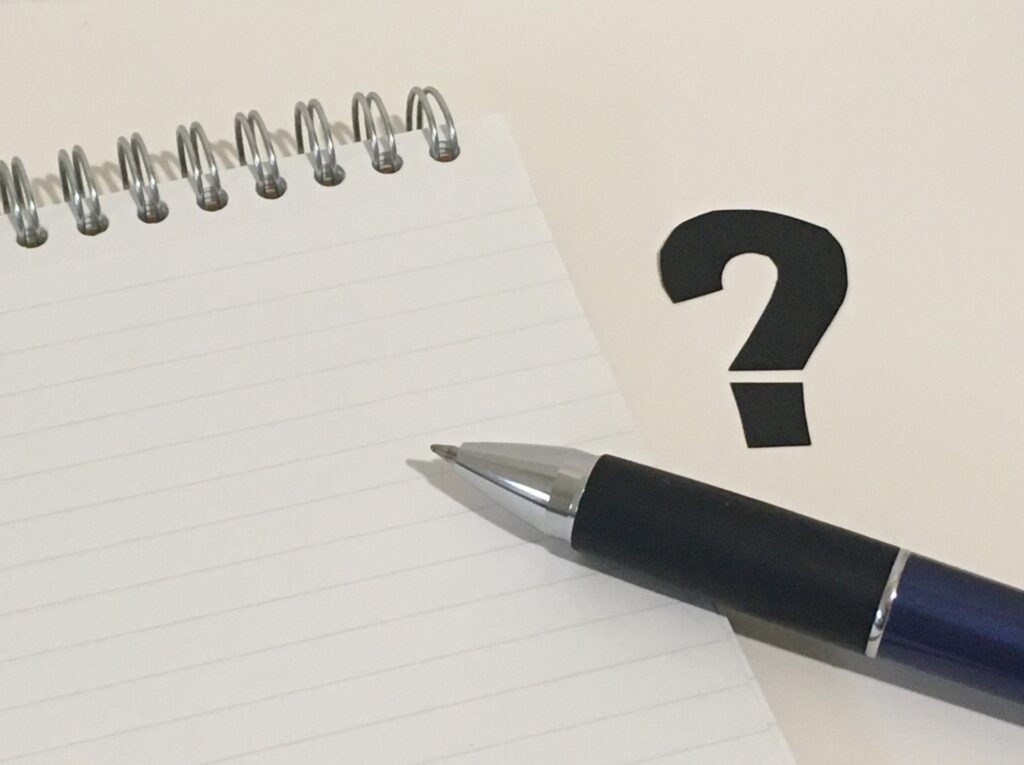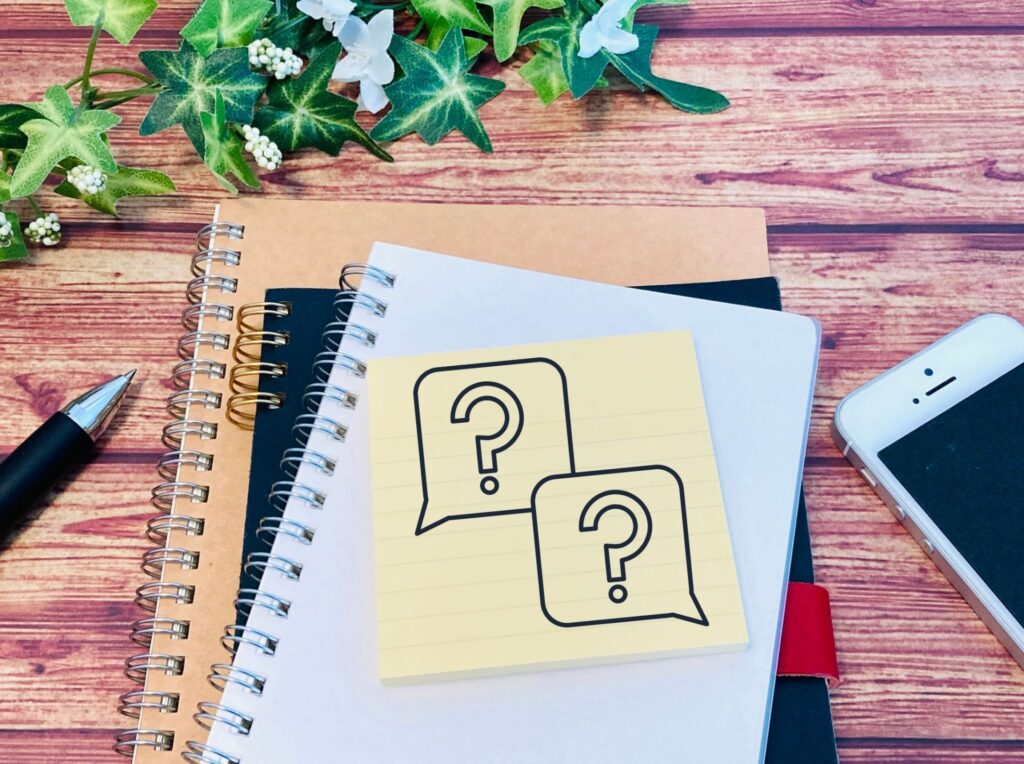こんにちは!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日は春から秋にかけて突然降ってくることがある「あられ」と「ひょう」について、その違いをスッキリ解説していきますね。
皆さんは「あられが降ってきた!」と「ひょうが降ってきた!」の違いがハッキリわかりますか?どちらも空から降ってくる氷の粒ですが、実は明確な区別があるんです。気になったので、ボクなりに調べてみました!
あられとひょうの決定的な違いは「大きさ」
あられとひょうの違いは、ズバリ「大きさ」です!気象庁の定義によると、直径5mm未満の氷の粒が「あられ」、直径5mm以上の氷の塊を「ひょう」と呼びます。
つまり、同じ氷の粒でも、5mmという境界線で呼び名が変わるんですね。子どもたちに説明するときは「えんぴつの芯くらいの大きさが境目だよ」と教えると、イメージしやすいかもしれませんね。
あられとひょうはどうやってできるの?
どちらも空から降ってくる氷の粒ですが、できる過程も知っておくと面白いですよ。あられもひょうも、発達した「積乱雲」という雲の中で作られます。
最初は小さな氷の結晶なんですが、積乱雲の中にある強い上昇気流と下降気流によって上下運動を繰り返します。その過程で雲の中の細かい水や氷の粒がくっついて、どんどん大きくなっていくんです。
ある程度の大きさになると、上昇気流よりも落ちる速度の方が大きくなって、そのまま地表に降り落ちてきます。この時、直径が5mm未満だと「あられ」、5mm以上だと「ひょう」になるというわけです。
降る季節も違う!あられとひょうの特徴
実は、あられとひょうは降る季節も異なります。俳句の世界では、あられは冬の季語、ひょうは夏の季語として使われているんですよ。
あられは冬に降ることが多く、雪と一緒に降ったり、雪があられに変わることもあります。一方、ひょうが降りやすいのは春から秋にかけて。特に5月〜6月は地上の気温が暖かくても上空に冷たい寒気が入る「大気の不安定」な状態になりやすく、ひょうが降りやすい時期なんです。
あられの種類いろいろ
あられにも実はいくつか種類があります。気象庁では以下のように区別しています。
・雪あられ:白い不透明な氷の粒で、固い地面に当たると弾んで割れることも
・氷あられ:半透明な氷の粒で、固い地面に当たると弾むが簡単につぶれない
・凍雨(とうう):透明な氷の粒で、直径は5mm未満
・霧雪(きりゆき):直径1mm未満の白く不透明な氷の粒
あられとひょうの危険性
大きさが違うだけでなく、危険性も異なります。ひょうは大きいほど落下速度も速くなり、直径50mm(5cm)ともなると、落下速度はなんと時速100kmを超えるんです!車が破損したり、人が怪我をしたりする危険性があります。
1917年には埼玉県熊谷付近でカボチャ大(重さ3.4kg)のひょうが降った記録もあるそうで、ビックリですね。気象庁では、ひょうによる被害を「ひょう害」と呼んでいます。
あられは小さいから安全かというと、そうとも言い切れません。地面に積もると非常に滑りやすくなります。ビー玉やパチンコ玉の上を歩くようなものなので、転倒に注意が必要です。
あられやひょうへの備え
あられやひょうは雷と一緒に発生することが多いです。天気予報で「雷注意報」が出ていたり、「大気の状態が不安定」「上空に強い寒気が」といった言葉が出てきたりしたときは、あられやひょうにも注意が必要です。
特に5月〜6月は注意しましょう。外出中に降ってきたら、安全な場所に避難するのが一番です。車を運転中なら無理に移動せず、安全な場所で収まるのを待ちましょう。
子どもたちにも「ひょうが降ってきたら、頭を守って建物の中に入るんだよ」と教えておくと安心ですね。
まとめ:あられとひょうの違い
あられとひょうの違いをおさらいしましょう。
・大きさ:あられは直径5mm未満、ひょうは直径5mm以上
・季節:あられは主に冬、ひょうは春から秋(特に5〜6月)
・危険性:ひょうは大きいほど被害が大きく、あられは積もると滑りやすい
・生成過程:どちらも積乱雲の中で作られるが、ひょうはより大きく成長したもの
天気の知識って、日常生活に役立つことが多いですよね。皆さんも空から氷の粒が降ってきたら、その大きさをチェックしてみてください。5mmを超えていたら「おっ、これはひょうだな!」と、ちょっと得した気分になれるかもしれませんね♪
「自然は常に私たちに謙虚さを教えてくれる」 ― レイチェル・カーソン
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!皆さんの毎日が晴れやかでありますように!