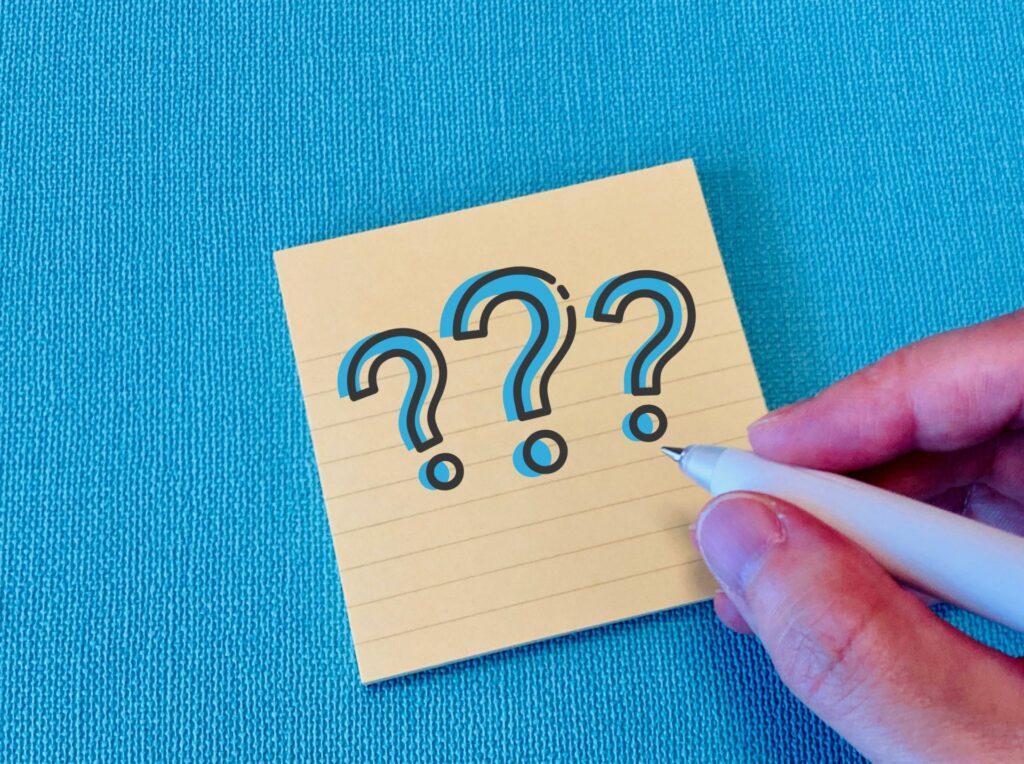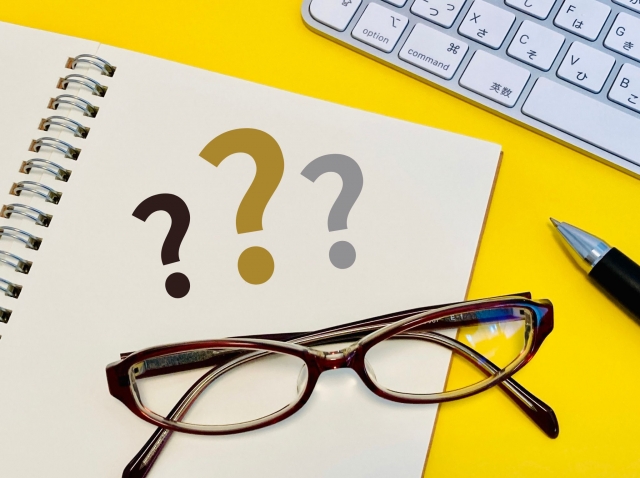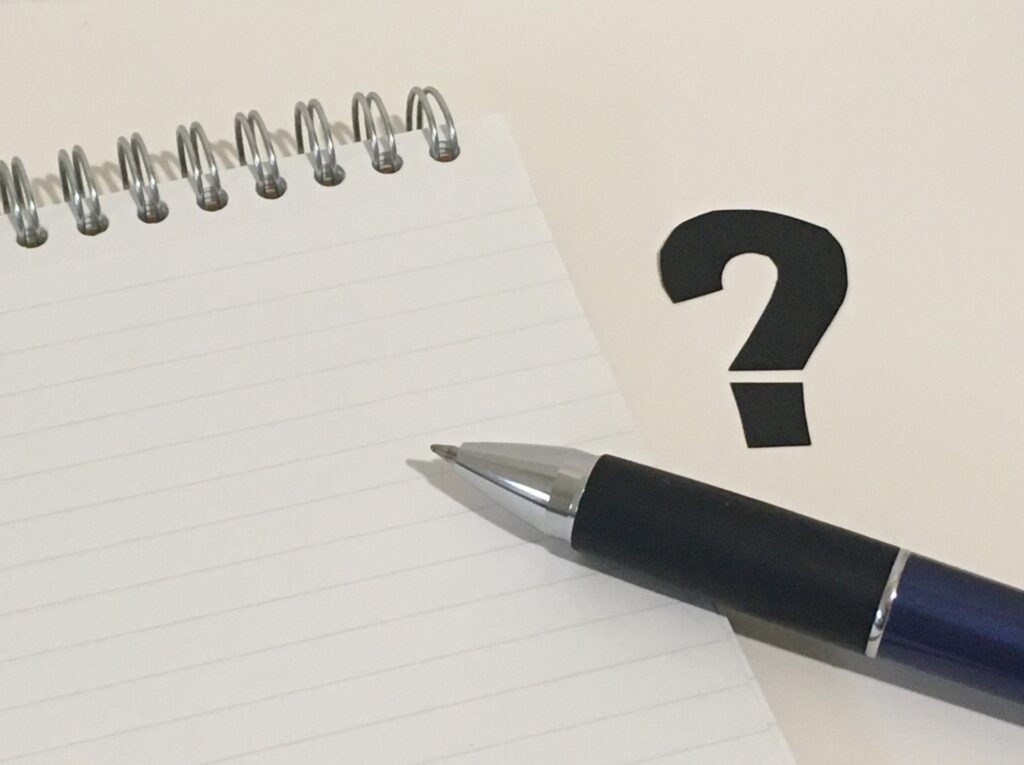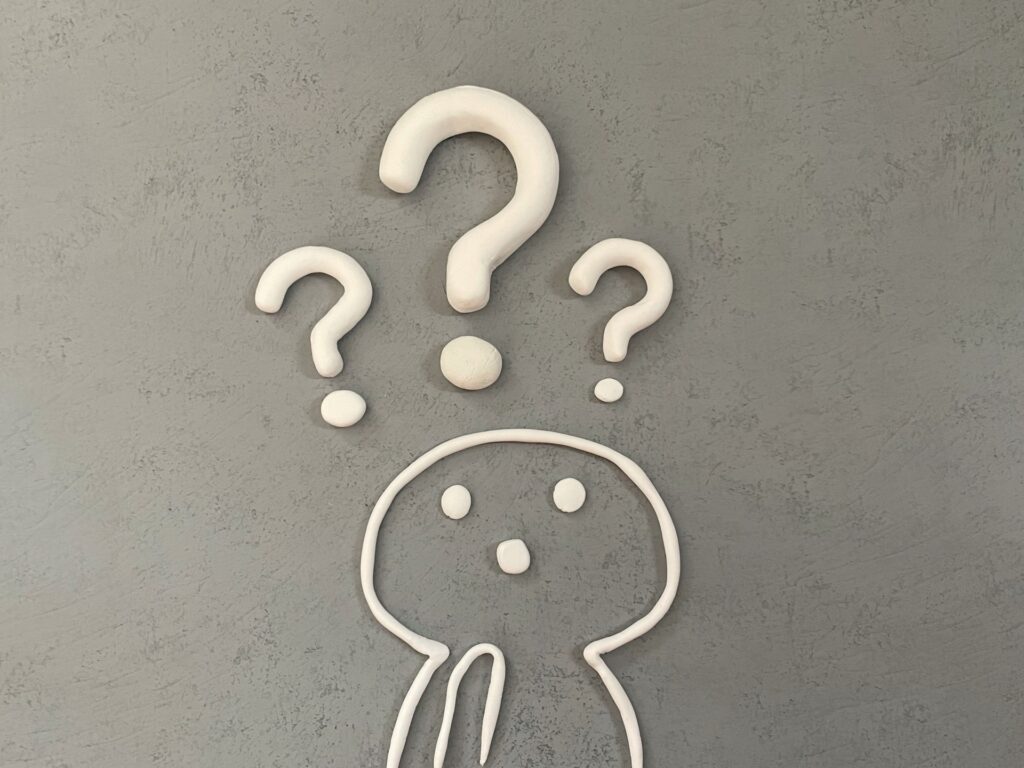みなさん、こんにちは!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日は、ちょっと難しそうだけど実はとっても大切な話題、「配偶者控除と配偶者特別控除の違い」について、ギュウギュウに詰め込んでお話ししちゃいます!
税金の話って、なんだかムズカシイ印象がありますよね。でも、ちょっと知識をつけるだけで、家計にスッキリとした余裕が生まれるかもしれないんです。そう考えると、ワクワクしてきませんか?
配偶者控除と配偶者特別控除、どう違うの?
まずは、この2つの控除の基本的な違いをおさえておきましょう。
対象となる配偶者の所得金額が違う!
配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入なら103万円以下)の場合に適用されます。一方、配偶者特別控除は、配偶者の年間の合計所得金額が48万円を超えて133万円以下(給与収入なら103万円超201万6,000円未満)の場合に適用されるんです。
つまり、配偶者の収入が増えても、一定の範囲内なら控除を受けられる可能性があるということ。これ、結構重要なポイントですよね!
控除額にも違いがあるんです
控除額も両者で異なります。配偶者控除の場合、最大で38万円、最小で13万円の控除を受けられます。配偶者特別控除は最大38万円、最小1万円となっています。
ただし、注意したいのは、納税者本人の所得金額によっても控除額が変わってくるということ。本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、どちらの控除も受けられなくなってしまいます。
配偶者控除・配偶者特別控除を受けるための条件
さて、これらの控除を受けるための条件をもう少し詳しく見ていきましょう。
共通の条件
まず、両方の控除に共通する条件があります。
納税者本人の年間の合計所得金額が1,000万円以下であること
配偶者が民法上の配偶者であること(内縁関係は対象外)
配偶者と生計を一にしていること
配偶者が青色申告または白色申告の事業専従者でないこと
これらの条件を満たした上で、先ほど説明した所得金額の範囲に入っているかどうかで、どちらの控除が適用されるかが決まるんです。
配偶者控除・配偶者特別控除のメリット
「へぇ〜、なるほど」と思っていただけましたか? でも、まだ「そもそもこの控除って何のためにあるの?」って疑問が湧いてきた方もいるかもしれませんね。
実は、これらの控除には大きなメリットがあるんです。課税所得額から控除額を差し引くことで、納付すべき所得税が低くなる可能性があるんです。つまり、税金の負担が軽くなるかもしれないということ!
特に、配偶者の収入が103万円を超えると社会保険料の負担が増えるため、収入が増えても手取りが減ってしまう「103万円の壁」と呼ばれる問題がありました。でも、配偶者特別控除のおかげで、その壁を越えても一定の控除が受けられるようになったんです。これって、働く配偶者にとってはうれしいことですよね!
年末調整での注意点
さて、これらの控除を受けるためには、年末調整の際に「給与所得者の配偶者控除等申告書」を勤務先に提出する必要があります。ここで気をつけたいのは、配偶者控除と配偶者特別控除は重複して適用できないということ。どちらか一方しか選べないんです。
また、配偶者の収入状況や自分の所得金額をしっかり把握しておくことも大切です。年の途中で状況が変わることもあるので、こまめにチェックする習慣をつけておくといいでしょう。
まとめ:家計のためにも、しっかり理解しよう!
いかがでしたか? 配偶者控除と配偶者特別控除、最初は難しそうに見えても、ポイントを押さえれば結構シンプルですよね。
ボクたち夫婦も、この制度のおかげで少し余裕ができた経験があります。皆さんも、ぜひこの知識を活用して、家計にゆとりを持たせてくださいね。
税金の話って、ちょっと面倒くさいと思いがちですが、実は私たちの生活に直結する大切な話なんです。「知らなかった」では済まされないこともあるので、少しずつでも理解を深めていくことが大切だと思います。
今日はここまで! 最後に、今日の名言を紹介して締めくくりましょう。
「知識というものは、それを求める熱意に比例して得られるものだ」 – アインシュタイン
税金の知識も同じですね。求める気持ちがあれば、きっと理解できるはずです。皆さん、一緒に頑張りましょう! それでは、また次回のミーミルメディアでお会いしましょう。元気で!