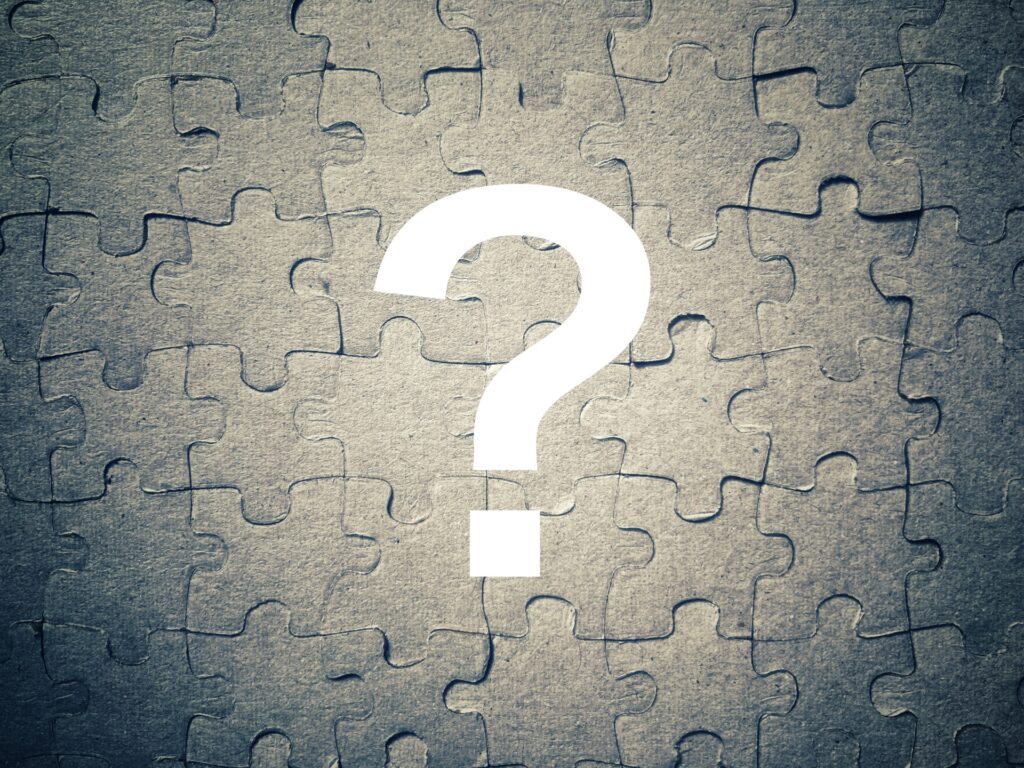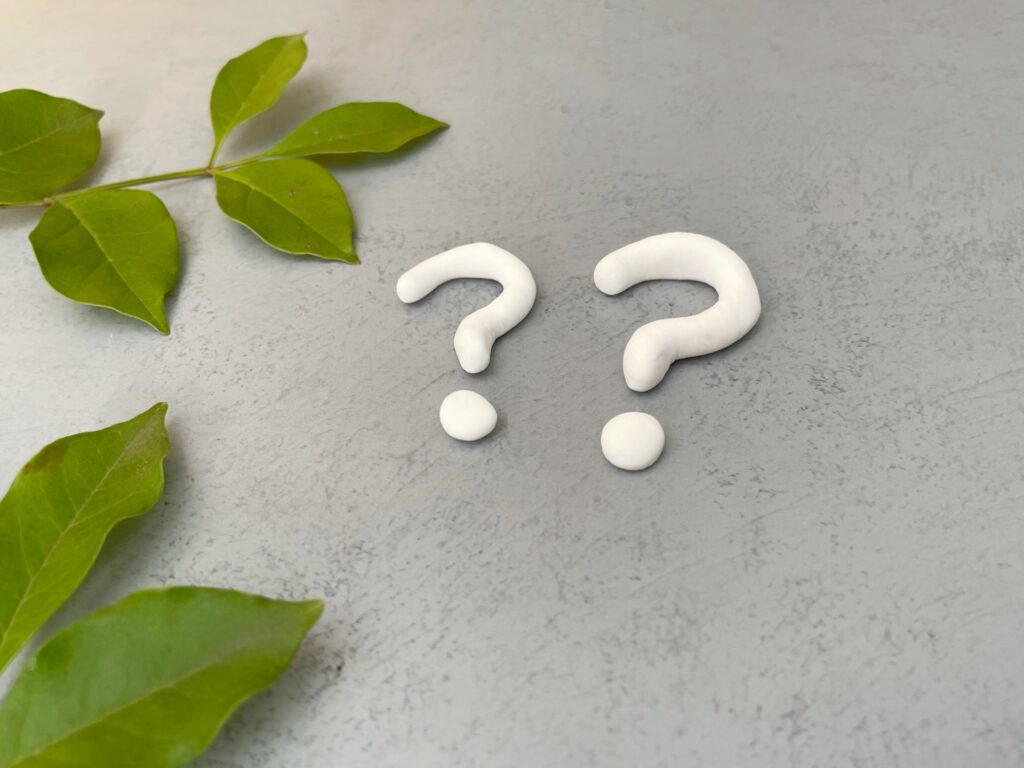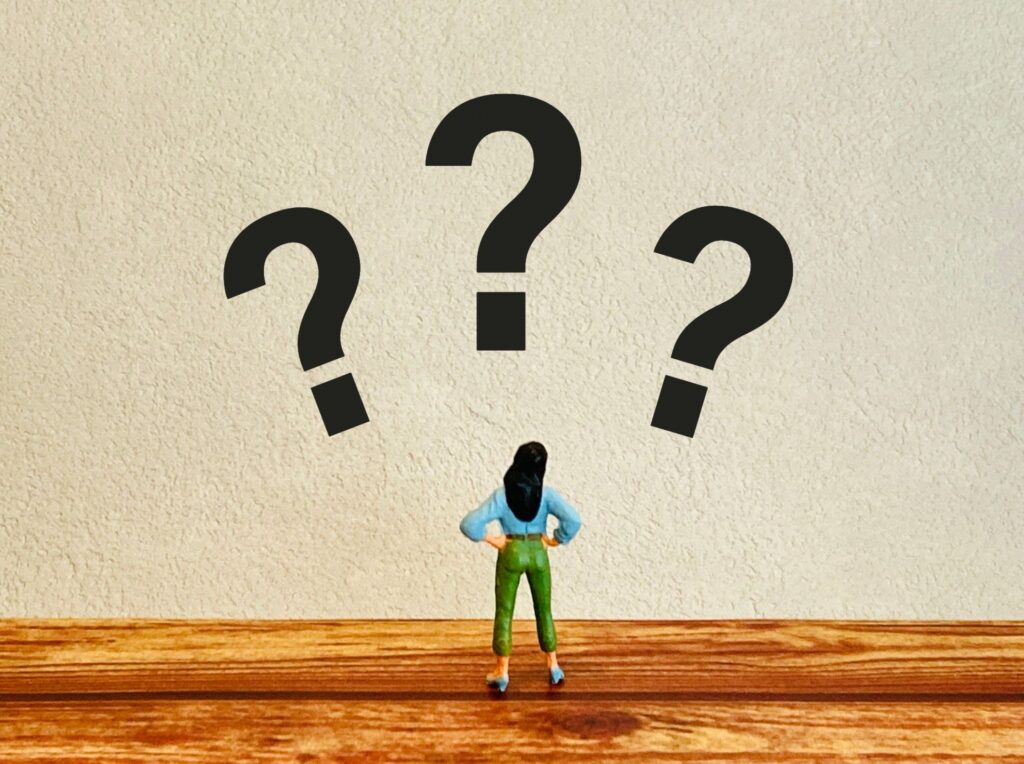こんにちは、皆さん!ミーミルメディア編集長のしげっちです。最近、ニュースで「劇症型溶連菌感染症」について取り上げられることが多くなりましたね。「溶連菌って子どもがよくかかる喉の病気じゃないの?」と思っている方も多いのではないでしょうか。実は同じ溶連菌でも、通常の感染症と劇症型では全く違う病気なんです。今日はその違いについて、分かりやすく解説していきますね!
溶連菌とは?基本的な知識から
溶連菌は正式には「溶血性連鎖球菌」と呼ばれる細菌です。この菌にはいくつかの型があり、特にA群溶血性連鎖球菌(GAS)が主に病気を引き起こします。子どもたちの間でよく見られる「溶連菌感染症」は、このA群溶血性連鎖球菌が喉に感染して起こる咽頭炎や扁桃炎が一般的です。
通常の溶連菌感染症の症状は、38〜39℃の発熱や喉の痛みが代表的。体や手足に小さな赤い発疹が出たり、舌にイチゴのようなツブツブができる「イチゴ舌」が特徴的です。また、頭痛や首のリンパ節の腫れ、腹痛や嘔吐などの症状も見られることがあります。風邪と違って咳や鼻水が少ないのも特徴のひとつですね。
劇症型溶連菌感染症とは?怖い理由を解説
一方、「劇症型溶血性連鎖球菌感染症」(STSS:Streptococcal Toxic Shock Syndrome)は全く別物と考えた方がいいでしょう。これは同じA群溶血性連鎖球菌が原因ですが、菌が筋肉や血液、肺などに侵入して急速に進行する非常に重篤な感染症です。
劇症型の特徴は、数時間から数日の間に症状が急激に悪化すること。主に手足の先端が赤くなり強い痛みを感じ、水ぶくれや血豆のようなものができます。そこから急速に症状が広がり、菌が血液に乗って全身に回ると(菌血症)、血圧低下、ショック状態、多臓器不全へと進行し、最悪の場合は命を落とすこともあるのです。
通常型と劇症型の違いはどこにある?
同じ溶連菌なのに、なぜこんなに症状に違いが出るのでしょうか?
1. 菌のタイプの違い
溶連菌といっても様々なタイプがあり、特に強い病原性を持つ特定のタイプ(毒素産生株やM株など)が劇症型の症状を引き起こすと考えられています。喉が好きな溶連菌もいれば、皮膚や筋肉が好きな溶連菌もいるというわけです。
2. 感染する部位の違い
通常の溶連菌感染症は主に喉に感染しますが、劇症型では皮膚の下の組織や筋肉に感染し、「壊死性筋膜炎」という状態を引き起こします。
3. 感染する人の違い
通常の溶連菌感染症は子どもに多いのに対し、劇症型は30歳以上、特に高齢者に多く見られます。また、心臓疾患、腎臓病、肝臓病、糖尿病、悪性腫瘍などの基礎疾患がある方はリスクが高くなります。
最近なぜ劇症型溶連菌感染症が増えているの?
2024年に入って劇症型溶連菌感染症の患者数が急増していると報告されています。これまで国内では年間100〜200人程度の報告でしたが、2024年2月18日までにすでに338例が報告されているそうです。
この増加の理由としては、コロナ禍が終わり人との接触が増えたことが考えられます。マスク着用や手洗いなどの習慣が減り、細菌への曝露が増えた結果、様々な感染症が増加している可能性があります。また、コロナ禍で細菌一般に対する免疫が減っていることも一因かもしれません。
劇症型溶連菌感染症を予防するには?
劇症型溶連菌感染症は稀な病気ではありますが、増加傾向にあることは確かです。予防のためには以下のことに気をつけましょう。
- 手洗いやうがいを徹底する
- 皮膚に傷がある場合は清潔に保つ
- 体調不良時は無理をしない
- 高齢者や基礎疾患のある方は特に注意する
また、手足の先端が赤くなり強い痛みを感じる、水ぶくれができる、症状が急速に広がるといった症状がある場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。早期診断と迅速な対応が生命予後を左右する重要な因子となります。
まとめ:過度に怖がらず正しい知識を持とう
劇症型溶連菌感染症は確かに怖い病気ですが、まだ稀な疾患であることも事実です。過度に恐れるのではなく、正しい知識を持ち、異変を感じたらすぐに医療機関を受診することが大切です。
皆さんも「案ずるより産むが易し」の精神で、必要以上に心配せず、でも必要な注意は怠らないようにしましょうね!
「知識は恐怖を打ち消す最良の武器である」 – エドマンド・バーク
今日も最後まで読んでくださってありがとうございました!健康で元気に過ごせますように!