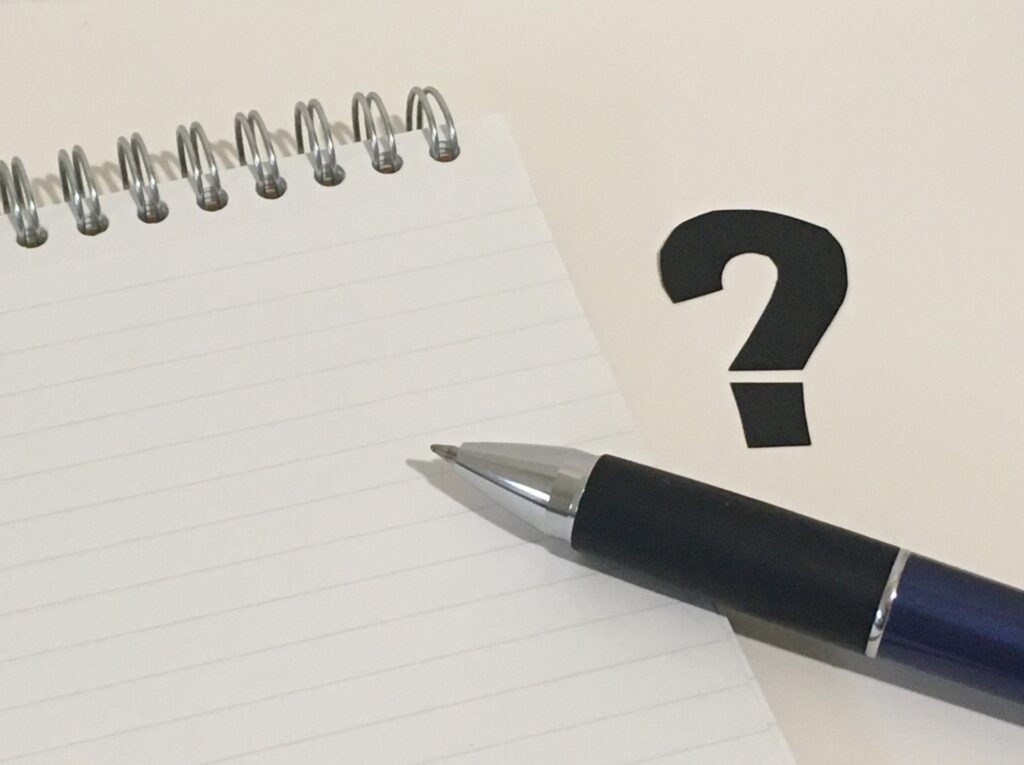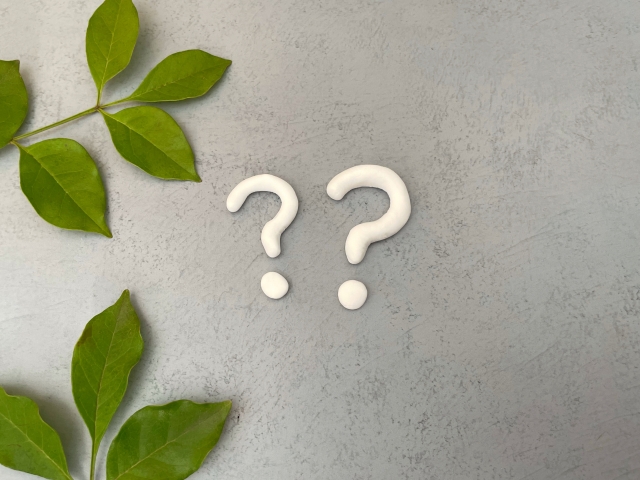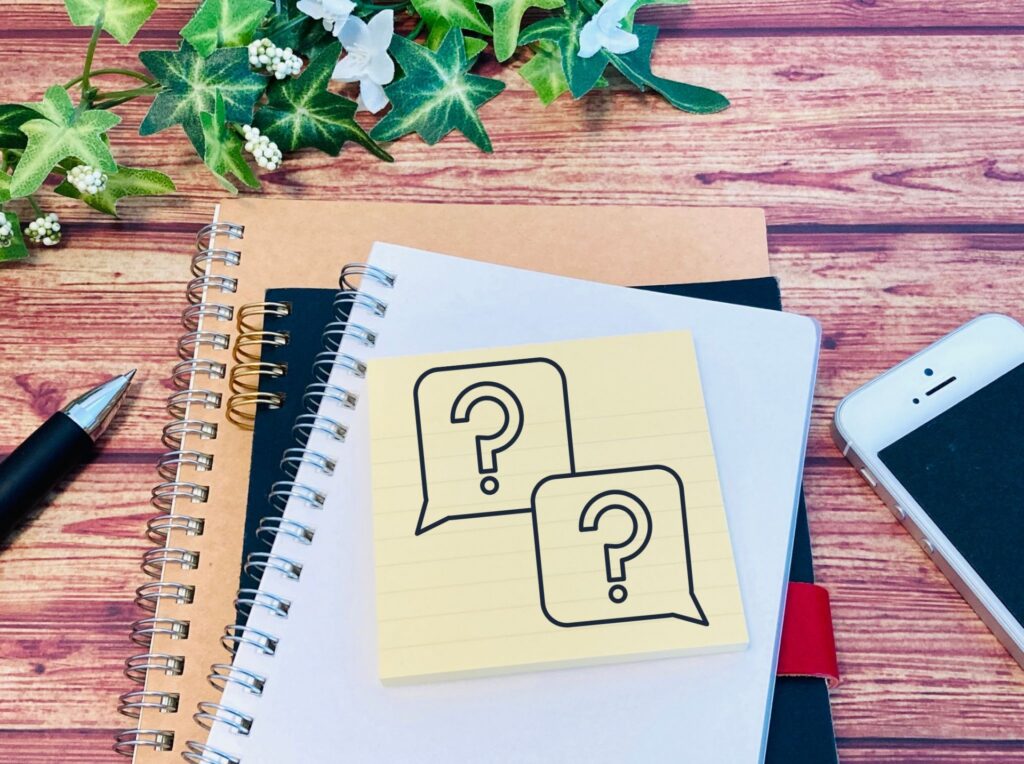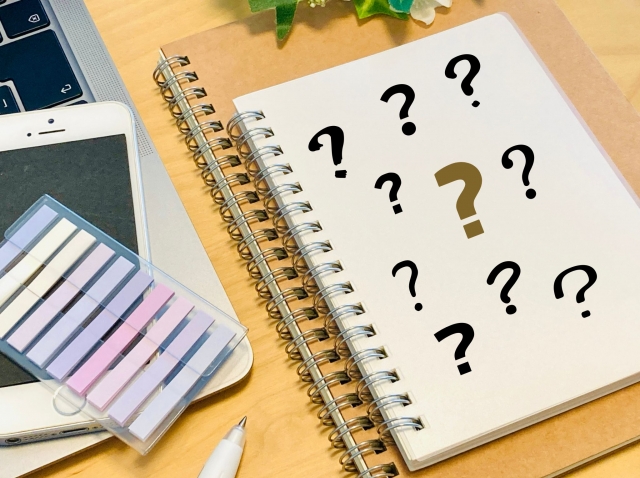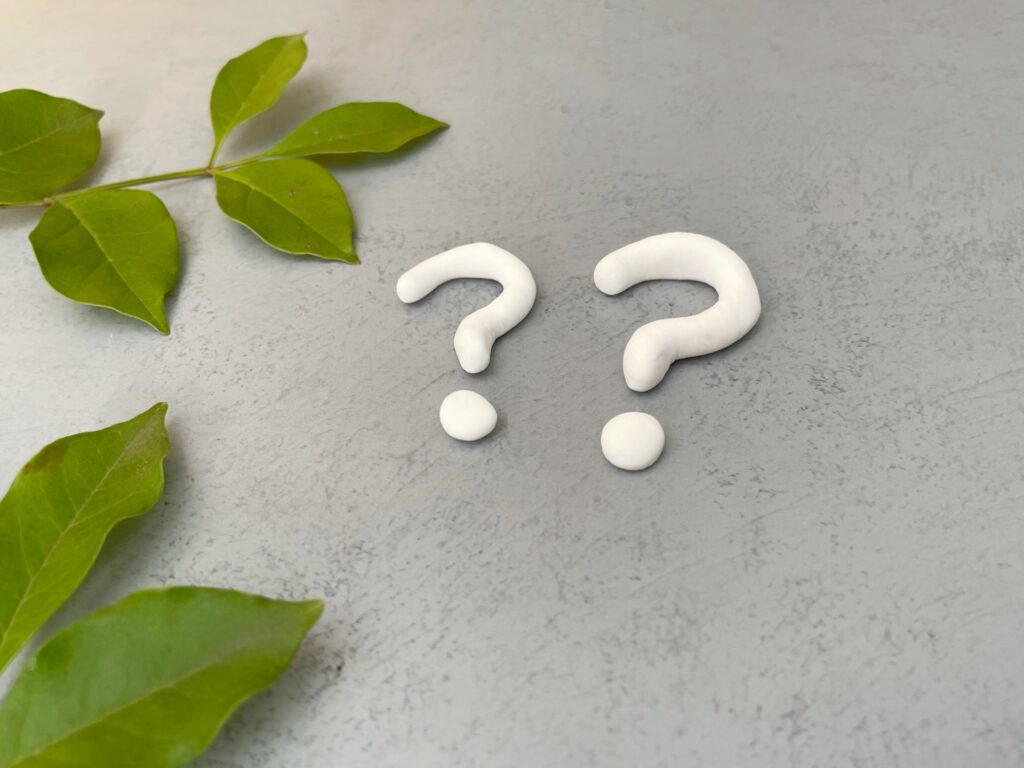こんにちは、皆さん!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日は日本の仏教について、特に「浄土宗と浄土真宗の違い」について詳しくお話ししていきたいと思います。
お墓参りや法事の時期になると、「うちの宗派って何だっけ?」と思うことありませんか?実は日本人の多くが所属している浄土宗と浄土真宗、名前は似ていますが、いくつかの重要な違いがあるんです。今回はその違いをギュウギュウに詰め込んでご紹介します!
浄土宗と浄土真宗の基本的な違い
まず押さえておきたいのは、浄土宗と浄土真宗の基本的な違いです。両方とも日本の仏教の中でも特に有名な宗派ですが、浄土真宗は日本で最も信仰者が多い宗派として知られています。
浄土宗と浄土真宗の基本的な違いは主に3つあります。
まず「開祖」です。浄土宗の開祖は法然上人で、平安時代末期に開かれました。一方、浄土真宗の開祖は法然の弟子である親鸞聖人で、鎌倉時代に成立しました。
次に「本山」です。浄土宗の総本山は京都の「知恩院」、浄土真宗は「本願寺」を本山としています。ちなみに、浄土真宗は「西本願寺を本山とする浄土真宗本願寺派(お西さん)」と「東本願寺を本山とする真宗大谷派(お東さん)」の二つに大きく分かれています。
そして「時代」です。浄土宗は平安時代末期、浄土真宗は鎌倉時代に成立しました。
面白いことに、本尊はどちらも阿弥陀如来で共通しています。
教えの内容にみる違い
浄土宗と浄土真宗は、教えの内容にも違いがあります。親鸞は法然の弟子だったため、基本的な考え方は似ていますが、いくつかの重要な違いがあります。
浄土宗の教え
浄土宗では、「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えることで、誰でも極楽浄土に往生できると教えています。これは「専修念仏」と呼ばれる考え方です。
浄土宗では、念仏を唱えることそのものを重視し、これを「自力念仏」と呼びます。つまり、念仏を唱える行為自体が極楽往生への道とされているんですね。
また、浄土宗では「成仏」と「往生」を区別して考えます。極楽浄土に往生した後、そこで修行して成仏すると考えるんです。
浄土真宗の教え
一方、浄土真宗では、阿弥陀仏の救いを信じるだけで救われるという「他力本願」の考え方を強調しています。念仏は修行としてではなく、阿弥陀仏への感謝の表れとして唱えるものとされています。
浄土真宗では「阿弥陀様が救ってくださる」と信じることで往生できるとし、それ以降は感謝の行ないとして念仏を唱えるという考え方です。
親鸞は「自分の罪を自覚した悪人こそが救われる」と説きました。これは、悪人のほうが善人よりも自分の「悪いところ」を自覚しているので、より阿弥陀仏にすがる気持ちが強いからだとされています。
僧侶の生活と戒律の違い
浄土宗と浄土真宗では、僧侶の生活様式や守るべき戒律にも大きな違いがあります。
浄土宗の僧侶と戒律
浄土宗の僧侶は、伝統的な戒律を守ることが求められます。「結婚してはならない」「坊主でなければならない」「肉を食べてはならない」など、出家者として禁欲的な生活を送るのが一般的でした。
また、「不殺生」(どんな生き物も殺さない)や「不邪淫戒」(性的関係を持たない)といった五戒を守る必要があります。
浄土真宗の僧侶と戒律
対照的に、浄土真宗の僧侶には特定の戒律がなく、髪型も自由で、結婚や肉食も認められています。これは、親鸞聖人自身が結婚し、家庭を持っていたことに由来します。
親鸞は「すべての人が差別なく、幸せになれることこそが本当の仏教」と考え、在家信者と僧侶の区別をあまりつけませんでした。浄土真宗では、共に阿弥陀仏の教えを実践することが重視されているんです。
仏壇と本尊の違い
浄土宗と浄土真宗では、仏壇の形や本尊の祀り方にも違いがあります。
浄土宗の仏壇と本尊
浄土宗の仏壇は、主に木目の美しい唐木仏壇が用いられます。本尊は阿弥陀如来の木像や絵像が一般的です。
配置としては、中央に阿弥陀如来像を安置し、向かって右側に高祖善導大師、左側に法然上人の像を配置することが多いです。また、最上段に位牌を安置するのが一般的です。
浄土真宗の仏壇と本尊
浄土真宗の仏壇は、全体が金色の金仏壇が特徴です。本尊としては、阿弥陀如来の名号(「南無阿弥陀仏」と書かれた掛け軸)を用いることが一般的です。
向かって右側に開祖である親鸞聖人の絵像や「帰命尽十方無碍光如来」の十文字、左側に第8代宗主蓮如上人の絵像や「南無不可思議光如来」の九文字を配置します。
また、浄土真宗では位牌を用いず、過去帳を使用するのが一般的です。さらに、浄土真宗は本願寺派(西本願寺)と大谷派(東本願寺)で仏壇の柱の色に違いがあり、本願寺派では仏壇内部の柱が金色、大谷派では黒色に塗られています。
お経と念仏の違い
浄土宗と浄土真宗では、重視するお経や念仏の唱え方にも違いがあります。
浄土宗のお経と念仏
浄土宗では、「阿弥陀経」「観無量寿経」「無量寿経」の三つをまとめて「浄土三部経」と呼び、特に重視しています。これらのお経は、阿弥陀仏の教えや極楽浄土の様子を説いています。
浄土宗では、「南無阿弥陀仏」と十回唱える「十念」という唱え方が一般的です。念仏を唱えることそのものが極楽浄土への道と考えられています。
浄土真宗のお経と念仏
浄土真宗でも「浄土三部経」を大切にしていますが、特に「正信偈(しょうしんげ)」を重視します。これは親鸞聖人が阿弥陀仏の本願や浄土真宗の教えをまとめたもので、日常の勤行や法要でよく唱えられます。
浄土真宗では「南無阿弥陀仏」を唱える回数に特に決まりはなく、阿弥陀仏への感謝や信頼の気持ちを込めて念仏を唱えます。
また、浄土宗では「般若心経」を唱えることがありますが、浄土真宗では「般若心経」を唱えません。これは、浄土真宗が他力本願の教えを重視し、「般若心経」が自力での修行を説く内容とされているためです。
葬儀と法要の違い
浄土宗と浄土真宗では、葬儀や法要の内容や考え方にも違いがあります。
浄土宗の葬儀と法要
浄土宗の葬儀では、故人が極楽浄土へ往生し、その後修行を経て成仏すると考えます。そのため、授戒(仏弟子としての戒律を授ける)や引導(故人を仏の世界へ導く)の儀式が行われます。
葬儀の流れは、通夜、告別式(授戒・引導あり)、火葬、初七日法要という順序で進行することが多いです。浄土宗では、故人の冥福を祈るために四十九日や一周忌などの法要を重視します。
浄土真宗の葬儀と法要
浄土真宗では、故人は亡くなった瞬間に阿弥陀仏の力によって極楽浄土へ往生し、即座に成仏すると考えます。そのため、他の宗派で行われる授戒や引導の儀式は行われません。
葬儀の流れは、臨終勤行、通夜、葬儀・告別式(授戒・引導なし)、火葬という順序で進行します。浄土真宗では、故人の冥福を祈るというよりも、阿弥陀仏の救いに感謝する意味合いが強いです。
亡くなってすぐに極楽浄土に辿り着くと考えられているため、初七日に法要をする必要はないとされています。
お盆の違い
浄土宗と浄土真宗では、お盆の考え方や習慣にも違いがあります。
浄土宗のお盆
浄土宗では、一般的なお盆の習慣を重視します。先祖の霊がこの世に戻ってくると考え、お盆の初日に迎え火を焚き、最終日に送り火を焚いて先祖の霊を迎え入れ、送り出します。
また、家の軒先や仏壇の周りに盆提灯を飾り、先祖の霊が迷わず帰ってこれるように道しるべとします。さらに、仏壇とは別に精霊棚(しょうりょうだな)を設け、供物や位牌を供えて先祖を供養します。
浄土真宗のお盆
浄土真宗の教えでは、故人は阿弥陀仏の本願によってすでに極楽浄土に往生しており、特定の時期に霊が戻ってくるという概念はありません。
そのため、浄土真宗のお盆では盆提灯や精霊棚を設けることはせず、仏壇の飾り付けも通常と同様に行います。お盆は先祖を偲ぶとともに、阿弥陀仏や親鸞聖人の教えを聞き、自らの生き方を見つめ直す機会と捉えられています。
戒名と法名の違い
浄土宗と浄土真宗では、故人に授けられる名前にも違いがあります。
浄土宗の戒名
浄土宗では故人に「戒名」を授けます。戒名は以下の要素で構成されます:
院号(いんごう):「○○院」のように、故人の功績や人柄を表す称号
誉号(よごう):「誉」の字が含まれ、浄土宗特有の称号
戒名(かいみょう):仏弟子としての名前で、故人の徳を表す
位号(いごう):「居士」「大姉」「信士」「信女」など、故人の性別や地位を示す
浄土真宗の法名
浄土真宗では「戒名」ではなく「法名」と呼び、以下の要素で構成されます:
院号(いんごう):「○○院」のような称号
釋号(しゃくごう):男性は「釋」、女性は「釋尼」を用い、お釈迦様の弟子であることを示す
法名(ほうみょう):仏弟子としての名前で、通常は二文字で構成される
浄土宗では戒律を守ることを重視し、位号を用いますが、浄土真宗では阿弥陀如来の本願を信じることを重視するため、位号を用いず「釋」の文字を付けることで仏弟子となったことを表します。
やってはいけないこと
浄土宗と浄土真宗には、それぞれ「やってはいけないこと」があります。
浄土宗でやってはいけないこと
浄土宗では、以下のことは避けるべきとされています:
他宗派の教えや儀式を取り入れること
念仏を軽視すること
浄土真宗でやってはいけないこと
浄土真宗では、以下のことは避けるべきとされています:
位牌を用いること(代わりに「過去帳」を用います)
般若心経を唱えること
線香を立てて供えること(線香は寝かせて供えるのが正式です)
神棚を祀ること
清めの塩を使うこと(死を穢れとしないため)
まとめ:浄土宗と浄土真宗の選び方
浄土宗と浄土真宗は、どちらも阿弥陀仏を信仰する宗派ですが、多くの場合、生まれ育った家庭の宗派に従うことが一般的です。家族や親戚との関係を円滑に保つためにも、実家の宗派に合わせるのが無難でしょう。
結婚や転居により異なる宗派の環境に入ることもありますが、その際は新しい環境の宗派の教えや習慣を尊重し、柔軟に対応することが大切です。
ただし、無理に自分の信仰を変える必要はなく、最終的には自身の信仰心や家族との関係を考慮し、どちらの宗派に共感できるかを判断することが重要です。
いかがでしたか?浄土宗と浄土真宗の違いについて、少しはスッキリしましたか?宗教や宗派の違いについて普段はあまり意識することはないかもしれませんが、浄土宗では故人に「戒名」を授けます。戒名は以下の要素で構成されます:
- 院号(いんごう):「○○院」のように、故人の功績や人柄を表す称号
- 誉号(よごう):「誉」の字が含まれ、浄土宗特有の称号
- 戒名(かいみょう):仏弟子としての名前で、故人の徳を表す
- 位号(いごう):「居士」「大姉」「信士」「信女」など、故人の性別や地位を示す
浄土真宗では「戒名」ではなく「法名」と呼び、以下の要素で構成されます:
- 院号(いんごう):「○○院」のような称号
- 釋号(しゃくごう):男性は「釋」、女性は「釋尼」を用い、お釈迦様の弟子であることを示す
- 法名(ほうみょう):仏弟子としての名前で、通常は二文字で構成される
浄土宗では、以下のことは避けるべきとされています:
- 他宗派の教えや儀式を取り入れること
- 念仏を軽視すること
浄土真宗では、以下のことは避けるべきとされています:
- 位牌を用いること(代わりに「過去帳」を用います)
- 般若心経を唱えること
- 線香を立てて供えること(線香は寝かせて供えるのが正式です)
- 神棚を祀ること
- 清めの塩を使うこと(死を穢れとしないため)
いかがでしたか?浄土宗と浄土真宗の違いについて、少しはスッキリしましたか?宗教や宗派の違いについて普段はあまり意識することはないかもしれませんが、こうして詳しく見ていくと、それぞれの特徴や考え方の違いが見えてきますね。
ボクも今回、改めて調べてみて、「へぇ~、そうだったんだ!」と驚くことがたくさんありました。特に、浄土真宗の「悪人正機説」には目からウロコが落ちる思いでしたね。「自分の罪を自覚した悪人こそが救われる」という考え方は、なんだかホッとする部分もあります。
皆さんの中にも、「うちの宗派はどっちだっけ?」と思った人もいるかもしれません。でも、大丈夫!どちらの宗派も、阿弥陀仏の教えを基本としているので、根本的な部分では共通しているんです。大切なのは、自分の信仰心や家族との関係を大切にすることですね。
最後に、今日の名言を紹介して、この記事を締めくくりたいと思います。
「人生において重要なのは、自分が何をするかではなく、自分が何者になるかである。」 – トーマス・マートン(アメリカの修道士、作家)
この言葉は、まさに浄土宗や浄土真宗の教えにも通じるものがあるように感じます。自分の行動だけでなく、内面的な成長や信仰心を大切にすることの重要性を教えてくれていますね。
皆さん、今日も一日、笑顔で過ごしましょう!それでは、また次回の記事でお会いしましょう!