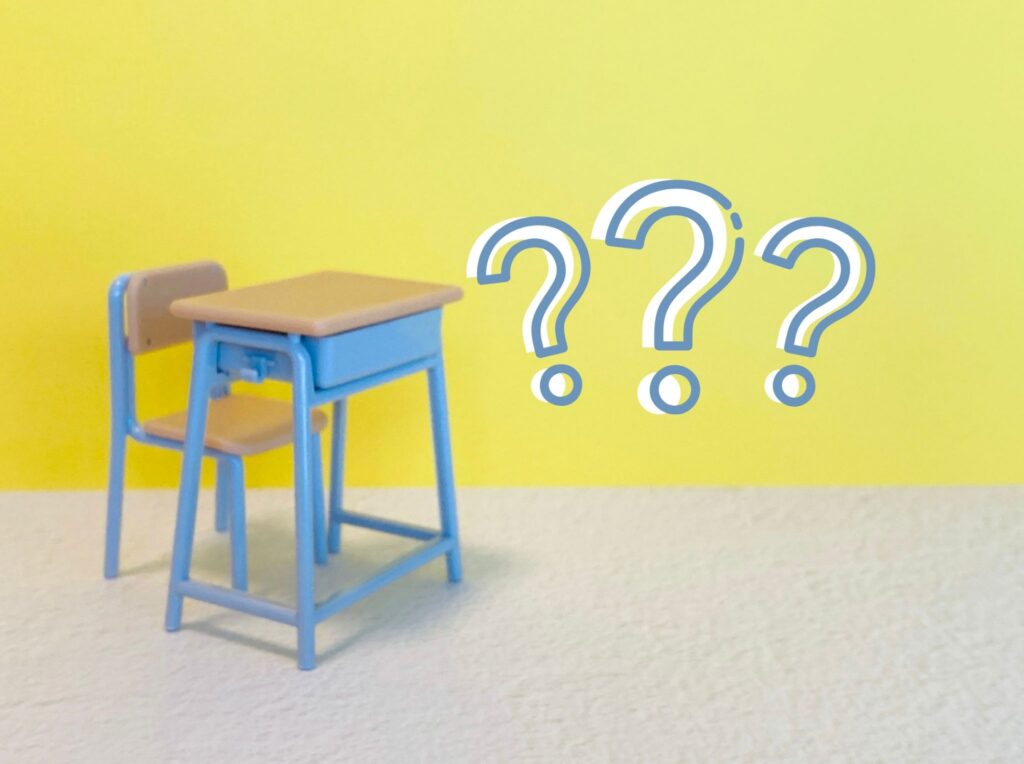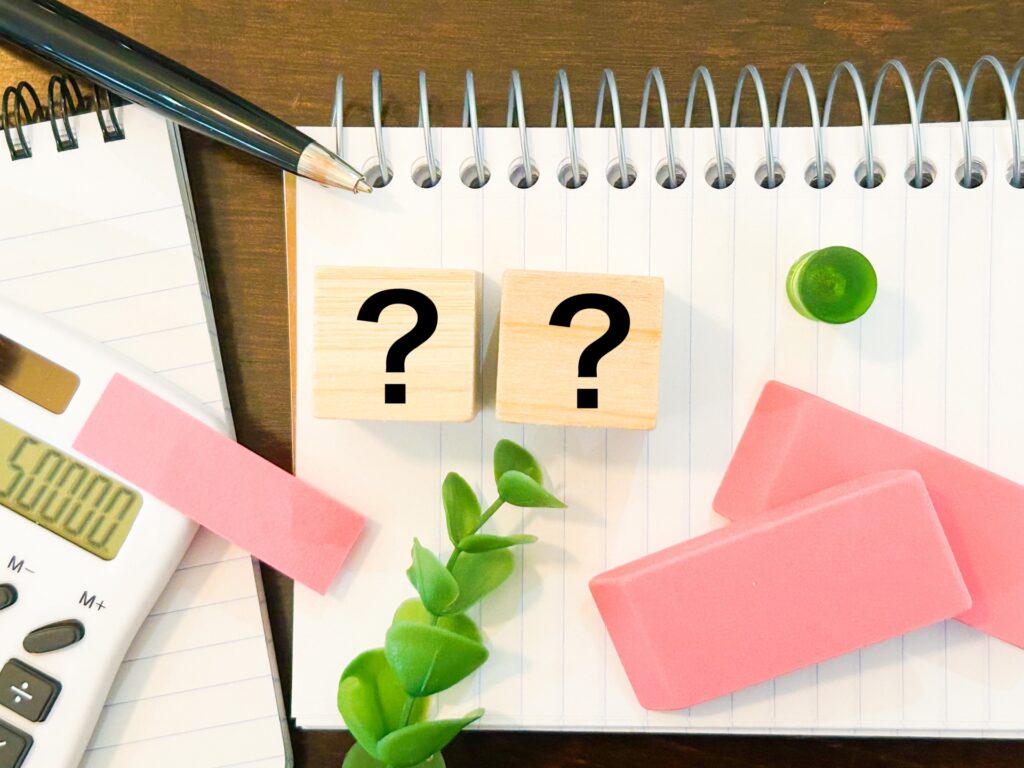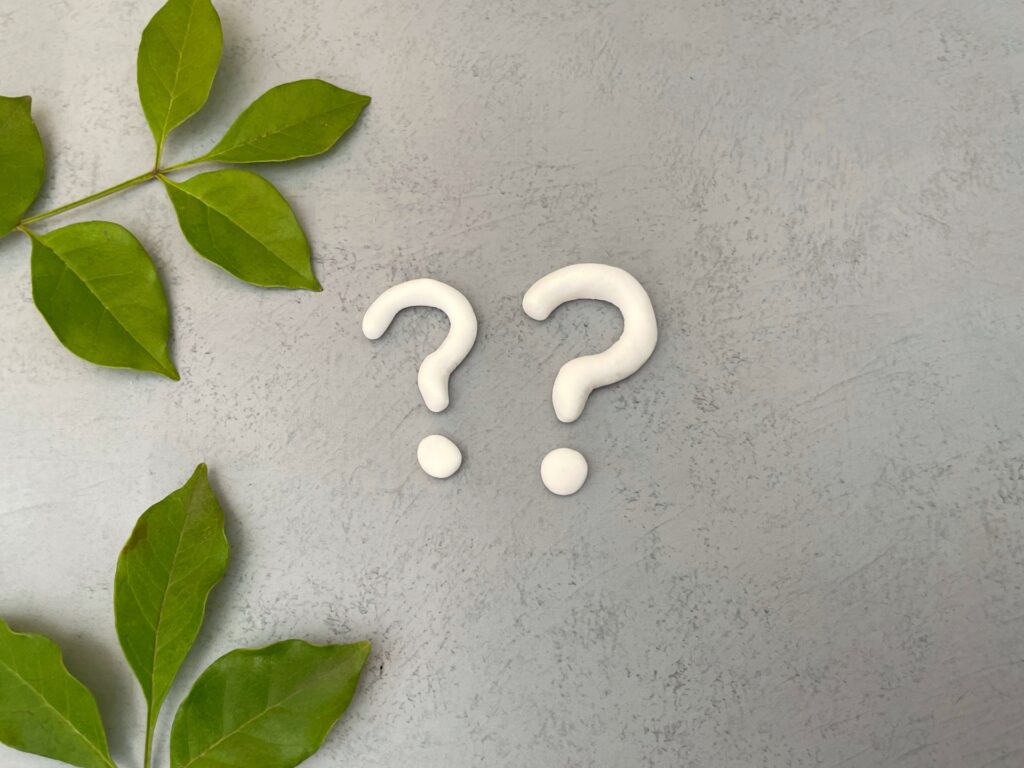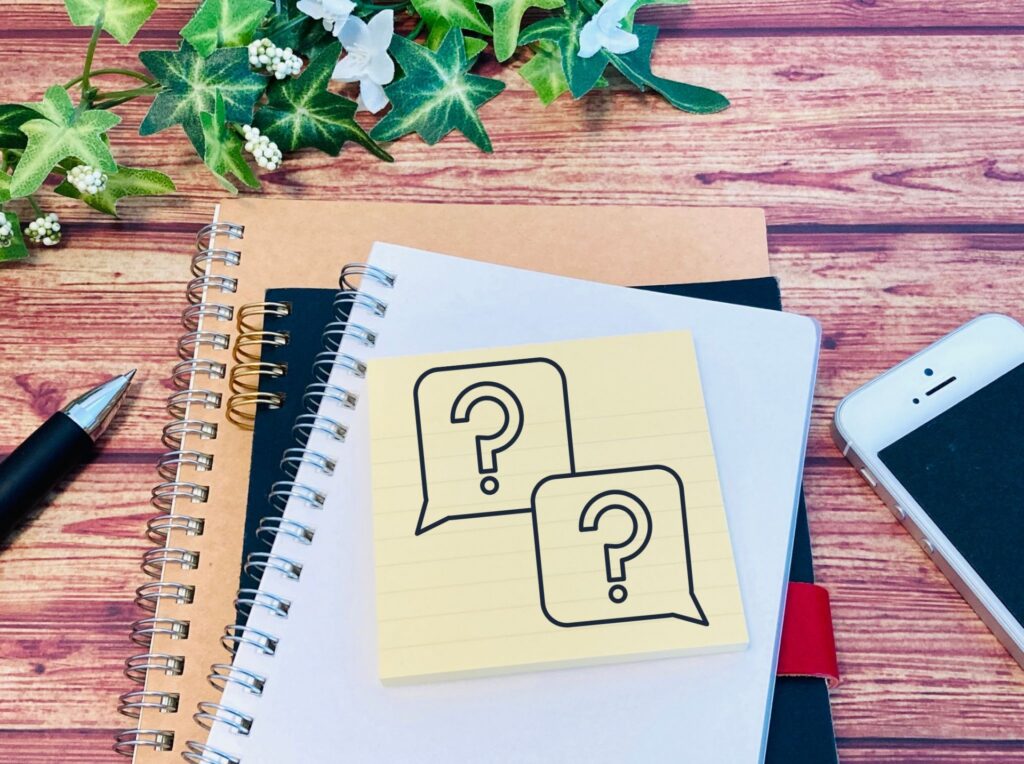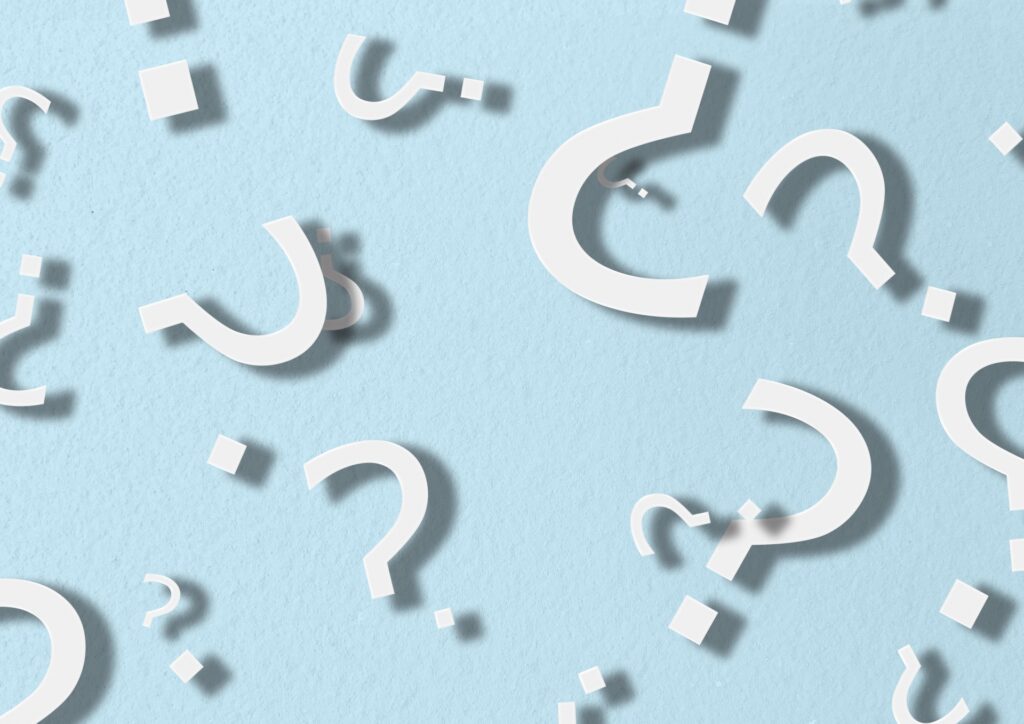こんにちは!ミーミルメディア編集長のしげっちです。今日は皆さんの健康に関わる大切な話題、「糖質と糖類の違い」について詳しくお話ししていきますね。
最近、スーパーやコンビニで「糖質オフ」「糖類ゼロ」という表示をよく見かけませんか?これらの違いって実はハッキリ理解している人は少ないんですよ。ボクも最初は「同じようなものでしょ?」と思っていたのですが、調べてみるとかなり違うことがわかりました!
それではさっそく、糖質と糖類の違いについて、わかりやすく解説していきましょう。
糖質と糖類の基本的な違い
まず最初に、糖質と糖類の関係性を簡単に説明すると、「炭水化物>糖質>糖類」という大小関係になっています。つまり、糖類は糖質の一部分なんです。
糖質は炭水化物から食物繊維を除いたものです。つまり「炭水化物-食物繊維=糖質」という計算になります。食物繊維は体内で消化吸収されないため、実際にエネルギー源となるのは糖質の部分なんですね。
一方、糖類は糖質の中でも単糖類(ブドウ糖や果糖など)と二糖類(砂糖や乳糖など)を指します。甘みを感じる成分の多くがこの糖類に含まれるんですよ。
糖質の種類と役割
糖質は大きく分けると以下の5種類に分類されます。
- 単糖類(ブドウ糖、果糖など)
- 二糖類(ショ糖、麦芽糖、乳糖など)
- 少糖類(オリゴ糖など)
- 多糖類(でんぷん、グリコーゲン、ペクチンなど)
- 糖アルコール(キシリトール、エリスリトールなど)
このうち、単糖類と二糖類が「糖類」に分類されるんですね。
糖質の主な役割は、体を動かすためのエネルギー源となることです。特に脳や神経細胞、赤血球のエネルギー源として欠かせない栄養素なんです。ご飯やパンなどの主食に多く含まれていて、私たちの活動を支えてくれています。
糖質が不足すると「低血糖」という状態になり、疲労感や集中力低下、ひどい場合は震えやめまい、意識障害を起こす危険性もあるので、過度な糖質制限は危険です!
逆に糖質を摂りすぎると、余分な糖質が中性脂肪として体内に蓄積され、肥満や生活習慣病のリスクが高まります。バランスが大切なんですね。
糖質を多く含む食品
糖質が多い食品には、以下のようなものがあります。
- 白米:茶碗1杯(150g)で約55.2g
- 食パン:6枚切り1枚(60g)で約26.6g
- うどん:1玉(250g)で約52.0g
- さつまいも:100gで約30.3g
- バナナ:1本(100g)で約21.4g
- りんご:1個(250g)で約35.3g
- どら焼き:1個(100g)で約55.6g
- ポテトチップス:1袋(60g)で約30.3g
- オレンジジュース:200mlで約24.0g
ゆるやかな糖質制限を行う「ロカボ」では、1食あたり20~40g、1日の総糖質量を130gに抑えることを推奨しています。ご飯1杯とうどん1玉、それにジュースを飲むだけで130gを超えてしまうので、意外と大変なんですよね。
糖類とは何か?
次に糖類について詳しく見ていきましょう。糖類は糖質の一部で、単糖類と二糖類から構成されています。
糖類の種類
糖類には以下のような種類があります。
- 単糖類:ブドウ糖、果糖、ガラクトースなど
- 二糖類:ショ糖(砂糖)、麦芽糖、乳糖など
これらは「糖」と聞いたときに多くの人が想像するような、甘みのもとになる成分です。
糖類の役割と特徴
糖類も糖質の一部なので、体のエネルギー源としての役割があります。ただし、糖類は糖質の中でも特に消化吸収されやすいという特徴があります。そのため、食後の血糖値が急激に上昇しやすくなるんです。
血糖値が急上昇すると、膵臓からインスリンが分泌されて血糖値を下げようとします。このインスリンには血糖を脂肪に変え、蓄える働きもあるんですよ。だから糖類の摂りすぎは肥満の原因になりやすいんです。
糖類を多く含む食品
糖類が多い食品には、以下のようなものがあります。
- グラニュー糖:100gで100g(当然ですね!)
- はちみつ:100gで約43.6g
- 干しぶどう:100gで約38.5g
- コーラ飲料:500mlで約57g
- チョコレート:70gで約28g
世界保健機構(WHO)では、1日の糖類摂取量を総エネルギー量の5%未満に抑えることを推奨しています。成人では約25gが目安です。コーラ500mlを飲むだけでこの2倍以上になってしまうんですね。ギョッとしますよね!
糖質制限と糖類制限、どちらが良いの?
「糖質制限」はダイエットや健康維持のための食事法として有名ですが、最近では「糖類制限」の方が良いのではないかという考え方も出てきています。
糖質制限では炭水化物全体を減らすことになりますが、炭水化物に含まれる食物繊維やでんぷん、オリゴ糖は腸内細菌のエサとなり、腸を元気にしてくれる短鎖脂肪酸を生み出します。つまり、炭水化物は適度に摂取することが大切なんです。
一方、単糖類や二糖類などの糖類だけを制限する「糖類制限」なら、必要な栄養素を摂りながら、血糖値の急上昇を防ぐことができます。特に加工食品に含まれる「添加された糖類」を減らすことが効果的です。
糖質・糖類との上手な付き合い方
最後に、糖質や糖類と上手に付き合うためのポイントをいくつか紹介します。
食べる順番を工夫する
食物繊維は糖の吸収をゆるやかにする働きがあるため、食物繊維の豊富な野菜から食べ始めるのがおすすめです。「野菜→おかず→主食」の順番で食べると、血糖値の急上昇を抑えることができます。
規則正しく食事をとる
食間が空くほど次の食事で血糖値が上がりやすくなります。1日3食規則正しく食べ、時間が空きそうなら低糖質のおやつを活用して空腹を防ぐといいでしょう。
甘味料を選ぶ
甘いものが好きな方は、血糖値が上がりにくいキシリトールやエリスリトールなどの糖アルコールを使った商品を選ぶのも一つの方法です。ただし、人工甘味料の甘さに慣れると、より強い甘味を求めるようになる可能性もあるので注意が必要です。
表示をよく確認する
「糖類ゼロ」と表示されていても、砂糖などの糖類はゼロでも、人工甘味料や糖アルコールなどの糖質は使用されている場合があります。「カロリーオフ」と表示されていても、100mlあたり20kcal未満であれば表示できるので、500mlのペットボトル1本で100kcal近くになることもあります。表示をよく確認して、摂取量に気をつけましょう。
いかがでしたか?糖質と糖類の違いについて、少しでも理解が深まったでしょうか。健康的な食生活のためには、これらの違いを知り、バランスよく摂取することが大切です。
皆さんも今日からの食生活で、糖質と糖類について意識してみてくださいね!
本日の名言として、こちらをご紹介します。
「健康であることの価値は、病気になって初めてわかる」 ― トーマス・フラー
健康は何物にも代えがたい財産です。日々の食生活を大切にして、元気に過ごしましょう!それではまた次回の記事でお会いしましょう!